新人歓迎会の季節も、だいたい一段落しましたね。
新しい職場への適応を迫られている新社会人のみなさん、息していますか?
新社会人や新一年生はもちろん、そうでない人でも飲み会が苦手な人はいらっしゃるでしょう。かく言う私も飲み会のたぐいが苦手で、アルコールが回るほど白けてしまうタイプでした。
以前、借金玉さんというブロガーの方が、「就職面接が茶番だと思う人のためのアドバイス」を書いていたことがありました。
皆さんは世の中の様々な営為を眺めたとき、「これは茶番だ」と認識する能力がとても高いのではないかと推察します。
実際、人間がなんか必死でやってるのを見て「くっだらねえなぁ」と思うことが非常に多いのではないですか?少なくとも僕はそうです。
アルバイトで単純な仕事をしたとき、街頭で募金を求める人を見かけた時、政治的な意見を掲げてデモをする人々を見かけた時、皆さんの中を通り過ぎるあの冷笑的な感情は否定できないでしょう。
リクルートスーツを着た新卒の群れを眺めてこの感情が起きない人間が僕のブログを読んでいるとは思えません。
私の場合は、この”茶番センサー”が飲み会で働きやすかったわけです。
しかし、捨てる神あれば拾う神あり。研修医だった頃の私は、年上医師や年上看護婦の何人かが
「今度の飲み会には出たくないぁ」
「面倒くさい」
などとこぼしているのを耳にしていました。
勤続数十年のベテランでも飲み会が得手とは限らない事実が、私には心強く感じられました。なぜなら、飲み会が苦手なままでも社会人として生きていけることを、彼らが証明しているように思われたからです。
「飲み会は“情報戦“」という理解
さて、それから数年が経ち、私は「職場の飲み会は“情報戦“だ」と考えるようになっていました。
たとえば新人歓迎会。新人歓迎会は、飲み会のなかでも「人間観察」としての側面が露わになりやすいものです。
飲み会で新人がどのように振る舞い、誰とどんなことを話すのかを眺めていれば、その新人の人となりや社会性がおのずと明らかになります。
「新人をのぞく時、新人もまたこちらをのぞいているのだ」というのも事実ですが、新人とベテランではキャリアに差があり、新人側はアウェーの条件で参加していますから、新人歓迎会の人間観察はベテラン側に地の利があります。
また、通過儀礼として新人が演し物をやらされる場合なども、そちらに気を取られてしまい、どうしても観察が後手に回りがちです。
また、それ以外の飲み会でも、飲み会での人の動きや会話に注意を傾けていると、普段は見えにくかった人間関係の相関図が見えやすい瞬間というのがあって、職場の人間関係の相関図マッピングが大幅にアップデートされることもあります。
はい。こういうやつですね。
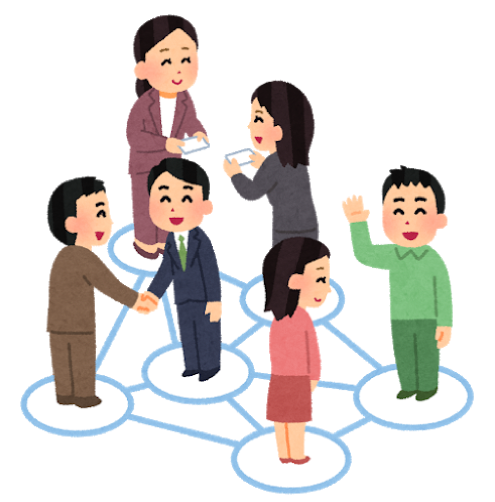
人間関係の相関図を頭の中に叩き込んでおくことは、たいていの職場において有効な処世術です。
これを読み誤ったまま働いていると、わけもわからないまま上司や同僚の不興を買ってしまったり、いつの間にか苦しい立場に置かれていたり、ろくなことがありません。
ちょっと遅れていた私は、アラサーになってようやくその重要性に気づくようになり、飲み会は相関図をアップデートするための貴重な機会だと思うようになりました。
そして情報を集めているのは自分だけではなく、他の飲み会参加者も同じですから、「これは、お互いに情報を出し合って相関図をアップデートしあう一種のゲームだな」と認識するようになりました。
私は根っからのゲーム好きなので、ゲームだと割り切ってしまうと大抵のことは面白がれてしまいます。飲み会のことを情報戦だと捉えるようになってからは、ある程度飲み会が面白いと感じるようになりました。
なにより、参加すること自体に意義がある
それからさらに十数年が経ち、最近の私は、職場の飲み会を「仲間であることの意志表示の場」と捉えるようになりました。
さきに書いたとおり、職場の飲み会には“情報戦”としての側面がついて回ります。
しかしそれは副次的なもので、そもそも、職場の飲み会に顔を出すこと自体に意義があり、出席するという行為がメタメッセージとして重要と考えるようになりました。
以前私は、「内容の無いコミュニケーションを馬鹿にしている人は、何もわかっていない」というブログ記事を書いたことがありました。
挨拶には内容は無い。昔は、“お早うございます”にも内容があったのかもしれないが、もはやテンプレート化している今では、無いも同然だろう。だが、社会人になったら真っ先に挨拶が問われることが示しているように、コミュニケーションに占める挨拶のウエイトは馬鹿にできない。
日和や季節についての会話や、女子高生同士のサイダーのような会話も、しばしば「内容のない会話」の例として槍玉に挙げられる。しかし、交わされる言葉の内容そのものにはあまり意味が無くても、言葉を交換しあい、話題をシェアっているということ自体に、大きな意味がある。
言葉には、一種の“贈り物”みたい効果があって、言葉を交換しあうことが人間同士に信頼や親しみを生む。というより、黙っていると発生しがちな、不信の発生確率を減らしてくれる、と言うべきかもしれない。
職場の飲み会も、基本的にはこれと同じではないかと今は思うのです。
時間やお金を出し合って、同じテーブルを囲んで宴の席をもうける。そして飲食を共にする――この、飲み会というプロセスをとおして、私達はお互いがメンバーシップの一員であることを確認しあいます。
逆に言うと、飲み会のたぐいはメンバーシップの“点呼“のような機能を持ち合わせているとも言えるでしょう。一度や二度、飲み会を欠席したからといって問題が生じるわけではありませんが、何回も連続で欠席していれば不自然に思われる程度には、飲み会の“点呼“機能は無視できません。
そう考えると、かつて、年上の医師や看護師が「今度の飲み会も出たくない」「面倒くさい」と言いつつも、割と律儀に出席していたことの辻褄が合うのです。
「メンバーシップの一員であることの確認」の重要性を、彼らはよく心得ていたのでしょう。
「“点呼“なんて、タイムカードで十分じゃないか」と言いたくなる人もいらっしゃるかもしれません。
が、ただタイムカードを打つのと、飲食を共にするのでは、人間関係に与える影響は全く違います。人間は、太古の昔から飲み会のたぐいを執り行ってきたわけですから、私は、そういう効果は馬鹿にしないほうが良いと踏んでいます。
この飲み会に限らず、世の中には、表向きは茶番や浪費のようにみえて、情報交換やメタメッセージとして重要な役割を担っているに営為がいろいろあります。
好悪は人によってさまざまでしょうけど、そういう営為に理解を深めて、そつなくこなせるようになっていくのも社会人の成長プロセスなんでしょう。
足下を掬われない程度にがんばっていきたいものですね。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma ブログ:『シロクマの屑籠』

(Photo:Nirava // is Ready for Miracles)














