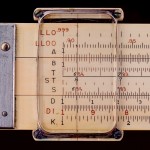いまどきの子どもは行儀が良い。
うちの子どもを見ていても、その友人達を見ていても、遠い街の見知らぬ子どもを見ていてもそう感じる。
もちろん子どもだから、多少の不備や不注意はある。
それでも高齢者には席を譲り、道路で出会った人には挨拶をし、道草をしないで登下校する。
そう、子どもが道草をしないのだ。
当直明けの平日が休みになった時、帰宅する私と学校に到着する子どもがすれ違うことがあるのだが、うちの子どもも含めて、子ども達はまっすぐ学校に向かっていく。
空想イメージ上のドイツ人のごとく、子ども達は時間に正確だ。
下校の時もそうで、学校から自宅まで、まっすぐに帰ってくる。
授業が終わって自宅に着くまでの所要時間はいつも同じだ。
通学路の途中には、子どもがよく遊ぶ公園や神社もあるけれども、それらに立ち寄って遅れることは無いという。
実際、下校時間にそのあたりを散策してみると、真っ直ぐに下校する子どもの姿はどこでも見かけるが、カバンを脇に置いて道草に耽る子どもは見かけない。
よその学区ではどうなのか。私は住宅街ウォッチが趣味になっているので、出張などの折も、ちょうど下校時間を迎えた住宅地を歩き回ってウォッチしている。
やはり、道草する子どもはなかなか見かけない。道草を見かけないのは田舎でも都会でも同じだ。
子どもとは、こんなに道草しないものだっただろうか。
いや、子ども達は道草していた。割と最近まで。
この、私の疑問にズバリ答えてくれる本が見つかった。
その名も、『子どもの道くさ』。
2006年に出版された、小さな本である。
この本は、子どもが道草をとおして何を経験し、何を学んでいるのか、たくさんの写真をまじえて紹介している。
この写真がまたいい。昭和時代の片田舎で育った私には非常に懐かしく、日常的だった風景だ。
ミカン狩りをする子どもの写真。写真のなかの小学生は、よその家の庭のミカンを取りに来ている。
『子どもの道くさ』によれば、子どもたちの頭のなかにはそれぞれ独自の環境認知マップが描かれていて、天候や季節、気分にあわせて登下校のルートを変えているのだという。
だからミカンの季節には、ミカンのなる家に立ち寄って帰宅する。
私自身の子ども時代も、まさにそのようなものだった。
5月にはツツジの蜜が吸える庭園に立ち寄り、初夏には桑の実を、晩夏にはヒマワリの種をみんなで食べていた。
地元の人々は、子どもはそういう道草をするものだと思っていたらしく、バレでも叱られることはなかった。
天候や季節、気分次第で登下校のルートも所要時間もまちまちだった。
そしてピンポンダッシュ。
現在ではもう、死語になっているのではないだろうか。
私の時代にはまだピンポンダッシュは健在だった。
もちろん、褒められた遊びではあるまいし、毎日のようにピンポンダッシュしていたわけでもない。
けれども年に一度か二度ぐらいは、「ピンポンダッシュをやろう」という流れが発生したものである。
ただし、ピンポンダッシュをする家は「選んでいた」と思う。
桑の実やヒマワリが食べられる季節と場所を知っていただけでなく、どの家が危なくてどの家が危なくないのか、子ども時代の私たちは知ったうえで道草をしていた。
そうした地元の情報は、自分で歩き回って知ったり、同級生や年上から教わったりするものだった。
『子どもの道くさ』は2006年に出版された本で、写真に写っている乗用車をみる限り、2000年±5年程度の間に撮影されたものと推測される。
00年代のはじめ頃まで、こうした道草は残っていたのだろう。
「安全」と「効率性」が道草を禁じる
しかし、2019年現在、私が子どもの道草を見かけることは少ない。
うち子どもに「ねえ、道草しないの?」と聞くと、全くしないと答えるし、実際、道草している様子がない。
学友たちも道草をせずまっすぐに帰っているという。
もちろんうちの子どもは、いつの季節に、どこに寄ると何が食べられるのかなんて知らない。
地元のどこにどういう人が住んでいて、どの家が危ないのかを知っているそぶりもない。
かろうじて、道草という言葉だけが子ども世代に伝わっている。
なぜ、道草は衰退したのか?
『子どもの道くさ』の筆者である水月昭道氏は、同書のなかで以下のようなことを述べている。
地域社会は子どもの安全を最優先に求め始めている。
安全性の確保こそが全てというような風潮が社会に浸透し始めているのである。
地域で偶然見かけた見知らぬ人に過剰に反応し疑いを抱いたり、地域行事への子どもの参加を見合わせるといったことも起こっている。
ひとつには、子どもの「安全」。
時代を経るにつれ、人々は子どもの安全に神経質になっていった。
登下校の際に子どもの身に何かあっては大変、というわけである。
道草のなかには、塀の上を歩いたり道路で遊んだりするものもあるから、安全性という意味では道草なんて無いほうが良いに決まっている。
真っ直ぐ家に帰り、そこから塾や稽古事などに出掛けたほうが、事件や事故に巻き込まれるリスクは少なくなる。
内閣府が行った、『平成25年度「家族と地域における子育てに関する意識調査」』を見ても、現代の父兄が地域社会に期待しているのが「安全」であることがみてとれる――地域で子育てを支えるために必要なことを問うたアンケートの1位は「子どもの防犯のための声かけや登下校の見守り」だった。
子どもの安全にセンシティブな社会は、子どもの道草を許さないだろうし、実際、道草が盛んだった時代と比較すると、子どもが事件や事故に巻き込まれる件数は低下し続けている。
また水月氏は価値観の変化にも言及している。
なぜ、道くさは社会的に見て悪者のように扱われるのだろうか。
二〇世紀の価値観とのかかわりに注目したい。前世紀は、効率追求型の社会のなかで何ごとも合理的であることが好ましいことのように信じられてきた。
科学技術の発展と経済成長を背景に、この価値観は絶対的な力を持ち得ていた。
社会全体がこうした価値観の軸にあるとき、道くさはどのように位置づけられるだろうか。
効率性を至上命題とすると、資本主義的な価値観のもとでは、子育てもまた、効率的に行われなければならない。
放課後の時間は有限のリソースなのだから、道草のような、何の役に立つのかわからない(というより、おそらく厄介事やリスクをもたらしかねない)時間はできるだけ避け、目的にかなった時間の過ごし方をすべきとなる。
インターネットには「効率厨」というスラングがあるが、この「効率厨」の考え方で子育てに臨むなら、道草など許されるものではなく、目的意識をもったスケジュールにもとづいて放課後を過ごすべき、ということになる。
都合が良いのは地域の大人も同じ
そして水月氏自身はあまり触れていないが、道草を禁じることによって「安全」や「効率性」を得られるのは、子どもだけではない。
むしろ、地域の大人たちのほうが「安全」や「効率性」を得られるのではないか。
子どもが道草をし、たとえば私有地にあった穴に落ちて服が汚れた時、「どうして穴なんか開けてあったんだ、おかげでうちの子の服が汚れてしまったじゃないか」と父兄に言われたら、その私有地の持ち主はいい気はしないだろう。
服が汚れたぐらいならまだいい。
裏庭の池に勝手に子どもが遊びに来て、そこで溺れた時に責任を問われたらかなわない。
責任という視点で考えるなら、あらゆる私有地は道草禁止にすべきだし、あらゆる路上の遊びも禁じなければならないはずである。
子どもの危険は、大人の責任問題と背中合わせなのだから、「安全」という意識は子どもと大人の双方を守っていると言える。
しかも、子どもに何かを勝手にいじられたり、ミカンや桑の実を持っていかれたり、ピンポンダッシュで煩わしい思いをすることもなくなる。
上の写真が暗に示しているように、子どもを好き勝手に遊ばせておくと、モノを壊してしまいかねない。
街から道草する子どもがいなくなれば、モノを壊される心配もしなくて済むようになる。
現代社会は、効率性を重んじる資本主義的なモノの考え方が行き渡っていると同時に、子どもの命を重んじる個人主義的なモノの考え方も行き渡っている。
くわえて、法律に従って責任の所在や権利について考える契約社会的なモノの考え方も行き渡っている。
この、資本主義-個人主義-契約社会が三位一体になったイデオロギーにもとづく限りにおいて、親が子どもに道草を許す余地は無いし、地域の大人も子どもの道草を許容する余地が無い。
『子どもの道くさ』のなかで水月氏は、このままでは道草が廃れてしまい、道草が提供していた社会機能も失われることを懸念しているし、その懸念は尤もなものではある。
しかし世の中には優先順位があり、たとえ道草がなんらかの社会機能を担っていたとしても、資本主義や個人主義や契約社会のロジックに逆らってまで大目にみてもらえるものだとは、ちょっと考えられない。
自分の家の子どもが安全でなくなることを許せず、私有地を遊び場にされた挙げ句、安全管理の責任を問われることも許せない現代社会である以上、もう社会には道草の居場所はなくなったのだ、と私は思う。
そして道草の無くなった世界で
たぶん私たちはもう、道草が滅んだ後の世界を生きている。
道草が無くなって得られたものは明らかだ――安全性が高まり、効率性も高まり、責任を巡って揉めるリスクも遠のいた。
では、道草が無くなって失ったものとは何か。
ひとつには、子どもと地域の大人の接点。
うちの子どもは、地域にどんな大人がどんな風に暮らしているのかを、あまり観察していない。
知っているのは、せいぜい友人の親ぐらいまでである。
神経質で怒りっぽい大人が地域のどこに住んでいて、おおらかでアイスをおごってくれることもある大人が地域のどこに住んでいるのかを、子どもたちは知らない。
道草せずにまっすぐ登下校する子どもは、地域の大人を知る機会を失い、地域の大人に知ってもらう機会をも失った。
だが、個人的には、それ以上に大きな喪失に思えるものがある。
それは子どもの認知……というより子どもの世界観だ。
うちの子ども、あるいはうちの子どもの友人達を見ていて私が思うのは、彼らが「点と線からなる世界観」を生きていることだ。
どういうことか。
うちの子どもは、自宅と学校という二つの点と、それを結ぶ通学路という線の世界を生きている。
あとはせいぜい、友人と遊ぶ公園や神社、学習塾やコンビニといった幾つかの点と、それらを行き来する道路という線が加わるぐらいだ。
道草が許されていた私の時代は、そうではなかった。
学校と自宅という点の間には、無限といって良いほどのルートがあった。
というよりあらゆる場所に立ち寄り、あらゆる場所に遠回りして遊んでいたのだから、私の世界観は「面」からなっていたと言える。
必然的に、昭和時代の私は学校と自宅の間について、うちの子どもよりもずっと多くのことを知っていたし、多くのものを見ていた。
この左右の模式図を比べていただければ、「面の世界観」と、「点と線の世界観」の違いが伝わるのではないかと思う。
かつての私は地域のどこにでも立ち寄り、どこでも遊んでいたから、近所のあらゆる場所を認知していたし、認知していなければならなかった(面の世界観)。
対して、2019年のうちの子どもは、自宅と学校、公園や学習塾やコンビニといったいくつかの点と、それらを行き来するための線しか知らない。知る必要も感じていない(点と線の世界観)。
2019年のうちの子どもとて、何も見ていないわけではない。
たとえば、通学路の途中で見つけた動物の死骸や、咲いている花などは詳しく見ている。
けれども昭和時代の私とは違って、近所のどのあたりにどんな植物が生えているのか、どこの家にどんな大人が住んでいるのかを、うちの子どもは知らない。
むしろ私のほうがよく見て、よく知っているとさえ感じる。
「面の世界観」で生まれ育った私に見えているものが、「点と線の世界観」に住んでいるうちの子どもには見えていないのだとしたら……。
資本主義-個人主義―契約社会の徹底した、安全で便利な現代社会では、「点と線の世界観」でもおそらく生きていけるのだろう。
それでも、上の表から薄らぼんやりと感じる直感として、私にはそれが小さくない喪失に思えてならない。
道草の喪失と、それに象徴される安全で効率的で契約社会にもとづいた世界観は、私たちが見ているもの・見えているものを、とても狭くしてしまっているのではないだろうか。
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

(Photo:Ryanda Maxima)