管理職は人を使うのが仕事だ。
ただ、誰もが人をうまく使えるわけではない。
「人を使う訓練」を受けたことのある人は極めて少数のため、その成果は個人の素養に大きく依存している。
したがって、管理職の悩みが「的はずれ」であることが頻繁に見受けられる。
そのうちの一つが「部下に自主性がない」、または「部下が自走しない」という悩みだ。
*
以前、「どうも部下が、自主的に動かないんですよね。そう言う人って、どうすればいいですかね?」という相談を受けたことがある。
彼は管理職になって2年目、現場での成果が認められて抜擢された若手管理職だ。
だが、この手の主観的な悩みは扱いが非常に難しい。
「自主的」という言葉が何を意味しているのか、人によって相当異なるからだ。
この場合、何を持って「自主的ではない」と彼が考えているのか確認をする必要がある。
私は尋ねた。
「自主的に……と申しますと?「自主的」かどうかに、なにか組織としての基準があるのですか?」
彼は言った。
「特に、基準はないのですが……、自分から動いて仕事をしない、というイメージです。」
「なるほど……」
これは多分、厄介なやつだ。
私は重ねて質問をした。
「えー、それは「部下のやりたいようにやってほしい」ということですか?」
彼は怪訝な顔をした。
「勝手にやられるのは困ります。」
私は辞書を確認した。
「自分から動く、というのは「勝手に動く」のと何が違うのですか?」
辞書によれば、「自主的」というのは、ほかからの干渉を受けずに自分で決定して事を行うこと、とある。
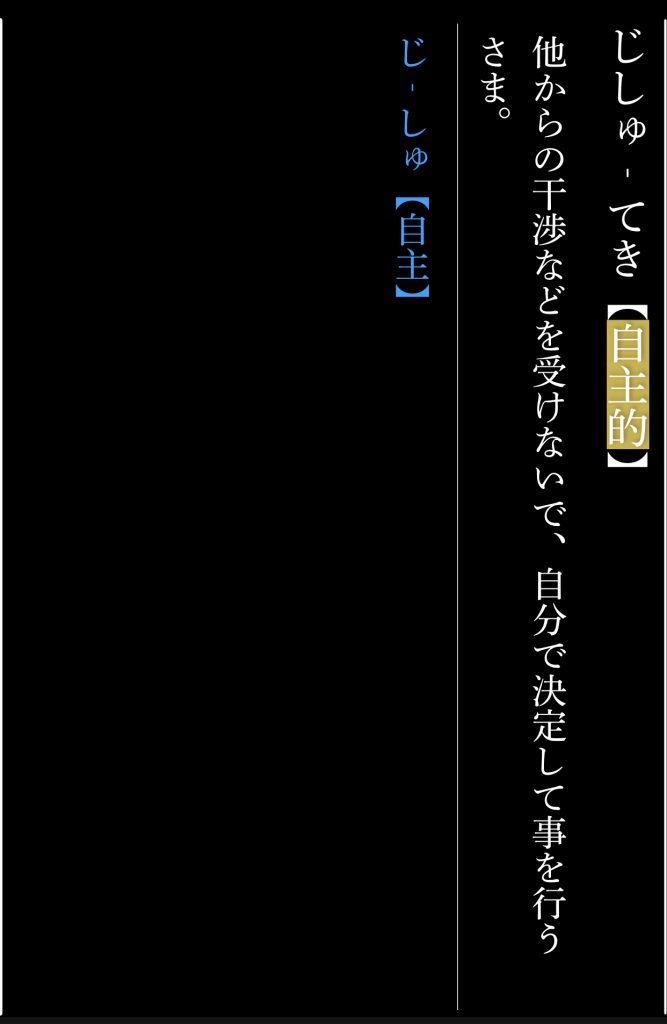
彼は「面倒だな」といった顔をした。正直な人だ。すぐに顔に出る。
が、彼は答えた。
「ちがいます。「自分から動く」というのは、逐一こちらの指示を待たなくても動ける、ということです。
自主性ではなく、自走する、というべきでしょうか。」
正直、この人の言う「ちがい」が、私には全くわからなかった。
私は質問した。
「上司の言うことに干渉されず、指示を待たなくても動くのは、「勝手」ではないのですか?」
「うーん、ちょっと違うんですよね……。こちらの意図をくんで動く、というか。」
「なるほど。」
彼に質問しても、これ以上は何も出てこないだろう。
おそらく、彼は自分の要求をまだ言語化できていない。言語化できてないことを、人にやらせるのは無理である。
部下が彼の指示に戸惑うのは当然だ。
*
そこで、私は聞き方を変えることにした。
「具体的にどんな事があったか、教えていただけないでしょうか。」
すると、彼はスラスラと答えた。
「私は自部署の特定の製品のマーケティングを任されました。メンバーは私を除いて3名です。」
「つまり、部下が3名ですね。」
「そうです。」
「先を続けてください。ちなみに、マーケティングはどういった成果を求められているのですか?」
「一番わかり易いところで言えば、問い合わせの増加です。目標値もあります。」
「いつまでに、どれくらい、といった数値はありますか。」
「今期中に、前年対比◯%アップ、という形であればあります。」
なるほど、そこは明確になっている。
「では、「部下が自主的に動かない」と判断した理由をいただけますか?」
「3人をそれぞれ、問いあわせのチャネル別に、ウェブ担当、既存客担当、代理店担当、としています。既存客担当と代理店担当は良いのですが、ウェブの担当の動きが悪いです。」
「具体的には?」
「ウェブは大きく分けると、ホームページからの問い合わせ、広告からの問い合わせ、メルマガからの問い合わせと3つの施策を動かしているのですが、広告とメルマガは外部の協力会社を使っているので、あまり心配はない状況です。」
「すると、ホームページですね。」
「そうです。期首にホームページのリニューアルをしよう、という方針を固め、その部下に任せることにしました。ところが進捗が悪く、こちらが逐一指示を出さないと、何もしないのです。」
「その担当者は、指示がないと動けない、ということでしょうか。」
「そうです。」
なるほど。
大体の状況はわかった。
だが、もう少し確認が必要だ。
「その人は、ホームページのリニューアルを以前にやったことがあるのですか?」
「ウチでは初めてです。ただ、前に居た会社で多少やった、と言ってたと思います。だから任せました。」
私は思い切って尋ねた。
「その仕事を、結局、任せられなかったのが、課題なのですね?」
「できれば任せたいのですが、もう少しでも自主的に動いてくれればいいのに、と思っています。」
*
事の本質は、簡単なのだ。
要するにその仕事を遂行するだけの知識と能力が、その部下になかった、という話であり、それを「自主性」という言葉で覆い隠しているだけである。
単純に、部下はホームページのリニューアルに関して、
・何をすべきか
・何を調べればよいか
・誰に聞けばよいか
など、仕事に必要なタスクがわかっていない。
上司に先んじて確かめたり、交渉したり、質問する力量もない。
だから仕事がスタックする。
そして、スタックしたことを上司に言うと、自分が馬鹿だと認識される(と思っている)ので、相談もしづらい。
そうして「自主性がない」という評価に落ち着くというわけだ。
だから、彼に必要なのは「自主性を身につける」ことではない。
現実に「何から手を付けて、何をなすべきか」を逐一教えることである。
*
そうした話を、その管理職にすると、彼は言った。
「どうすればいいかなんて、自分で調べたり、聞いたりすればわかるじゃないですか。」
私は首を振った。
「知識がある程度ないと、調べることもできないし、あなたのように怖い人に聞くのは難しいですよ。」
彼はまだ、納得していないようだった。
少なくとも彼は「ずっと自主的に動いてきた」という自負があるのだろう。
そして、それが功を奏したからこそ、その地位にいるのだ。
私は言った。
「部下の彼が、あなたと同じくらい優秀であれば良かったですね。」
実際、相手がとびきり優秀なら、
営業 → 売上を上げろ
技術者 → 納期に間に合わせろ
マーケター → 引き合いの数を増やせ
で、問題なく終わってしまう。
そして、上司は楽ができる。ビジョンを語っていれば良いからだ。
実際、そう言う人ばかりで固められた会社もまあ、無くはない。
だが、相手が普通のレベルの人なら、逐一指示が必要だし、仕事がスタックしていないかどうか、見張る必要がある。
*
行動経済学者のチップ・ハースは、著書の中で次のように述べている。
多くのリーダーが、おおまかな方向性を定めて満足している。「私はビジョンは定めるが、詳細には立ち入らない」。
確かに、次の章でも説明するように、魅力的なビジョンは重要だ。しかし、それだけでは十分とはいえない。
おおまかで放任的なリーダーシップは、変化の場面ではうまくいかない。
変化のもっともむずかしい部分、つまり麻痺を引き起こす部分は、まさに詳細のなかにあるからだ。
そう、彼の部下はまさに「麻痺」していた。
曖昧な指示、大きな指示を出されると、普通の人は動けなくなる。
それは時に「自主性がない」「抵抗している」とみなされるが、実はその人は戸惑っているだけであり、細かい指示を必要としているだけだ。
チップ・ハースはこんな事例を引き合いに出している。
ウェストバージニア州の研究者たちは、住民に「健康的な食生活をおくる」という目標を達成してもらうために何が必要なのかを考えていた。
「健康的な食生活をおくってください!」と叫ぶだけでは、誰も動かないからだ。
そこで研究者たちはターゲットを絞り、住民たちに向けて「低脂肪乳を買おう」というキャンペーンを打った。
アメリカ農務省の推奨する飽和脂肪の摂取基準を、日常生活の普通の牛乳から置き換えるだけで満たすことができるからだ。
このわかりやすく、メッセージ性の高いキャンペーンは当たり、住民の多くに「健康的な食生活」を提供することができた。
これを受けてチップ・ハースは
「壮大な目標よりも、日常の行動から指示せよ」
「行動するためには、あいまいさは敵である」
という。
必要だったのは、壮大な目標を日常的な行動のレベルに落としこみ、健康的な食生活を送る数多くの複雑な選択肢を仕分け、手軽な開始点を提案してくれる人だったのだ。
あいまいさはその敵だ。変化を成功させるには、あいまいな目標を具体的な行動に置きかえることが必要だ。簡単に言えば、変化を起こすには、「大事な一歩の台本を書く」ことが必要なのだ。
そう言う意味で、部下が特に優秀でもないのに、「マイクロマネジメントは嫌だ」と、大まかな指示だけをして、ビジョンばかり語る
「ビジョナリー・上司」は迷惑な存在だ。
*
結局のところ、「部下の自主性」を上司が期待するのは的外れだ。
多くの場合「仕事が滞る」のは自主性ではなく、能力に起因する問題だし、「自主性」という曖昧な概念は上司の主観に依存するので、「お前は自主性がない」など言われても、部下は戸惑うだけだ。
だから、自走する部下がほしい、なんて言わないでほしい。
仮にいたとしても、自走する部下は、その人の元からすぐに去るだろう。
なぜなら、上司を必要としてないからだ。
部下はほぼ100%、「細かい指示を必要としている」と、まずは割り切ること。
そのあと、仕事がうまくいくようなら、手を離しても大丈夫だ。
最初から細かい指示を必要とせず、勝手に仕事を遂行してくれる人については、
「指示していないことまでやってくれるのは儲けもの。彼は早く管理職になるべき」
くらいに考えておくのが、丁度いい。
◯Twitterアカウント
ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>
第6回 地方創生×事業再生
再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】
ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。
当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。
【今回のトーク概要】
- 0. オープニング(5分)
自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)
保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)
再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)
経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)
「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)
数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)
経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”
【ゲスト】
鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏
ExePro Partner代表 経営コンサルタント
兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。
高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。
卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。
株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。
その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。
現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。
【パーソナリティ】
倉増 京平(くらまし きょうへい)
ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事
顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。
コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。
ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。
(2025/7/14更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント
◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。
Photo by Amy Hirschi on Unsplash













