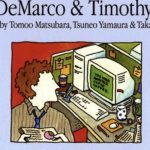世界中で「コスト圧縮」の流れ
コロナウイルス禍で経済活動がストップし、イベントの主催者が、世界中で「コスト圧縮」をしている。
まず「オリンピック」そして「F1」
延期の東京五輪・パラ 大会サービス厳しく見直しコスト削減へ(NHK)
F1、さらなるコスト削減のために予算上限の低減やPU開発制限を検討か(motorsport.com)
「シルク・ド・ソレイユ」は一時解雇(レイオフ)に踏み切り、話題となった。
もちろん、企業活動も同様だ。
「航空会社」「アパレル」「金融」「製造」いずれの業種にもコスト圧縮の動きがある。
ルフトハンザ、40機超を削減 コロナで需要低迷長期化(日本経済新聞)
アパレルブランドの悪循環の始まり? GAP、夏物と秋物の注文をキャンセル(Business insider)
アメックス、費用30億ドル削減目指す-新型コロナでカード利用額急減(Bloomberg)
日産1万人レイオフ コロナ禍でゴーン路線が重荷に(日本経済新聞)
もちろん、生き延びるための、必死のコスト削減もあるだろう。
関係者各位の努力には頭が下がる。
ただ、これらをすべて、ネガティブに捉える必要はない。
実際、こうした時期は景気が良い時に「高コスト状態」となってしまった企業体質を改めるのに、とても良い機会であることも多い。
例えばこの機会に「オフィスの解約」などを進めている企業を見かけるが、他にも「交際費」「会議費」「旅費交通費」「販促費」といった、社員への影響が小さい、減らしやすい部分への介入は
「なんとなく緩んでいた財布の紐」
をしっかり締め直す良いきっかけとなる。
「乾いた雑巾を絞るように」はトヨタのコスト意識の凄まじさを表す言葉だが、トヨタに至ってはこの時期においても、黒字を確保している。
【決算ウォッチ】「さすが」トヨタの決算発表だが…… コロナショックからの回生シナリオは思惑どおりに進むのか?
販売台数の減少により、営業利益が1兆5000億円減少すると予想しているが、記者会見で豊田社長は「リーマン時と比べて販売台数の減少は激しいが、企業体質を強化したことで黒字を確保できる」と述べている。
だがこのような時期にはもっと思い切ってやる事ができる。
例えば、費用の本丸である「人件費」だ。
だが、将来への投資である製品開発部門を止めたくはない。また、新しく仕事を取るための営業部門も同様だ。
要するに、「直接、収益に関わる部門」のコストにはできるだけ手を付けたくない。
不況時であっても、未来の仕事のために手を止めるわけには行かないからだ。
とすれば。
コスト圧縮の対象として、最後に残るのは「間接部門」。
つまり総務・経理・人事などのコストとなる。
この状況は「間接部門のコスト圧縮」を進める、またとないチャンス
「普段から間接部門のコストは抑制しているよ」という会社もある。
だが実は「間接部門」のコストに、本当に思い切って手を付けている会社は少ない。なぜか。
最も大きな理由は「リスク管理」の観点だろう。
間接部門には利益を生み出さないとはいえ、法律上の対応が絶対であり、ミスが許されない業務が数多く存在している。
また、経営の意思決定に重要なデータを作る部門であり、安易に削減すると長期的に痛い目にあう。
特にお金を扱う経理部門は安易なコスト削減が、不正や申告漏れなどに通じる部分もあり「リスクがあるから手を付けたくない」と、経営者が尻込みする領域でもある。
だから通常「間接部門のコスト圧縮に取り組みたい」との意識はあっても、本格的に手を付けることはむしろ少ない。
せいぜい「正社員をできる限り少なくする」くらいだろう。
ところがこの「コロナウイルス禍」下ではそんな悠長なことを言ってはいられない。
金融機関からカネを借りるにも、株主にも「コストを絞りましたよ」という何かしらの行動が必要だ。
つまり抜本的な見直しが必要とされている。
ただし、「ピンチはチャンス」でもある。
つまり裏を返せば、コロナウイルス禍は、今まで手を付けにくかった「間接部門のコスト圧縮」を積極的にすすめる、またとないチャンスだ。
リモート化、オンライン化で経理コストは半分に
これらの「経理部門のコスト圧縮」ニーズに対して、サービスを提供している企業の一つが、以前にも紹介した
「リモートワーク」
「アウトソーシング」
をキーワードとしたサービスを幅広く提供している、株式会社キャスターだ。
参考:
この状況下において「経理業務のアウトソーシング」についても、利用企業が急増している。
経理アウトソーシングサービスを手掛ける
「キャスタービズアカウンティング」の宮川さんは、「多くの会社が、経理にかけるコストを大きく削減できる」とする。
そこで、「どの程度コストを減らせるか」との目安を聞いた。
宮川さんによれば、
・50名から100名規模、2〜3部門あるような会社
の場合、経理部門の構成は、概ね
・経理の責任者1名
・正社員1名
・派遣社員を2〜3名
程度の構成が多いという。これは、派遣社員のコストだけで月に約70〜80万円かかる計算だ。
この状態から、抜本的に経理業務の
「リモート化」「オンライン化」
を進めれば、派遣社員をゼロにしたうえで「アウトソース費用」も含め、ランニングコストを月に25万円〜45万円程度に抑制することができる。
これは、年間トータルで500万円程度のコスト抑制になる計算だ。
リモート化、オンライン化は「属人化」「採用難」への対処も可能
また、リモート化・オンライン化は、「コスト圧縮」というメリットだけにとどまらない。
「経理の属人化」と「高スキル人材の採用難」への対処も可能だ。
例えば、ある観光・宿泊業の会社は、
・経理知識の深いメンバーが部長1人のみ
・知識がないメンバーはマニュアル通りの作業を行うが、例外事項も多く、ミスや漏れが多発
という状態に悩んでいた。
ここには、大きな課題が2つある。
一つは、部長しか経理の内容を知らないという大きなリスク。内部統制上の懸念だ。
そしてもう一つは、経理の実務経験を持つ人を採用しにくいというリスクだ。
そのためキャスター社は「業務の整理」を行うことを提案した。
具体的には以下のようなリモート化、オンライン化による、業務の標準化だ。
・クラウド会計・給与計算システムの利用
・販売管理システムの利用
・請求書発行システムの利用
・支払請求書受取の電子化
・経費精算システムの利用
・小口現金の廃止(経費精算へ統合)
最終的には、上述した観光・宿泊業の会社は
部長+正社員+派遣社員
の3人体制から、
部長+正社員+キャスター
という体制に移行し、経理のランニングコストを、月額にして50万円ほど削減するだけでなく、退職リスク、内部統制上の懸念を払拭した。
「経理社員のキャリア」もアウトソース化で改善される
ただ、このような話をすると「経理部門の社員の雇用はどうなる」という懸念を抱く方もいるだろう。
経理社員の雇用を守るのも、企業の役割ではないか、という話だ。
ただ、雇用云々の前に、現実的には「経理の正社員」は、クラウド会計ソフトの発達に伴い、ますます少ない人数で十分で回すことができるようになった。
そもそも、今後必要となる人員は、減りこそすれ、増えることはない。
そして、さらなる事実として「特定の1社で、ずっと経理として働く」というキャリアは、本人にとっても、かなりリスクのある選択だ。
ルーティンワークがどんどん減り、経理の仕事は高度になるばかりの状況で「うちの会社に特化したスキル」しかつかないのでは、どんどんスキルが陳腐化してしまう。
もしその会社が倒産したら?
もしその会社が合併・吸収されたら?
もし業績悪化で会社を縮小せざるを得なくなったら?
陳腐化したスキルしか持たない「経理部員」に、もはや行く場所はない。
そうなると、高度な経理スキルを持つ人物は、「経理業務のアウトソースを受ける」ほうが、遥かに合理的な選択ではないか、という仮説を私は持っている。
アウトソースを受ける側であれば、様々な会社の経理に携わることが出来る。
そして、様々な会社の経理業務の改善に携わり、業務設計を行い、最新のツールに精通する。
それは「汎用的なスキル」であり、貴重な人材となれる。
実際、キャスターアカウンティングのサービスを行っているメンバーは、全員、経理出身だという。
そう言う意味で「経理のアウトソース」は、出す側も受ける側もメリットがあるのではないか、と考えている。
>キャスタービズアカウンティングに話を聞いてみる
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)
◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。