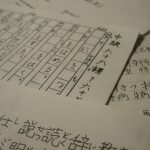最近は出番がなくなってきたけれども、一時期、子どもの読書感想文や日記について相談を持ち掛けられる……というより困っているのを見つけて助け舟を出しがちな状況があった。
ありがちパターンはこうだ:週末、「宿題は終わった?」と訊ねたら「だいたいやってある」と子どもが答える。うんうん、感心感心。ところが日曜日の午後8時ぐらいに「日記がまだ書いてない」という言葉が聞こえてくる。さあどうしよう。日記のネタを探すところからやらないと……といった具合だ。
読書感想文の場合は、週末の初め頃に何を読むべきか悩んでいたり、「読んだはいいけど何を書けばいいのか困っている」と子どもから耳にすることが多い。
私の子どもは21世紀生まれなので、一定程度は本を読むにせよ、私自身の幼児期に比べれば本を読んでおらず、そのぶんオンライン上のドキュメントを読んでいたり動画を見ていたりする。
それは別に悪いことではないが、本の読解力や自分の考えや体験を言語化する能力はこれからも必要だ。だから学校が日記や読書を宿題として出してくれることには感謝している。
「じゃあ最初に、週末に起こったことを思い出してみよう。お昼に何を食べたか、午前中に何を見たのか、そんなことでいいから。動画の内容でもいいし。」
子どもが日記に困っている時には、まず週末に何をしたのか、どんな週末だったのかについて話し合う。
日記のネタがないと言っても、振り返ってみれば案外あるものだ。
昼ごはんに出たチャーハンが近くの中華屋さんのテイクアウトだったが、それがいつもと盛り付けが違ったとか、午前中にPCの回線がつながらなくなってルーターやらなにやら切断して二十分後に再開通しただとか、テレビをつけていたらカゲロウの一生をやっていて、それを何気なく見ていたとか、案外、日記の素材になりそうな出来事は転がっている。
「でも、そんなこと書いてもたいしたことじゃないし」
「そうはいうけど、日記って特別なことしか書いちゃいけないってわけでもないんじゃないの?」
子どもはしばしば、「日記を書くにはそれに値するイベントがなければならない」と思いこみがちだった。
たとえば日記を書くためにお菓子をつくるだとか、日記を書くためにどこかに出かけるだとか。
もちろんイベントを日記に書くのはまっとうなことだし、ときには日記のために出かけるのもいいだろう。でも「日記」というぐらいだから、日常のなかで感じたいろいろなこと、思ったことを書いたっていいものじゃなかっただろうか。
「ほら、チャーハンのこともPCの回線が繋がらなかったこともカゲロウの一生の番組も覚えているんだから、そのときにやったことや思ったことを書けば立派な日記になるんじゃない?」
そこから一緒に、チャーハンについて、PCの回線について、カゲロウの一生の番組について、ああだったねこうだったねと会話をする。
会話をしてみると、確かにそれらが今日の出来事だったという気持ちになってくるし、そのときの気持ちも蘇ってくる。こうなったら日記は書いたも同然だ。15分後には、子どもはそれらしい日記を書きあげている。
出来事そのものに、自分の気持ちを添えればまあまあの日記(や感想文)になる
世の中には、大人になっても日記や読書感想文のたぐいが苦手だという人が多いと聞く。我が家の子どもも、前述のように日記や読書感想文に苦戦している時期があった。
ところで私は、日記や読書感想文が得意である。
実際、自分のブログは17年以上続いているし、ワインの感想を書いたブログの記事数も2400をこえている。だから世間一般の人より日記や感想文が得意な性質だと思って構わないだろう。
その私からみると、毎日の生活には日記や感想文を書く材料が無限にあふれている。
もちろん、完全に家にひきこもっていて誰とも交流をしていないなら、材料の入手先は限られ、経験の絶対量が減ってしまって難しいだろうなと思う。
でも、学校や会社に通い、それなり人とコミュニケーションしている人の日常には、日記や感想文の材料が毎日のように供給されている。
日記を書きたくても書けない人は、まず、一日なり一週間なりを振り返って二つ三つの出来事を思い出してみることをオススメする。よく思い出してみれば、だいたい何かが起こっているはずだ。
それは通勤中に変なものを見かけたことだったり、いつもの昼食にいつもでない要素が闖入したことだったり、なんだか気持ちがクシャクシャするような仕事をやってしまったことだったりする。
職場の窓の外の風景がいつもと違っていて、たとえば雨あがりに虹が出たりして、それをきれいだと思ったことなどは日記にしやすい立派な出来事だ。
学校に提出する日記でないなら、オンラインで見聞きしたことでも構わない。自分の琴線に触れる文章を読んだ、ソーシャルゲームのイベントでスタートダッシュできた、対戦ゲームで勝った負けた、そういったものでも良いだろう。
思い出しやすい出来事は、自分なりに感じたこと・思ったことが伴いがちだから、思い出した出来事を書き、そのときの自分の感想や感情、考えたことを書き添えれば、だいたい立派な日記になる。
読書感想文の場合も、この日記作成法に近いことをやればだいたい書ける。
迷ったときは、感想文の前半にその本の要約を書き、後半にその要約を書く際に自分が何を感じたのかや何を知ったのかを少し書き足せばいい。
「読書をとおして何を知ったのか」を書くがワンパターンだと感じたら、「今まで何を知らなかったのか」を書いたり、「読んでいる最中の自分自身の感情の動き」に重きを置いて書いてみるのもいい。
だから読書感想文のメインは内容の要約と個人的な印象や感想の二本柱ということになる。
内容や書く媒体、気分などによって、その二本柱のウエイトは変わり得るが、どちらか一方だけでは読書感想文としてバランスがとりにくい。
別の言い方をするなら、読書感想文には客観的な内容と主観的な受け取り方の両方を書いておけばおおよその体裁は整う、とも言える。
読書に限らず感想文的なものを書きあぐねている時には、「要約」→「思ったこと」の順に書いてみればだいたい何とかなる。
読書感想文や日記はリテラシーを育てる
こうして日記や読書感想文の書き方についてまとめてみると、なるほど、学校でこれらを宿題や課題にするのは理にかなっている。
さきに挙げたように、読書感想文の主柱は内容の要約と個人的な印象や感想の二本柱だ。
しかし、まさにこの二本柱は国語の精髄というか、国語能力のきわめて重要な部分を占めていると思えないだろうか。
読んだ本や文章の内容を要約するのは、文章の理解力に直結する課題だし、学校のテストでも、実質的にはこの要約をさせている設問がドシドシ出題される。
そういう意味で、小さい頃から読書感想文を書き、それをとおして要約力を鍛えるのはリテラシー(読み書き能力)を向上させるストレートな方法だと思う。
この能力は、会話をとおしても強化できる。「今日読んだ本には何が書いてあった?」「今日の『ぼっち・ざ・ろっく』はどんな話だった?」 子どもにそういう質問を日常的にしていると、子どもは読んだ本や見たアニメについてさまざまなことを語ってくれる。
その語りから子どもの見たものを想像し、関心を示し、ときにはこちらからさらに質問をしたりすると、子どもはもっともっとそういうことを話してくれるようになる。
作文用紙に書かなくても、これは、頭のなかで見聞したものを要約し言語化するトレーニングになるんじゃないだろうか。親子の会話のネタとしてもバッチリだから一石二鳥である。
だから本に限らず、子どもが見聞きした色々な面白いもの・難しいものに関心を示し、それを親が喜んで聞いていると、子どもの要約力が勝手に鍛えられ、おそらく、読書感想文をつくる能力も国語力も潜在的に鍛えられるんじゃないだろうか。
個人的な印象や感想を語ることもすごく大事だと思う。
自分の思いのたけを言語化することは、他人に自分の思いを伝えるうえでも、ストレスに対処するうえでも、プレゼンテーションを行ううえでも必須だ。自分の内面を耕すうえでも有用かもしれない。
日記や読書感想文は、そうした自分の思いのたけを言語化するトレーニングとしては王道だ。
それらを書かなれば通り過ぎてしまった感動を振り返り、心のうちの小さなさざめきを短文に転写することで、言語化能力は高まっていく。
もちろんこれも、会話をとおして強化できることだ。どう思ったのか・どう感じたのか・すごかったのか・たいしたことがなかったのか、そういったことを日常的に親子で会話していると、子どもの言語化能力が自動的に高くなっていくと私は想定し、私の家ではそうしてきた。
会話のなかの読書感想文や日記なら、文章ばっている必要は何もない。
子どもとの会話の場合は特にそうだろう。「『スプラトゥーン3』のXマッチで今日はこてんぱんにやられた。海女美術大学は苦手だ」「相手のリッター4kが百発百中で試合にならなかった。でも自分の仕事はできたと思う」これぐらいでも十分だ。
自分が何を経験したのかを言語化できること、自分がそのとき何を思ったのかを言語化できること、そのひとつひとつの積み重ねがリテラシーを養っていくとしたら、アニメやゲームについてのやりとりも、学校の宿題や図書館から借りてきた本についてのやりとりも、等しく貴重で、ためになるものに違いない。
日記や読書感想文に「面白い」スパイスを載せるには
以上が、読書感想文や日記が書けるようになるための私家版トレーニング方法だ。
これらに沿ってやっていれば、学年が進むにつれて日記や読書感想文が書けるようになる。あるいは日記を書きたくない日でも日記を「でっちあげる」ことが可能になってくる。
書きたくない日にでっちあげるのも案外バカにならない能力だ。社会人になれば、砂をかむような報告書や日報を書かざるを得ないこともままあるからだ。
さて、とりあえず読書感想文や日記が書けるようになった向こう側には、面白い読書感想文や日記を書くこと、人を惹きつける文章を書くこと、といった課題が存在している。
この課題については、前述のトレーニング方法だけではたぶん足りない。前述のトレーニングは基礎づくり的なものであって、面白味や魅力を保証してはくれない。
面白味や魅力のうち、ある一面は、それでもトレーニングによって何とかなるかもしれない。
というのも、要約しづらいものまで要約できること、それ自体も文章の魅力の一端となるからだ。文章の内容を要約するトレーニングがきわまってくると、解説系のブログの文章として魅力的なものができあがってくると思う。
他方、その書き手自身の魅力や個性となると、はてさて、どうすれば魅力的になるのか……。
連載を持っている凄腕エッセイストなどがそうだが、何を書いても映える人、面白く書ける人というのも存在する。凡人が読んでもたいして面白くもない本が、その人が読書感想文を書くと面白そうにみえる。日常の景色をその人が切り取るとやけに印象的にみえる。そういう反則のような書き手だ。
おそらく、そのような書き手には世界がそのように面白く見えているのだろうし、箸が転がっても面白がることができるのだろう。
到底、誰でもなれるものとは思えない。凄腕エッセイストの魅力や個性はきわめて属人的で、再現は不可能だ。
しかしもし、そうした書き手に追い付く道があるとするなら、やはり、感想文や日記を書いていくほかないのかなとも思う。
どんなことにも目を向け言語化し、人に伝える営みを繰り返していけば、人に伝えるということ、それ自体には習熟していける。
面白さを発見する目も養えるのかもしれない。それらは才能の開拓ではなく、しょせん、元からあった才能の研磨でしかないのかもしれないが、やらないよりはいいだろう。
とはいえ、感想文や日記が特別に面白くないからといって困ることもあるまい。
一般的なコミュニケーションや仕事に必要な程度のリテラシーは、読書感想文や日記をとおして十分に強化できるように思う。
その習得過程を助けるのは、学校の宿題や塾の授業だけでなく、家庭での親子のコミュニケーションでもあると私は思うので、子どもとそういう会話をいっぱいしてみませんか、というのがこの文章の一番言いたかったことになります。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。
twitter:@twit_shirokuma
ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo by Yumi Momoi