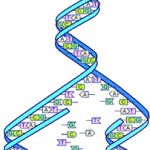マクドナルドがヤバイ、ということが日経新聞で報じられている。
マクドナルドがヤバイ、ということが日経新聞で報じられている。
”中国上海市の仕入れ先が使用期限切れの鶏肉を使用していた事件が起きて、日本マクドナルドホールディングスの店頭から顧客が目に見えて減っていった。既存店売上高は急落し、業績の予想すらできない窮状に陥っている。その客足が遠のいた店舗を歩くと、「迷走する経営」があぶり出されてくる。”(日本経済新聞)
既存店舗の同年前月比の売上はマイナス20%(!)近く。大きなマイナスだ。
報道では、中国の期限切れ鶏肉と業績不振との関連性を強調しているが、実際にはこれはきっかけにすぎないようだ。実際には、マクドナルドの不振は世界中で同時進行している。
”米ファストフード大手マクドナルドにとってこの10年で最悪のスランプにある背景には、今後さらに厳しい時期が続くことを暗示するトレンドがある。それは若年層にとって金色のアーチ(マクドナルドのシンボル)が輝きを失っているという現実だ。”(ウォール・ストリート・ジャーナル)
子供の頃、マクドナルドに連れて行ってもらうのはちょっとした楽しみだった。普段家庭では絶対無いような味と雰囲気、確かにあれはひとつのエンターテインメントだった。
しかし、確かに最近マクドナルドには殆ど行かない。私の友人たちも、「行かなくなった」としている。そして、それはどうやら世界中で同じようだ。
”マクドナルドの試練の背景には主要な顧客年齢層の変化もある。
レストランコンサルティング会社テクノミックがウォール・ストリート・ジャーナル向けにまとめたデータは、マクドナルドの顧客年齢の問題を指摘している。
長年同社事業の主要な支持層だった 20〜30代の顧客は競合他社にくら替えしており、特にメキシコ料理チェーンのチポトレ・メキシカン・グリルやグルメバーガーチェーンのファイブ・ガイズ・ホールディングスなど、「ファストカジュアル」と呼ばれる業態のレストランの人気が高まっている。
若年層は、より新鮮で健康的な食品を求め、ファストフードのセットメニューとあまり変わらない価格でカスタマイズ可能なメニューを提供するレストランを求めている。
最近デューク大学を卒業したニュージャージー州ホーボーケンのアレック・ピーターセンさん(21)は、マクドナルドに行くことはもうほとんどなくなったと話す。
「マクドナルドに懐かしい思い出はあるが、チポトレの方が断然食べ物の質が高い。あるいは、少なくともそう感じる」と述べた。”(ウォール・ストリート・ジャーナル)
多分、21歳の彼が言っていることは的を射ている。
20年前「マクドナルド」はたしかに特別だったが、今のマクドナルドはありふれている、高い、そして、美味しくない食事と思われている。
”米国の有力消費者情報誌「コンシューマー・リポート」の最新調査で、米国の大手ハンバーガーチェーン全体の中でマクドナルドのハンバーガーが一番まずいという結果が示された。この調査結果は同誌の定期購読者のうち3万2405人の回答と、ファストフード・チェーンなど65カ所での9万6200回以上の食事経験に基づいている。”(ウォール・ストリート・ジャーナル)
外食産業は、本質的には「味」が良くなければ誰も来ない。だから、マクドナルドは「味」を改善しなければ、業績の回復は見込めないだろう。
しかし、マクドナルドは厨房をあまりにも特定の作業に特化してしまったゆえに、他の味を作り出すことが難しくなってしまっている。
”バンズ(パン)やパティ(肉)、野菜、ソースなどを「基本アイテム」として、この組み合わせで複数の商品を作り上げている。
だが、高級バーガーとして食材が増えると、極限まで効率化された厨房に混乱を来す。昨年7月、1日限定の1000円バーガーを販売して話題を集めたが、「20分で売り切れる商品のために、練習をするわけにもいかない。ベテラン店員まで、新人のように戸惑ってしまった」(兵庫県の店舗オーナー)。結局、生産工程を大きく変更しなくても提供できる商品で勝負するしかない。スピード重視の価格訴求型商品となるが、そのカテゴリーには牛丼や回転ずし、コーヒーチェーン、コンビニエンスストアなど、効率化を追求した精鋭たちが揃っている。少しでも隙を見せれば、客を奪われてしまう。”
「特殊化の果てにあるのは緩やかな死」というのは、今のマクドナルドに当てはまるのかもしれない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (スパムアカウント以外であれば、どなたでも友達承認いたします)