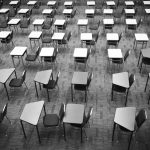テレワーク体制での新人教育で苦労している話をします。
3月からこっち、コロナ禍で仕事をする体制になって半年以上が経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
運動不足になってないですか?
私はリングフィットアドベンチャーを購入出来たんですが、負荷を重くし過ぎて正直あんまり継続出来てないです。
緊急事態宣言が解除されてしばらく経ちましたが、未だコロナが収束したとはとても言えない状況です。
会社によって体制も様々なら企業人の皆様のスタンスも様々でしょうが、可能な限り対人の接触を減らさなくてはいけない状況が続いている、という点については衆目の一致するところではないでしょうか。
で、今しんざきが働いている会社でも、大筋テレワークが基本となる体制が続いておりまして、やむを得ず出社せざるを得ないタイミングもあるとはいえ、基本的にはリモート勤務主体でお仕事をしております。
で、リモート勤務体制でも、大体のタスクはコロナ以前の頃とそれほどパフォーマンスを変えずに処理できるようになったんですが。
一つだけ、以前に比べて格段にやりにくくなったなー、しかも正直まだ解決までの道筋が明確には見えてないな、と思っていることがありまして、それが何かって
「新人研修」
「新人教育」
なんですよ。
***
しんざきはそこそこ新人の皆さんと接触する機会が多い方でして、研修や勉強会を主催することもそれなりの頻度であります。
で、これは以前もどこかで書いた記憶があるんですが、新人に限らず誰かに何かを教える時、一番重要なことは何かっていうと
相手の「分からない」をどうやって拾い上げるか
ということなんですよね。
これは一般的な話でして、学習塾だろうが家庭教師だろうが、新人研修だろうが勉強会だろうが変わりません。
断言しますが、「何か分からないところはありますか?」とか「何か質問ある人」という言葉は、少なくとも教える側の心構えとしては、何の役にも立たないと考えておくべきです。
「なんか質問ある?」と聞いて「しーーーーん」となるのは、それはプレゼンターにとって一つの敗北です。
基本、「知らないことを学ぶ」際には、「何が分からないのか分からない」というのがデフォルトです。
ただでさえもやもやとしている「分からない」ことを明確にして、しかもそれを「質問」というきちんと相手に伝えられる形式で言語化するというのは、その時点でかなりのスキルが必要なことです。
もちろんそういうスキルを持っている人も中にはいますが、教える側が新人にそれを期待してはいけない。
それに加えて、「分からないことを聞く」ということは、ある程度慣れていないと大変に心理的障壁が高いものです。
世の中、「先生、しつもーん」と気軽に手をあげられる生徒ばかりではない。
「こんなこと聞いてあきれられないかな…」
「なんもわかんないって言って評価下げられないかな…」
というハードルは、誰にとっても大きいものです。
これについては、以前も類似のことを書きました。以下の記事、気が向いたら読んでみてください。
質問が出ないのは話し手の責任が8割。だから「質問が出る」ようにルールを決めたら、大成功した話。
だから、「質問」のハードルを下げることはまず前提条件として。それはそれとして、「分からない」は、基本的には「教える側」からとりにいかないといけない。相手任せにしてはいけない。
相手の分からない度合いによって、どれだけ教え方を調整出来るかが教える側の腕の見せどころだと、私はそう考えています。
ところがですね。
実際やってみて分かったんですが、リモートでこれやるの、めっっっちゃくちゃ難しいんですよ。
今まで使ってた手法が殆ど通用しないんです。マジで苦労しました。
なんだかんだ、直接顔を合わせて教えていると、「相手の理解度」って結構見て分かるものです。
今、手を動かしてメモっている内容はなんだろう?
後で質問する為に、曖昧なところを書き留めているのかな?
それともポイントを絞って記憶しているのかな?
よくわからないから取り敢えず手を動かしているだけかな?
あ、今はちゃんと聞いてるな。
今はちょっと目が泳いでるな。
一応視線は合ってるけど今は聴いてないな。
頭に入ってないな。
face to faceだと、そういったリアルタイムの「見た目」で分かる情報ってめちゃ多いです。
それで、「あ、今この辺はあんまり理解が進んでないっぽいな」というのが大体分かる。
もちろんこちらから雑談まじりの質問を投げることも気軽にできますし、実際に手を動かしてもらって、引っかかっているところ、手が止まるところを実地で確認することも出来ます。
相手の「質問」に頼らなくても、理解度のチェックが比較的容易なんです。
で、「今あんまり理解が進んでないな」と分かれば、説明の速度をゆっくりにすることも出来るし、説明を手厚くすることも、なんなら気分転換に雑談を挟んで集中力を回復してもらうことも出来る。
ところが、リモートの研修だとそれがすげーーーー難しい。
顔は見えるっちゃ見えるんですが、画面共有しながらだとちっちゃくしか見えないですし。
目つきを判別するのも相当難しい。
手元なんか何も見えない。
質問を投げることは出来るには出来るんですが、「実際に手を動かしてもらう」のはかなり難しい。
相手の手元にしかデスクトップはないですから、ちょこちょこ動きながら手元を確認する、なんてことも出来ないです。
どこかで引っかかるにしても、それをいちいち言葉でやり取りしないといけなくって、その間他の人との情報交換が止まってしまう。
これどうにかしないとしんどいなーと思ったんですよ。
この数か月試行錯誤してたんです。
もちろん、「リモートならではの強み」というのも一応ありまして、試行錯誤の結果何点かはデフォルト実施にしました。
・自分が話した内容を動画アーカイブ化しておいて、いつでも見返せるようにする
・非リアルタイム、かつ一対一の質問チャンネルを別に設けておいて、「後からでいいし、どんなしょうもない内容でもいいから」としつこく言って心理ハードルを下げる
・その上で、来た質問の内容は匿名にしてFAQ的に共有する
この辺は工夫してみました。
特に、動画アーカイブについては唯一「対面での新人研修」に勝っている部分だなーと思っていまして、「いつでも見返せる」っていうのは割と大きい。
まあ別に対面でもアーカイブ化は出来ないことではないんですが、私対面だと結構動きまわる方なんで動画化難しかったんですよ。
また、「一対一のチャンネルを別に設ける」というのも多分大事で、少なくとも「みんながいる前で「分からない」と発言する」ということはそれで避けられる。
いやこれ、「いい大人が、質問するの恥ずかしいとか…」って思うかも知れないですけど、質問慣れしてない人にとっては「人目があるところで自分の不理解を開示する」ってマジ心理ハードル高いですからね?
「人目がないチャンネルがある」ってめちゃ重要なんですよ。
かつ、対面と違って「一対一の質問が、研修中にその場で出来る」ってのも大きいですね。
で、上記のような工夫はそれなりの成果を出していると思ってはいるんですが、やっぱりどうしても「分からない」を拾い切るには至っておりませんで、
「「分からない」の言語化が得意かどうかで、学ぶ側の習熟度に大きな差が出来てしまっている」
ということは今のところ避けられてないな、と自己評価せざるを得ません。
つまり、上の方で書いた「何が分からないのか」をある程度言語化出来るのか、どうか。
その言語化した内容を講師に投げることが出来るのか、どうか。
少なくとも、「分からない」を曖昧にでも発信できれば、それを端緒に解決に持っていくことは出来るんですが、それも出来ないと正直かなり厳しい。
教える側が「分からない」を拾いにくくなった分、「分からない」を言語化する能力の重要性がより一層増してしまった、という話なんです。
実際、これは教える側として忸怩たる思いがあるのですが、新入社員が入ってから半年ばかり経って「出来ること」の幅は明らかに「言語化が得意かどうか」でレベル差が出来てしまっている気がします。
普段ならある程度底上げが出来るんですが、その底上げがカバーし切れていない為に、「言語化」の有無が直接響いてしまっているんですよ。
現状、この「リモート主体の業務体制」というのは終わりが見えていません。
正直また対面主体に戻すことが出来るのか自体怪しいと言わざるを得ず、むしろ恒久的にリモート主体でお仕事をするのがスタンダードになっていきそうな雰囲気もあります。
つまり、リモート環境で、教える側が相手の「分からない」を拾い上げにくい環境は、今後も長期間継続する可能性がある。
もちろん、教える側として、リモート環境でも相手の「分からない」を拾い上げる方法については、今後も試行錯誤をするつもりではあります。
上手くいけば、もっといい方法を思いついて実施出来るかも知れません。
とはいえ、時間は有限ですし、教えてさえいれば他の仕事は一切しないでいいというわけでもなく。
正直、完全な解決は現状難しいかも知れない、とも思っております。
となると、
・「分からない」を言語化する
・「分からない」を気軽に開示する
能力の重要性は、どんな分野だろうと、今後ますます高まっていく可能性が高いんじゃないかなあ、と。
そう考えざるを得ないわけです。
自分の子どもたちには、「聞くはそもそも恥じゃない」を合言葉に、可能な限り気軽に「分からない」を言語化出来るよう、今後も親として教育していこうと思うと共に、新入社員の方々にも、可能な限り「分からない」ということのハードルを下げていかなくてはなーと。
そう考えるばかりなのです。
今日書きたいことはそれくらいです。
ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>
第6回 地方創生×事業再生
再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】
ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。
当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。
【今回のトーク概要】
- 0. オープニング(5分)
自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)
保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)
再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)
経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)
「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)
数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)
経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”
【ゲスト】
鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏
ExePro Partner代表 経営コンサルタント
兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。
高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。
卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。
株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。
その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。
現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。
【パーソナリティ】
倉増 京平(くらまし きょうへい)
ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事
顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。
コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。
ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。
(2025/7/14更新)
【著者プロフィール】
著者名:しんざき
SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。
レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。
ブログ:不倒城