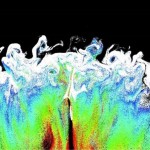先生という存在に初めて触れるのは、恐らく幼稚園から。早い人であれば幼児教室などに通っているから、3歳から4歳くらいから「先生」について学ぶ。
先生という存在に初めて触れるのは、恐らく幼稚園から。早い人であれば幼児教室などに通っているから、3歳から4歳くらいから「先生」について学ぶ。
それから小学校、中学校と進学し、高校には9割以上、大学にも6割以上の人が現在は進学しているところを見ると、「先生」には20年以上も教えられ続けるわけである。
ところで皆さんには「記憶に残る先生」はいるだろうか?
私はそれを聞いて回るのが好きなのだが、必ず誰にでも一人や二人、「自分の人生に影響を与えた先生」がいるはずだ。
個人的には小学校の時に通っていた塾の先生が私の記憶に一番残っている。小学5年生から2年間、塾通いをしていたのだが、6年生の時の塾におけるクラス担任がその先生だった。
その先生はとにかく熱心だった。生徒全員の様子をとても良く知り、とにかく生徒に成果を出させるため、猛烈に生徒に勉強をすることを求めた。
例えば、その先生は正規の塾の授業時間が終わった後、終わらせるべき範囲が終わっていない場合は全員を塾の物置のような部屋に移動させ、先生が独自に作った実力テストのような問題を全員に解かせる。
当然親も心配するだろうが、先生は親に電話し、「まだ終わっていないので、居残りでやります」と連絡する。
正規の塾の時間は夜8時位までであったが、先生のプリントをやっていると当然夜9時、ときにはもっと遅くまで勉強することになる。
当然腹がへるので皆は親の作ったお弁当を食べながら勉強する。時には先生がサンドイッチなどを買ってくれ、それをもらって食べるのだ。
だが、不思議とつらいことは1回もなかった。みなでお弁当を食べることも楽しかった。あのクラスには同じ目的に向かう仲間同士の一体感が確かに存在していた。
先生は、そう言った形で完全に塾の運営を逸脱した形での指導をしていた。
上司から指摘されないのか…と心配される方もいるかもしれないが、その先生は当時校舎長であったため、自由にやれたのだと思う。
またその先生は「武者修行しろ」といって、時々クラスの全員を他のレベルの高い教室に送り込んだ。
私達は少人数のクラスだったため、塾の本拠地のある大きな、最もハイレベルのクラスに送り込まれたのだが、あまりの雰囲気のちがいに私はとても驚いた。
私はいわゆる「井の中の蛙」というやつで、上には上がいて、勉強が出来る人はたくさんいることをそこで見せつけられたのである。
周りが全員天才に見える、緊張する、そう言った雰囲気を体感させ、きたるべき入試の雰囲気に備えさせたり、「戦いの現場」を体験させたかったのだと思う。
また、毎回の授業ではテストがあるのだが、先生がテストを採点して返してくれた答案には、とても厳しいことが書いてあった。
その先生は小学生に向かって赤ペンでこう書くのだ。
「お前は今の時点での実力では到底、目標校に入れない。のんびりしすぎている。繰り返し同じ問題で間違うことも多いから、なぜ間違えたのかを追求し、二度と同じミスをしないように最大限の努力をすること。あと入試まで6ヶ月しかない。遊んでいるヒマはない」
先生は我々を子供扱いしなかった。
子供ではなく、一人の人間として扱った。そしていかに目標達成させるか、ということについて真剣に考えさせた。
そして、先生はほとんど笑わなかった。常に真剣であった。とてもではないが、取っ付き易いタイプとは言えない人であった。
だが、皆その先生のもとで頑張った。
入試の日。私はほとんど緊張せず、のびのびと問題に取り組むことができた。多くの仲間が志望校に合格した。先生はとても喜んでくれた。
そして、しばらく経ち、先生にお礼をするため塾に行った。皆、先生がどんな顔をして迎えてくれるか、楽しみだった。
ところが、塾に言ってみると先生がいない。どうしたのかと聞いてみると
「先生は退職されました」
と聞かされた。皆に衝撃が走る。
「どこへ行ったのですか?」と聞いても、よくわからないという。
その後、風のうわさで先生の消息を聞くと、どうやら「職人になる」といって、会社を退職したとのこと。
私達は文字通り、最後の教え子となった。
その後、先生には会っていない。残念ながら、今もなお先生がどこにいるのかもわからない。
先生、お元気ですか。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします)
・【大学探訪記】を始めました。
「研究が楽しい」「研究成果を知ってほしい」「スタートアップを立ち上げた」
という学部生、大学院生、研究者、スタートアップの方は、ぜひ blogあっとtinect.jp までご連絡下さい。卒論、修論も歓迎です。ご希望があれば、当ブログでも紹介したいと思います。
【大学探訪記 Vol.10】池の水を少し汲めば、その池に住む生物がわかる。そんな魔法のような話、あるんでしょうか?
【大学探訪記 Vol.9】1年に13万件ある日経新聞の記事を、人工知能の一分野「機械学習」によって分類・分析する。
【大学探訪記 Vol.8】雲とチリの相互作用を、スーパーコンピュータで再現する。
・ブログが本になりました。
(Photo:Jonathan Leung)