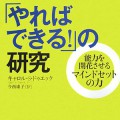目標管理制度(以下MBO)を導入している会社は多い。期首に目標を立て、期末に目標の達成度に基づいて成果を評価する、という人事制度の一つだ。日本の会社のおよそ8割が目標管理を導入している、非常にメジャーな制度である。
ただし、MBOをうまく使いこなせている会社は非常に少ない。データによれば、この制度に対して8割の会社が、問題を感じており、実際に制度の変更を検討している。
その中で比較的多く見受けられる問題は、「適切な目標をどうやって設定したら良いかわからない」という事だ。
目標管理制度は、「人は、目標を持つとそれに向かって頑張るはずだ」という考え方に基づいている。しかし、現実的には
- 人は「上から押し付けられた」目標を持たされても、それほど頑張らない。むしろ、殆どの人はやる気が下がる(評価のために統制されると、やる気が下がる)
- 目標に対して納得したとしても、全員に対して完全に公平な目標をつくるのは難しい
など、多くの欠陥を抱えながら運用されている。
さて、これらの問題を解決するために取られている手法が、目標設定の時、「やりたいことは何か」と上司が聞き、部下がそれに対して「XXがやりたいです」と回答し、折衷案をつくるやり方だ。
結論から言えば、このやり方は最悪に近い。
なぜか。まず普通の人は「やりたいこと」を聞かれても回答できない。前回も書いたが、これをやりたい、と明確に回答できる人は、普段からかなり仕事について深く考えている人だ。
2つ目に、仮に「やりたいこと」があったとしても、会社がその人に「やってほしいこと」とはめったに合わない。多くの場合仕事は既に割り当てが決まっており、会社が望んでいることとその人の希望は一致しない。
それなのに、目標設定の時だけ、「やりたいことは何か」と聞かれ、挙句の果てには「うちの会社ではそれは出来ないから、これをやってくれ」といわれるのである。まさに不毛な話し合いである。「だったら最初から「これをやってくれ」と、言ってくれよ」というのが、部下の本音だろう。実際、そのほうが良い。
この場合、どのような面談が望ましいのか。おすすめがある。目標設定の際に聞くことは「何がやりたいか」ではない。
「あなたの能力を生かして、会社にどのような貢献が出来ますか?」
と聞くほうが良い。会社への貢献を聞くのであれば、会社の業務から全く外れることは少ない。かつ、本人の意志と能力からどのような分野で貢献するのかを引き出すことができる。
もちろんこの質問は万能ではない。実際に聞いてみると単に「これだけの数字をやります」というように答える人から、「会社を明るくします」といったような定性的な回答をする人まで様々だ。しかし、「何がやりたいか」と聞くことに比べたら、はるかにマシな回答が返ってくる。
また、この方法は貢献の大きさを評価に結びつけるところに工夫が必要だ。しかし、本人の意志で「貢献の度合い」を決めることができるのであれば、評価の納得感も得られやすい。
かつて、ピーター・ドラッカーは「成果をあげるために貢献に焦点を合わせよ」と人々に説いた。基本はいつでも大事だ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。