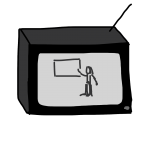電通の新入社員が超長時間労働により自殺。管理不届きという事で労災認定が下ったというニュースがここ数日話題だ。ニュースによるとこの電通の社員は残業時間が月に100時間を超えていたという。
筆者は一応医者である。そして研修医時代は日本有数のウルトラ激務病院に勤務していた。所属していた病院は残業時間という概念がなかったため、何時間残業していたのかを真面目に考えていなかったのだが、これを機に試算してみたら平均で200時間超であった。働き過ぎである。
こんなにムチャクチャに働いたにもかかわらず、自分の周りを見渡してみてもドロップアウトしている人は驚くほど少ない。
ひょっとして自分の経験がブラック企業勤務の社畜の皆様に役に立つ事があるかもしれないので、今日は長時間労働を生き抜けたコツのようなものを2つほど書いてみることにする。
超長時間労働を耐えきるコツ1。期限を決める。
現在の初期臨床研修制度はローテーション制である。内科3ヶ月、外科4ヶ月のように、1つの科にいる時間はあらかじめ決められている。
今でも覚えているのだが、筆者が初めに研修した科の上司はとんでもないパワハラ上司だった。まあこちらの物覚えが悪いというのもよくなかったとは思うのだけど、それはまあひどい言葉で詰られたものだ。そして詰められる度に僕はこう思ったものである
「どうせこいつと仕事するのも、長くても数ヶ月の事でしか無い」
月曜日が始まったら、あと6日働けば日曜日がやってくると思い、1週間が過ぎ去ったらあと3週間で1ヶ月目が終わると思った。こうして自分の中でカレンダーがさくさくめくられている感覚を積み上げる事により、どんなに嫌な事があろうが、終りがあると言い聞かせながら激しい就労期間を耐え抜いてきた。
一般企業で務めている人ははここまでわかりやすく勤務ローテーションが組まれる事は稀だろうけど、僕の使った考え方はあなたもきっと役立てられるはずだ。
「あと3ヶ月働いてみよう。3ヶ月後に、もう耐えられないと思ったら、無理せず辞めよう」こういう風にでも思いながら、働けばいい。日本は豊かだから、再チャレンジする事はそんなに難しい事ではない。
超長時間労働を耐えきるコツ2。厄介事に意義を見出す。
研修医のPHSはとにかく鳴り止まない。医者は下っ端と言えども指示出し役なので、多職種からの連絡がとにかく集中するのである。
あまりにもPHSが鳴り過ぎるので、結構な数の医者は電話が嫌いなはずだ(笑)実際、筆者もあまり好きな方ではない。そして結構な数の医者が、PHSをかけづらくする為にキツイ対応をしてしまうようになりがちである(よくない事ではあるのだが・・・)
ところで筆者の友人のうちの1人に、物凄く電話対応がいい奴がいた。
どんな酷い電話連絡だろうが、明るい声で対応する彼の元には、男女問わずコメディカルからの電話が物凄く集中していた。旗から見ていても恐ろしい電話量であり、よくもまあ明るく対応し続けられるものだと感心したのを覚えている。
さて彼はどうして明るく電話対応ができたのだろうか?その答えは1年後に飲み会の席で暴露される事となった。なんとコヤツ、明るい電話対応を繰り返していたのは下心があったからだという。
心地よい電話対応を通して親しみやすい雰囲気を形成する事で、目当てのナースに好印象を与え、夜間当直などで二人っきりになった瞬間を狙って電話番号を聞き出したのだそうだ(笑)
ただ彼の凄いのは、誰かれ構わず全員に気持ちいい対応をしていた事であり、電話上で人を全く差別していなかった所にある。
まあ下心の上になりたっていた優しさだとはいえ、その下心で病院みんなは気持ちよく仕事ができていいたのは事実であり、その姿勢からは学ぶものがある。
なお彼はご目当てのナースとその後、結婚した。なお結婚後も電話対応の評判はとても良いという事を付け加えおく。
このように、他人からの雑務の依頼という一見めんどうくさいものですら、人はポジティブなものにすり替える事が可能である。
その他に似たような話として、筆者が前に読んだ自己啓発本に、とある大企業の新人社員Aさんが地方出向先の工場で、3日間工場に寝泊まりして従業員の顔と名前を全て覚えたという話があった。
それまでは本社から地方の工場に出向される事は、出世ルートからの逸脱を意味しており、それも相まって本社出向組は出向先の工場でイジケてしまい、工場の社員とうまく溶け込めない人が多かったという。
ところがAさんは出向先でも挫ける事無く、工場の人達を人としてキチンと認識し溶け込むことに成功した。工場の社員も、それまでのやる気がない本社社員との違いに驚き、彼をチームの一員として気持ちよく受け入れたという。そしてこれを機にこの工場の生産性は著しく向上していく。
これが会社が始まって以来の快挙として評判となり、このAさんの行為は非常に賞賛される事となる。
その後Aさんは本社に戻り、大出世ルートを歩んだとの事だ(確か役員になったはずである)。
勿論このようなうまい話ばっかりではないだろうけど、これもやりたくない事から利益をもたらす事に成功した、1つの見本だろう。
人間、誰だってやりたくない事があるのは時事だ。こんな事書いといてなんだが、僕は今でもPHSがあまり好きではない(笑)だけどそのやりたくない事の先に、意義を無理矢理でもいいから見出すことができたら、それはライバルを突き放す1つのキッカケになるかもしれない。
——————–
いかがだっただろうか?まあ働くのは楽ではない。これは仕方がない事実である。 だけどちょっとしたコツで、その辛い労働を、少しはマシなものにできるのも、また事実である。
最後になりましたが、亡くなられた電通社員の方に、改めてお悔やみ申し上げます。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
著者名:高須賀
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki