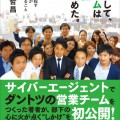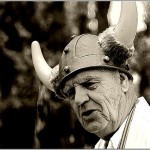以前、部下が上司を評価する人事評価制度について書いた。
しかし実際には「部下が上司を評価する」は通常の企業では劇薬であり、採用している会社は極めて少ない。
しかし、Googleでは検索エンジンのアルゴリズムを用いた360°評価を人事評価制度に用いているという。面白い試みである。
要は、「すごいとみんなが思う人が「すごい」と言っている人は評価が高くなる」評価制度だ。
さらに驚くことに、アメリカの、しかもGoogleのようなテクノロジー企業はともかく、日本で実際にGoogleと同じような評価制度を利用する会社があるという。
なんと、サイバーエージェントが、現場で試してみたという記事があった。
記事を読むと、Googleが特許を有す、本来ならばwebページの評価に用いるPagerankの公式を、純粋に社内の一部門のメンバーをwebページに見立てて公式を適用し、それぞれのメンバーの評価指標を算出している。
4回、この評価システムを用いて人事評価データを作り上げているが、特徴がいくつかある。
1.時期によって評価される人が異なる。(ある時期にトップの評価を獲得していた人が、3ヶ月後にはビリになっている)
2.評価は2極化する
なお、サイバーエージェントでは、最後に総括として、
”約半年間、このPageRank評価を使って、実際にマネジメントに利用したが全て評価結果を公開していることから評価者、メンバーともに異論を唱える余地はなく、定性評価を行う上での材料としては非常に参考になったと感じた。
定性評価について、もし異論がある場合は定量評価を元に異論を唱えることができるため、評価をする上でお互いに客観的に議論ができるのではないだろうか。
例えば、メンバーは異論がある場合は「PageRankが高いのになぜ最終評価が低いのか」という議論を行ったり、評価者も「PageRankが低いので最終評価も高くできなかった」という透明な説明ができる。”
ということで、サイバーエージェントの当該部門の中ではこの評価方法が役に立ったようだ。
人事評価に長く携わった人間として、個人的に思うのは
「民主的な評価制度は、真の意味で社内競争を激化させる」
ということだ。
サイバーエージェントが採用した評価制度は、まさしく「完全自由市場」の中での競争と同じだ。
「短期的に、その場その場でパフォーマンスを高めた企業が、一人勝ちする」
という状況を作り出している。
ウェブページの重要度は「べき乗則」に従う。
従って、「社内の人材の重要性」もべき乗則に従う。これは、「評価がロングテール化する」ということと同じであり、「一部の人間が、ほとんどの高評価をかっさらう世界」である。その影には、全く評価されない多くの人々がいる。
もちろん、サイバーエージェントのこの評価を用いた担当者は、
”いずれにしてもPageRank評価はあくまで最終的な定性評価を行う材料の一つであると考えているため、この結果だけを見て評価とすることは想定していない。”
と述べているので、ダイレクトに評価が反映されるわけでないだろう。
しかし、「客観的に、数値で」、社内の人材の評価がロングテール化したデータを全員に見せるということは、予期しないデメリットを呼び込む可能性もある。
考えられるデメリットは以下のとおり。
1.「1位以外は評価されない」ため、社内に勝ち組、負け組がくっきり出る
2.短期で評価が上下するので、短期志向を助長する
3.顧客や市場ではなく、社内で評価されることを目指すようになる
特に3のデメリットは深刻だ。ウェブページであれば、「サービスの評価者と、サービスの利用者が同じ」であるが、
人事評価は、「サービスの評価者と、サービスの利用者が異なる」ため、顧客を忘れて、「社内の他の人を助ける」ことに邁進してしまうかもしれない。
結果を見る限り、Googleやサイバーエージェントの安易なマネはしないほうがよさそうだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。