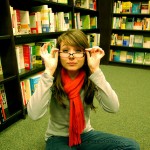コンサルタントだった時代、私は上司たちから「決められた回数以上、絶対にお客さんのところに行くな」ときつく言われた。
「なぜですか?」と聴くと、彼らは
「我々は、時間だけが売り物である。したがって、お金を受けて取らずにお客さんのところに行くということは、自分のところの商品を盗む行為である。それは許されない。」
と言った。
ロジックとしては完全に正しい。時間は商品、売り物である。無料で顧客に提供してはならない。
私はそれを信じ、いかに最小の時間で多くのお客さんを回すことができるかを追求し、最も多いときには、同時に10数社のお客様を一人で担当していた。
しかし、お客さんを最小の工数で支援するためには、恐ろしく工夫が必要だ。
例えば「予定にない相談」は受けない。予めきっちりとした議事を先方に送り、その中にある議題だけを討論する。
お客さんが「余談ですが」と無駄話を始めようものなら「それは後でメールで送ってもらえますか」と制止し、社内に持ち帰って、時間のある時に検討する。場合によっては他の人に任せるなど、生産性をとことん突き詰めた。
さらに、お客さんとのんびり飲みに行っている暇などない。一日に3社〜4社訪問し、夜は昼間の顧客のまとめと宿題の実施、そして明日の準備にあてた。
あの頃は自分が「歯車」だったように感じていた。
ただ、こうなるとどうしてもサービスは「テンプレ的」になり、多少突っ込んだ支援は難しい。
例えば、会議の中で「これをやりましょう」と施策が決まる。顧客の中で担当者が決定され、仕事を任される。
だが、大抵の場合はうまくいかない事がわかる。
なぜならば、多くの場合「仕事のできる方」は多くの業務を既に抱えており、新しくリソースを割いて施策を実施することは不可能だからだ。
責任感のある彼らは、締切までになんとか格好がつく成果物を持ってたり、実施してみたりするのだが、明らかに時間が不足しており、多くの場合その質は低かった。
本来、新しいことは試行錯誤を重ねなければならないので、顧客の担当者のかなりの時間的リソースが必要とする。
そんな時「私がやりましょうか?」とはとても言えない。
親切なことはできない。身の破滅につながる。
「客の仕事を勝手に請けるな」という上司たちの厳しい規律があるからだ。もちろん、月次の目標、年間の売上を達成するだけで必死だった、という事情も当然あった。
ところがあるシステム開発会社でのことだ。
その会社は慢性的に人が不足しており、プロジェクトに参加しているメンバーたちは明らかに疲れ切っていた。だが、もちろんこのプロジェクトは期限が決まっており、完遂できなければ会社に大きな損害が発生してしまう。
プロジェクトメンバーたちはそれでも歯を食いしばって、頑張っていたが、上のような事情もありどうしても期限に間に合わない仕事がポツポツと発生してくる。
メンバーの年齢が自分に近かったこともあり、ついに私は見るに見かねて、会社に内緒で仕事を手伝ってしまった。もちろん完全にボランティアである。
「本当に、アテにしないでくださいね」
と彼らに言ったが、もはや私が手伝わずして、プロジェクトの期限内での完遂は不可能であった。
こちらも必死に手を動かし、彼らのプロジェクトが無事に終わるように休日にも彼らの会社に足を運ぶ。もはや仕事なのか、単なる苦行なのかわからなかったが、とにかく仕事はやりおおせ、プロジェクトは終わった。
ただ、私はビクビクしていた。会社にバレたら、ただ事では済まない。キツイ叱責を受けた先輩も何人かおり、重大な規定違反になると出世にも響く。
見て見ぬふりはできなかったが、正直私は後悔していた。
「結局、そういうのはお客さんのためにもならないよ。自分たちで作ったものしか、実行しようと思わないから。」
とも言われていた。
だが、その後の展開は面白いものとなる。
「また、仕事を頼みたいんだけど」と、継続的に仕事が来るようになったのだ。社内ではクロスセルの目標があったが、お陰で私はクロスセルの目標を簡単にクリアすることができた。
また、その会社へ訪問した時の雰囲気も変わった。
それまでは「部外者」的な扱いだったものが、「仲間」という立ち位置になり、さまざまな内部事情も教えてもらえるようになった。
会社の教えは「コンサルタントは相手の会社の社員になってはいけない」というものだったが、私はそれに疑問を持つようになった。
確かに会社の言うこともわかる。
「相手の会社の社員」となってしまえば、何か問題が起きた時にスケープゴートにされる可能性もあるし、社内で余計な反発をもらってしまう可能性もある。
だが、そう言ったリスクを認めつつも、「一緒に同じ仕事をする」ということは、それ以上のメリットもあるのだな、と私は理解した。
つまり、ビジネスというのは、規律とルールよりも、親切と貢献をベースにすべきである、と悟ったのである。
ペンシルバニア大の心理学者アダム・グラントは「見返りを期待せずに人に親切にすること」が結果的にビジネスの成功につながることを研究で明らかにした。
彼はこんなエンジニアの言葉を引用している。
見返りのために、人に親切にするんじゃないんです。グループの目標は、与えることの大切さを行きわたらせること。取引する必要もなければ、交換する必要もありません。
だけど、グループの誰かに親切にすれば、自分に助けが必要になったとき、きっとグループの誰かが親切にしてくれますよ。*1
私も全く、そのとおりであると感じる。
ただ、当面の生産性を犠牲にして人に親切にすることを実践するのはとても難しいのだが。
*1
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。