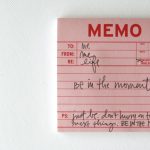会社はビジョンや理念のような、芯となる価値観を持つべき、とする方は多い。、コミュニケーションや意思決定のためのツールとして便利だからだ。
だがその一方で、その芯となる考え方が形骸化している会社もまた多い。
社員に理念を訪ねても、ぽかんとした顔をされることがどれほど多いか、想像するに難くはない。
なぜ社員は価値観を重要だと感じつつ、一方でそれを無視するのか。
それは「会社が提示する価値観」が彼らの琴線に触れていないからである。
例えば、理念が「誰でも賛成するでしょ」といった、議論の余地がないようなものになっているからである。
例えば「お客様のために誠心誠意仕事をする」という理念があったとしよう。
賭けてもいいが、この理念は誰も見ないし、覚えてもいないだろう。
なぜなら「当たり前」という感覚を皆が持つからだ。
誰もが納得するような、すなわち当たり障りのない理念は、存在しないのと何ら変わりはないからだ。
人の琴線に触れる理念や価値観というものは、もっとギリギリのものである。
だれもが「まあ、そうだよね」という程度のものでは、人の心に訴えかけない。
人によっては「絶対無理」とか「いやいや、ありえないでしょ」、「そこまでやっちゃいますか」というものである。そこまで言ってはじめて、価値観は力を持ち、判断基準となりえるのである。
だから必然的にそれらは物議を醸す。
そして、面白いことに物議を醸す「価値観」は、どの会社でも似ている。
従業員が「こんな考え方の合う組織にいるなんて幸せ!」と思ったり、「あれ……わたし、会社と価値観が合わない」と戸惑うのは、以下の項目だ。
1.会社は金儲けをする場か、楽しく仕事をする場か。
「会社は金儲けをする場だから、仕事が楽しいかどうかは二の次だ!」という方々と、「仕事は楽しくあるべきで、お金はその必要条件に過ぎない」と考えている方々は、しばしば衝突する。
2.職場の人間関係は親密であるべきか、ドライであるべきか。
飲み会や、家族を含んだイベント、社員旅行などを必要とする人々と、会社の人とは仕事以外ではかかわりを持ちたくない、という人々は、あまり相いれない。
前者はしばしば成果よりも人間関係を重視する傾向にあるし、後者は人間を「成果を上げるためのパーツの一つ」と思う傾向にある。
3.スキルアップに責任を負うのは、会社か、個人か。
「積極的に会社が教育してくれるんでしょ?という人々と、「結局、頼りになるのは自分だけでしょ」という人々は話が合わない。
4.同質性の高い集団にすべきか、多様性を追求すべきか。
同じような能力と考え方を持つ人々で組織を構成したいか、それとも能力も考え方もバラバラな人々を組織化することを選択するか。
前者の集団は同調圧力が高い一方で、目的が明確ならば強い力を発揮する。
5.経営者はワンマンであるべきか、チームで運営されるべきか。
言い換えれば、トップダウンが好みか、ボトムアップが好みかという話だ。いつの時代にもカリスマが好きな人は数多くいるし、権威が嫌いな人もそれと同じくらい数多くいる。
6.最大を志向するか、最適を志向するか。
組織はできるだけ早いスピードで大きくしなければならない、という人々と、マネジメントが困難なサイズまではむやみに大きくしない、という人々とでは会社の運営に対する考え方が全く異なる。
前者はしばしば、恐ろしく挑戦的な目標を掲げるが、成功すればリターンは大きい。後者は慎重に組織を運営するので崩壊しにくいが、大きな成功を一夜にして成し遂げる、という訳にはいかない。
7.感覚主導か、論理・データ主導か
会議において最も価値観の違いが顕著に現れるのが、感覚主導か、論理・データ主導か、という話だ。
前者の人々は、「データでは見えないものが大事なんだ」と主張するが、後者の人々は「人間はバイアスに支配されており、感覚などアテにならない」と主張する。
8.職人志向か、標準化志向か
前者は「会社の競争力は本質的に個人に属するもの」と考えており、後者は「会社に属するもの」と考えている。クリエイティブ(と当人たちが考えている)仕事ほど、前者を志向する。
9.成果志向か、プロセス志向か。
成果のみで評価する、という会社と、成果よりもむしろプロセスに評価の力点を置きます、という会社では成果に対する考え方が全く異なると言ってもよい。
多くの場合前者は短期的成果を重視し、後者は長期的成果を重視する。
10.全体志向か、個人志向か。
組織のために個人があるのだ、という考え方、いわゆる全体主義と、組織は個人の活動のためにあるのだ、という個人主義は相容れない。
もちろん、聡明な読者諸兄は、ほとんどの会社はこれらの価値観に対してはっきりと白黒をつけているわけではなく、多くの場合はその中間に存在していると知っているだろう。
だが、自分の属している組織が「どちらよりなのか」を知っておくだけでも、価値観の違いによるストレスや摩擦は軽減されるのではないだろうか。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。