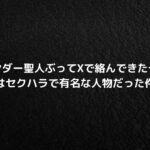テレビショッピングでよく知られる「ジャパネットたかた」の業績が、マズイことになっている。
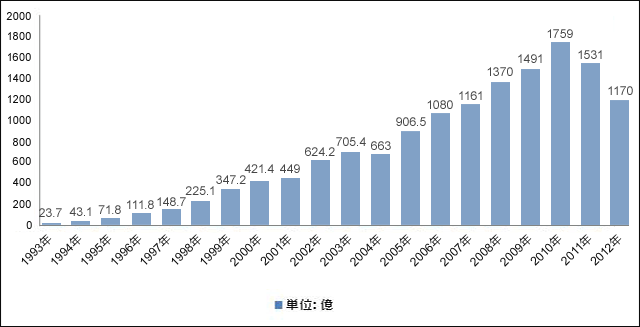
2010年のピークを境に、2012年は2007年と同水準、今年の決算がマズければ、社長は引退すると宣言している。
なぜ、ジャパネットたかたの業績が伸び悩んでいる、というより下降しているのか。記事によれば、主たる原因は家電の売上の落ち込みだ。
現在、家電が売れなくなっているという。2010年には月間で200億円以上の売上を出していたテレビが、今では5~10億円程度になった。
また好調だったパソコンもスマートフォンに食われ、今年になってからはタブレット端末が大変な勢いで売れている。さらにはカメラ機能を搭載したスマートフォンによってデジタルカメラが、今年に入ってからはカーナビが売れなくなってきているという。
Amazonなどのインターネット通販に押されている、という話もあるが、それは的はずれだろう。それは、Amazonとジャパネットたかたの顧客層が異なるからだ。
ジャパネットたかたの売上比率にはユニークなデータがあります。40代以上の売上の約8割に上り、20代と30代の売上は合わせて7%しかありません。しかも、売上商品の多くは40代以上に馴染みの薄い家電やコンピュータなどの機器となっています。
中高年の多くは、電子機器に馴染みが薄いため、ネットでの売上というのは期待できません。中高年にターゲットを絞り、ピンポイントに宣伝活動を行った結果が、折り込みチラシやCMの多用につながったと考えられます。Amazonなどの競合に負けずに張り合って戦えるのも、インターネットという同じ土俵を避け、ニッチな中高年という年齢層に絞って戦略を考えたからでしょう。(U-NOTE)
ジャパネットたかたの商品は安くない。というよりむしろ「高い」。だから、Amazonを使うような人々は、ジャパネットたかたからは買わない。ジャパネットたかたから購入するのは、テレビを良く見て、新聞をとっている中高年たちだ。
今まではデジタル機器に接点がなかった中高年にも、デジタル機器への扉を開いたという意味で、ジャパネットたかたの貢献は非常に大きい。デジタルテレビ、デジカメ、パソコン、こういった便利ではあるが、「ちょっと敷居が高い」機器類を、わかりやすく実演して届けた事が、支持されたのだろう。
しかし、おそらくそういった人々の需要が一巡した今、彼らはどこに市場を求めるのだろうか。
現在(2013年11月)のチラシを見てみると、「羽毛布団」や、「マッサージチェア」、「掃除機」、「ハンディカラオケ」、「ウォーキングシューズ」、「ルームランナー」などが掲載されており、「脱家電」を目指しているような動きだ。
数多くの会社を見たが、多くの中小企業では現在ある商品を「もっと多く売る」ことにはリソースをつぎ込むが、「商品開発」には消極的だ。ひどい時には、社長が片手間でやっていたり、100名の会社でも5名程度しか専任がいなかったりする。
しかし、どんな商品であってもいずれ市場は飽和する。儲かった時に社長の車をレクサスにしたりせず、既存商品が好調なときほど「今すぐは儲からない事業」やっておくべきなのかもしれない。
「ジャパネットたかた」が今後、商品ラインナップの転換をどのようにやっていくのか。注目である。
つづき:ジャパネットたかたがV字回復、社長交代。何が起きたのか?
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
筆者Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (安達の最新記事をチェックできます)