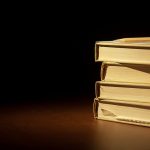直木賞作家であり、シナリオライターでもあるの向田邦子さんは、本が大好きだったらしい。
エッセイを読むと、本好きの様子が微笑ましく書かれている。
乱読で読みたいものを手当たり次第に読む方である。
寝転がって読み、ものを食いながら読む。
ページを折ったりシミをつけたりは毎度のことで、本を丁寧に扱う人から見たら風上にも置けない人種であろう。
(中略)
読書は、開く前も読んでいる最中もいい気持ちだが、私は読んでいる途中、あるいは読み終わってから、ぼんやりするのが好きだ。
砂地に水がしみとおるように、体のなかに何かが広がってゆくようで、「幸福」とはこれをいうのかと思うことがある。*1
向田邦子さん同様、個人的に読書はなかなか質の高いエンタテインメントだとは思うのだが、もちろんそこは人それぞれで、本を読まない人はかなり多くいる。
そう言う方々から言わせれば、読書など時間の無駄なのだろう。読書に全く興味を示さない人もいる。例えば前職の時、私は後輩に読んでほしいと思った本を無理やりあげてしまう、という悪いクセがあり、後輩の机の上でホコリを被っているのを見て、「ああ、悪いことをしたな」と思ったものだ。
だが、「読めるけど読まない」のはともかくとして、「本などの長文が読めない」ことはもしかしたら、これから、想像以上に不利に働くかもしれない。
昔、塾の先生から
「国語ができる子の成績を伸ばすのは簡単だが、国語ができない子の成績を伸ばすのはかなりの長期戦を覚悟しなければならない」
という話を聴いたことがある。
それを象徴するかのように少し前
「現状では人工知能は文章を理解していない。だが、驚くべきことに「読めていない」はずの人工知能よりも国語の成績が悪い子がいる」
というショッキングな記事を見た。
AI研究者が問う ロボットは文章を読めない では子どもたちは「読めて」いるのか?
これまでのところ、テストを受験した公立中学校生340人のうち、約5割が、教科書の内容を読み取れておらず、約2割は、基礎的な読解もできていないことが明らかになってしまった。
そして、偏差値の高い学校の生徒ほど、リーディングスキルテストの成績もよい。「読める」子が偏差値の高い学校に入っている可能性がある。
どうやって「読める」ようになるのか、その原因はまだわからない。
実際、「読めない」ということは、現代において極めて不利な条件である。
例えばビジネスパーソンの中にはメールが苦手で「電話」に強いこだわりのある方がいるが、電話は相手の時間を強制的に奪うものであり、情報の受け手として、これを嫌う人も多い。
お互いに「電話が良い」であればよいが、今は「メールの方が良い」という方も増えており、「メールの読み書きが苦手」では済まない。
また、現在の高度な仕事はほぼ全てが「知識」をベースにしているため、知識労働者でなければ、待遇面で満足の行く職を得るのも難しい。
ピーター・ドラッカーはこう警告する。
1900年ごろ、実際的な目的を持ちうる知識分野は、法律、医学、教育、宗教など幾つかの伝統的な分野に限られていた。
今日では、文字通り、数百にのぼる知識分野が雇用の場として開かれている。
あらゆる知識分野が、組織、特に企業と政府機関において必要とされている。
したがって今日はでは、誰でも自らの能力に最も合った知識分野を選択し、かつ雇用の場を見つけることができるようにならなければならない。*2
そして「知識労働者」は基本的に「読める人」でなければならない。
人間の体系的な知識の殆どは、「文字」と言うかたちで記録されており、そこから知識を読み出すには「読める人である」ことが必須の条件となるからだ。
読書ができない、ということは、本にある知識を吸収できないというだけではなく、文字情報を通じて正確な情報をやり取りできない、ということである。
また、web上の情報については信頼性に難があるため、出典元を当たることが重要なのだが、「本を読めない人」は、テレビやネットに溢れる、わかりやすく噛み砕かれた情報にばかり触れ、出典元の複雑な言葉で書かれた情報を当たることを嫌う傾向にある。
そのため、容易くデマゴーグに煽動されたり、メディアの意図通りに過剰反応してしまう。
また、ニュースサイトやキュレーションサイトにあふれるコメントを見ても、「このコメントを付けた人は記事の文章をきちんと読めていない」とはっきりわかってしまうコメントも数多くあり、この問題が深刻であることを物語る。
「英語力の強化を」と言うビジネスパーソンも多いが、実は日本語をきちんと扱うことができなければ、英語力以前に、コミュニケーションの根本が破綻する。
また「本なんかより経験が重要」という方もいるが、人生で経験できることは極めて限られており、また経験からしか学ぶことができないのであれば野生動物と変わらないのである。
だが「実は日本語をきちんと読めていない」という事実は普段極めて認識しにくい。
特に、普段本を読まない方は意識して読解能力を高めていかなければ、後々とても困ることになるのでは、と危惧している。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
*1
*2