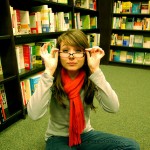付き合いが少ないことを「貧しい」と言うと、憤慨する人がいるかもしれない。
ならば、「弱い」と言ったらどうか。
これも、憤慨する人がいるかもしれない。
だが言い方がどうであれ、現代社会において付き合いが少ないこと、ましてや孤独に近い状態であることは、社会的生物として得ることが少なく、身体や精神の危機への備えが脆弱であることは確かだ。
だから、付き合いが少ないという状態を経済的な尺度で言えば「貧しい」ということになるし、生物の生存という尺度でみれば「弱い」ということになる。健康という評価尺度を持ち出すなら「不健康」ということになるだろう。
独りでも一応生きていける。だが、強く生きていくのは難しい
もちろん、付き合いが少ないくてもタフに生きている現代人はいる。
人間同士が助け合わなければ毎日の生活が成り立たなかった過去と比べれば、まだしも現代社会は独り暮らしをやりやすい。安全な都市空間。コンビニやスーパーマーケット。インターネット。そういったもののおかげで、金銭収入さえ確保できれば、現代人はほとんどのものを簡単に手に入れられる。“ご近所付き合い”や“村社会”的なしがらみにもあまり束縛されない。
それでも、付き合いの多寡は、生活の質や人生の難易度に相当な影響を与える。
近年は、孤独な生活は健康に良くないとする研究が立て続けに発表されている 。身体面でも精神面でも、健康を保ちたければ付き合いは無いよりはあったほうが良い。
「孤独死は独居老人より独身40代のほうが多い」特殊清掃人が断言
上掲リンク先の文章は『SPA!』によるものなのでちょっと煽りが効いているが、実際問題、こうした危機に直面しやすいのは孤独な一人暮らしをしている人だろう。
不摂生があっても誰もたしなめてくれず、悩みやストレスを愚痴ったりシェアしたりする相手がおらず、健康が害される段階に至っても誰も病院に連れていってくれない状態では、人は意外と簡単に死んでしまう。ワーカホリックな人も、繁華街を遊び歩いている人も、自宅にひきこもってインターネット漬けになっている人も、いずれもそうだ。
孤独でも健康な状態を保つためには、人一倍の節制とマネジメント能力、健康に対する注意深さが必要だろう。そういったものが無くても健康を維持できるのは、二十代から三十代まで、あるいはせいぜい四十代あたりまでだ。歳を取るにつれて、健康マネジメントの必要性と難易度は高くなっていく。
健康以外にも、人付きあいはたくさんのものを提供してくれる。コネクションがあること・顔が利くことはビジネスでも趣味生活でもプラスの影響をもたらす。多種多様なものの考え方に触れること・知的な刺激を与えられることも、付き合いがもたらすプラスの面だ。
こうしたプラス面のいくらかはインターネットによって代替できるようになったが、実際に人に会って話をしなければ得られない刺激はまだまだある。なにより、コネクションを作り上げるほどの“信頼”や“信用”を得るには、やはり付き合いが欠かせない。
そうした付き合いに伴うメリットは、近年はソーシャルキャピタル(社会関係資本)と名づけられて注目され、研究の対象にもなっている。アメリカの話だが、チャールズ・マレー『階級「断絶」社会アメリカ』によれば、近年のアメリカでは、経済力のある人のほうがこのソーシャルキャピタルにも恵まれているという。
これによれば「下町の貧乏人は、うまく助け合って生きている」というステロタイプは現代のアメリカ社会には当てはまらない。経済的に貧しい人は、付き合いの面でも貧しく、孤立しやすい。お金も人脈も“強者総取り”の構図が、この本には容赦なく記されている。
それともしがらみを最小化した自由な社会か、それとも付き合いの格差社会か
日本でも、こうした“強者総取り”は他人事ではない。
郊外空間や都市空間で人々が生活しはじめ、地域共同体が衰退し、思想面でも空間面でも個人主義が浸透していったという点では、日本は着実にアメリカ社会の後を追いかけている。
独りでも生活しやすい社会のインフラができあがり、その利便性を生かして自由に暮らせるようになったこと自体は歓迎すべきことだろう。しかし、どれだけ社会のインフラができあがっても、やっぱり人は独りでは生き辛い。健康や生活もマネジメントしにくいし、信頼や信用も獲得しにくい。
大昔の村社会などとは違って、現代における付き合いは、義務として課せられるものではない。付き合いをしたい人はすればいいし、しない人も当座は生きていけるだろう。だが、それゆえに、付き合いがもたらす“果実”は付き合いの盛んな人のところにとことん集まり、集まらない人のところにはとことん集まらなくなってしまった。
この構図を、しがらみを最小化した自由な社会と呼ぶべきだろうか。
それとも、付き合いの格差社会と呼ぶべきだろうか。
自己マネジメント力のしっかりした個人と、たくさんの人と難なく人付き合いをこなせる人にとって、今日の社会は定めし最適だろう。若くて行動力のあるうちは特にそうだ。だが、誰もが自己マネジメント力やコミュニケーション能力に恵まれているわけではないし、若さゆえの行動力は、やがて失われる。病気を患い、それによって付き合いを失ってしまう人もいるだろう。
「驕れる者も久しからず」。しがらみが少なく自由な社会は基本的には良いものだが、付き合いが少ないことが貧しさや弱さに直結する社会を、私は、無邪気に寿ぐことはできない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)など。
twitter:@twit_shirokuma ブログ:『シロクマの屑籠』