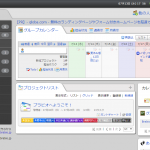赤ちゃん、特に歩けない時期の赤ちゃんは、親に世話されなければ生きていけません。
かわいらしいけれど、無力で何もできない存在。そんな風に思っている人も多いかもしれません。
でも、実物の赤ちゃんはそうではありませんでした。そんな話を、今回はツラツラ書いていきます。
「本を読んで」赤ちゃんを知ったつもりになっていた
私は人間心理についての仕事に就いているので、子どもの発達心理については、それなり勉強をしているつもりでした。
発達心理学系の本や、進化生物学系の本には、「赤ちゃんはそんなに受け身じゃない」「赤ちゃんアクティブだぞ」と書いてあって、そうか、赤ちゃんってのは母親に世話されるだけの“でくのぼう”ではないのか、と知識としては知っていました。
で、ある日、我が家に赤ちゃんがやってくることになりました。
少し肌寒い、小雨交じりの曇り空のある日、静かに眠る赤ちゃんが大切に抱えられて運ばれてきました。
家庭の新しいメンバーが、それも、人間になったばかりの生命体がやって来ることが、私には、途方もないように感じられました。
赤ちゃんを迎えて早々に気付いたのは、「泣く」ということ自体、生まれて間もない赤ちゃんにとっては大変な努力の産物だ、ということでした。
「泣く」という行動には、ものすごいエネルギーが必要です。泣くためには激しく呼吸しなければならず、それで鼻腔や咽頭が乾き過ぎると感染症になってしまうリスクもあります。が、それでも赤ちゃんは一生懸命に泣きます。
母親に世話されなければ生きていけない状況だからこそ、その母親を呼ぶための最終手段として、「泣く」という選択にエネルギーを惜しまず、リスクも冒していく――そのさまは、なかなか凄みがあって、積極的だと私は感じました。
もうひとつ、生まれたての赤ちゃんでも口の筋肉はしっかり動かします。
おっぱいを吸うことで栄養をもらうだけでなく、吸うことによって母親とコミュニケーションしているのが見て取れました。精神分析の世界では、赤ちゃんの時期を「口唇期」と呼ぶことがありますが、これを命名した奴は冴えている! と感じました。人生って、食事とコミュニケーションが合体した状態で始まるんですね。
どんなに小さくても、口はもう“一人前”です。
赤ちゃんが「空気を読む」ように
それから数ヶ月もしないうちに、赤ちゃんが「空気を読む」ようになりはじめました。
周りの大人の動きを観察しながら泣き声をあげるというか、本当におなかが減っている時の泣き方と、「とりあえず手近な大人を呼ぶ」時の泣き方に、はっきりとした違いがみられるようになったのです。
抱っこするかしないかを巡って、原始的ながら、“かけひき”が感じられるようになってきました。言葉は喋れなくても、コミュニケーションをとる意志と能力はもう持ち合わせているのです。
やがて、つんざくような泣き方を覚えたり、オモチャやぬいぐるみの手触りを確かめたり、行動にバリエーションが生じてきました。
この時期の赤ちゃんが、いろいろなモノを口元に運んでいくのを眺めていると、相対的に発達している口唇を使って、赤ちゃんなりにモノを調べているようにもみえます。
危ないものを呑み込まれては困りますが、赤ちゃんが外界を学ぶ一手段として、口の感覚は重要なのでしょう――手足や皮膚の触覚と同じぐらいには。
赤ちゃんと付き合っているうちに、「案外、言葉が通じない者同士でもコミュニケーションって成立するもんだな」と感じるようになりました。
あるいは、言葉が通じない者同士だからこそ、言葉以外のチャンネルが繋がりやすくなるのかもしれませんが。
生後7ヶ月ほどにもなると、赤ちゃんは「いないいないばあ」を喜ぶようになり、「ママじゃなきゃヤダ病」が深刻になってきました。人見知りも始まります。人見知りが始まるということは、それだけ、周りの人間をしっかり眺めているのでしょう。
母親がいない時に一人で目を覚ました赤ちゃんが、私にニッコリと微笑み、しばらくご機嫌に過ごしていたのが、母親が近づいてくる気配を感じるや泣いて“みせて”注意を惹こうとするのを見て、驚かされたこともありました。
これは、我が家の赤ちゃんがたまたまそうだったという話かもしれませんが、言葉のわからない時期の赤ちゃんでも、泣いたり笑ったりといった情緒的なコミュニケーションの精度は高く、むしろ、大人よりも的確にインプット/アウトプットできているように感じられました。
ただし、そのぶん赤ちゃんの情緒的なシグナルの影響は避け難く、泣いたり笑ったりに振り回される部分はありましたし、親自身の不安や怒りを赤ちゃんに伝えないようにするのも、かなり難しいように感じられましたが。
人間は、生まれながらにコミュニケーションする動物
そうやってコミュニケーションしながら赤ちゃんと付き合い続けているうちに、私は、赤ちゃんの観察者としての心構えより、養育者としての心構えのほうが強くなっている自分自身に気付くようになりました。
もちろん、そうなった一因には、私自身が赤ちゃんを観察したがっていたからもあるでしょう。
でも、それだけとは思えません。コミュニケーションする主体としての赤ちゃんが巧みにコミュニケーションを続けてくれて、コミュニケーションに巻き込んでくれたおかげで、私自身の心が変わっていったのだと思います。
赤ちゃんのコミュニケーション能力によって、私は、養育者としての心構えを身に付けられた、と言い換えてもいいのかもしれません。
これから赤ちゃんを育てる人は、是非、赤ちゃんをしっかり観察して、どうにかコミュニケーションを続けてみてください。
言葉に頼らなくてもコミュニケーションが成立し、その結果としてお互いに影響を受けあいながら変わっていくということ、こんなに小さな生物にもコミュニケーションする意志と能力が備わっていることが、実感できるかと思います。
そしていつしか、自分自身が養育者の心構えに変わっていることに気づくでしょう。
小さくても、人間は人間。
やはり、コミュニケーションする動物なんだなと知りました。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
著者:熊代亨
精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。
通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)など。
twitter:@twit_shirokuma ブログ:『シロクマの屑籠』

(Photo:Zaheer Mohiuddin)