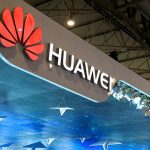努力できるのも才能のうち、とよく聞く。
「できないのは努力していないからだ」という意見への反論として言われることが多いように思う。
つまりできないのは努力していないからではなく、(努力する)才能がないからだ、と。
努力が才能なのかそうでないかについてここで論じるつもりはない。
ただ、努力している人がどういう心理で努力しているのかについて考えてみたので、書いていきたい。
努力しない人、あるいは努力する才能がない人にとって、努力している人は不思議に見えないだろうか。
報われないかもしれない未来に対して時間と労力を費やす行為の連続は、必ずしも賢い選択をしているように見えるわけではないだろう。
よほど目標への思いが強いのか、向上心が溢れているのか、成長意欲が高いのか……努力している人は、とにかく並大抵ではない思いを抱いている人に違いないと思ってしまうかもしれない。
でも、私は意外とそうではない人が多いのではないかという気がしている。
自分のことで恐縮だが、私は自分で決めたことについては割と努力できるほうだと思っていて、一方で、全く興味のないことについて努力することは絶対にできないという自覚もある。
自己分析になってしまうが、自分が努力しているときはどういう心理なのか、少し考えてみた。
結果がわからないけれど、勝ちたい試合が目の前にあるとき、人は努力する
私の感覚では、努力は「100%でない、ポジティブな可能性」を感じているときにしかできない。
「100%でない」というのは文字通りで、自分がどうなるかわかりきっているとき、努力しようとは思いにくいということだ。100%負ける試合・100%勝てる試合の前に練習する気は起きてこないだろう。
結果がわからないけれど、勝ちたい試合が目の前にあるとき、人は努力する。
で、ここからは完全に持論になってしまうが、私は「自分の実力をきちんと把握できている人はほとんどいない」と思っていて、「それゆえに人は努力し続けることができる」と思っている。
どういうことか。
人は自分の実力をよくわかっていない。回数を重ねてもわからない。
今日は試合に勝った。でも明日は勝てるかわからない。翌日、勝った。でもその更に翌日は勝てるかわからない。この繰り返しで、自分の実力は何度勝ち続けてもわからない。
まして途中で負け試合が挟まってくると、真の実力は一層わからなくなる。
「試合に勝ち続けていたら、さすがに実力はわかるのでは?」と思うかもしれないが、目標を達成するまではわからない。つまり優勝するまでわからないのである。(ちなみにこれまでずっと例として“試合”を挙げているが、当然様々な競争場面を想定している。)
少し話しは変わるが、「平均への回帰効果」という言葉を知っているだろうか。
『論理パラドクス 論証力を磨く99問』(三浦俊彦)という本から引用すると、次のような問いから説明することができる。
定期的なテストの成績を集計したところ、ほめられた子どもはその次の試験で成績が下がり、叱られた子どもはその次の試験で成績が上がることが多い。
これは、統計的に確かめられた事実である。この結果は、いつ、どの地域で、どのようなテストで、何年生を対象にした統計でも変わらなかった。どの条件を補正しても同じだった。(略)
さてここから、「子どもはほめるより叱って育てた方が伸びる」という教訓を引き出せるだろうか。
答えはNOだ。その理由が「平均への回帰効果」で説明できる。
試験でほめられたということは、(その子の基準からして)よい成績をとったということであり、叱られたということは、(その子の基準からして)悪い成績をとったということである。
そのほとんどは、本来の実力から外れた出来を示したという場合だろう。したがって、次にはその子の実力相応の成績にもどる確率が高い。
試合に勝ったからと言って、それが実力だとはなかなか思えない。
実力がわからないということは、良い結果の原因は実力以外にあると思ってしまうということであり、つまりは幸運だったという結論に結びつきやすい。
文字にすると、「そんな馬鹿な……さすがにある程度実力は把握しているでしょう」と思うかもしれないが、明確に「これは運のおかげである」と思っているわけではなく、ぼんやりと「今回は結果がよかったなー」程度に捉えていて、運とまでは言わないにしても、「なんかよかったなー」と。
「今回はよかったけれど、平均への回帰効果で、次は今回ほどうまくはいかないかもなー」と、なんとなく思う。だから、努力する。その繰り返しだ。
勝ち続けると平均は上がっていくはずだが、「幸運」という「偶然」の出来事は平均には加えられないので、平均の値は変わらない。「“たまたま”幸運が続いているだけ」なのである。
何も、平均への回帰効果を意識して考えているわけではない。ただ、無意識のうちにそう思ってしまっているのである。少なくとも私はそうだ。今回うまくいったのは運が良かったからで、次もうまくいくとは限らない。だから、努力しよう、と。
努力して勝ち続けても、それは「幸運が続いているだけ」なので、最後まで努力し続ける。それが、努力していない人の目には、不思議に映るのである。
「今うまくいっているのは、幸運が続いているだけだから、努力しよう」という心理。これが全てではないにしろ、私はある一面を表しているような気がしている。
☆★☆★☆
ではまた!
次も読んでね!
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
名前: きゅうり(矢野 友理)
2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。
【著書】
「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)
「LGBTのBです」(総合科学出版、2017/7/10発売)
(Photo:Michael Griffin)