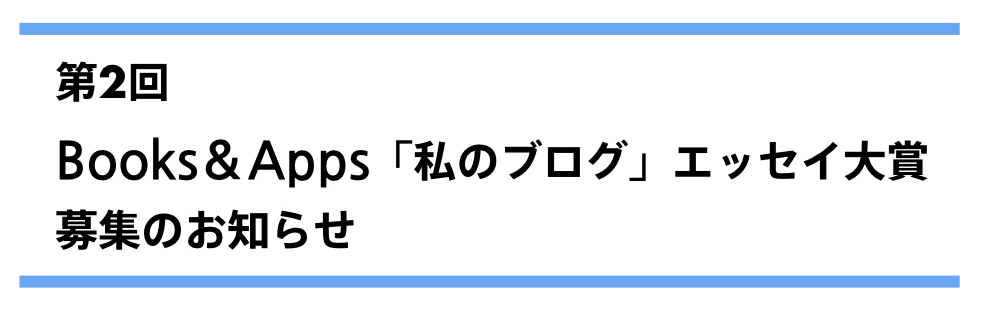ネットでの相談が目に飛び込んできた。
就職活動を1年間してきましたが、事務の内定を取れません。
このままだとまずいということはわかっているのですが、最近では、就職活動を頑張る気が起きません。もうやめたいとすら思ってしまいます。
非正規雇用で働いていたばかりに悲惨な現状にあるという話は、ネットにいくらでも転がっていますね。それを見ると20代のうちに正社員にならないといけないと思うのですが、やる気が出なくて困っています。
厳しい言葉でもいいので、どうすべきか教えてください。
もし本当のことであれば、相談者のことをとても気の毒に思う。
だが、気の毒に思うのは「内定を取れない」ことに対してではない。1年以上も同じことを繰り返して、「前提を疑うこと」ができなくなっていることにである。
例えば、あるIT業の会社での話だ。
受託開発をしていた彼らは納期遅延と、長時間労働で苦しんでいた。現場の技術者たちは、必死の努力をしていたが、思うように状況は改善されない。
経営陣や現場にヒアリングをかけると、
「生産性向上が必要だ」
「見積もりの精度を高めなければならない」
「スキル向上で効率よく開発を」
「ツールを導入したい」
と、様々な改善策があがってきたが、どれも時間がなく、一向に改善は進んでいなかった。
しかし、ある「前提」については、誰も疑いを持っていなかった。
それは何か。
「売上目標」を達成しなければならない、という前提である。
売上目標を達成するには、営業がかなりの努力をして、仕事をとってこなければならない。
しかし、目標は「成長」という名目で、それなりに厳しい数字に設定されている。
したがって、
売上目標が高い ⇒ 営業が無理をしてでも仕事を取ってくる ⇒ 現場に負担がかかりプロジェクトが遅延する ⇒ 売上目標の達成が厳しくなる ⇒ 更に営業が無理をする
という、フィードバックループに陥っていたのである。
そこで、経営者に「売上目標はどのように立てているのですか?」と聞いた。
すると、「前年の数字に、成長目標をプラスして目標を作っています」と回答した。
「なぜ、成長目標をプラスするのですか?」と聞くと、「全員の給料を上げなければならないし、利益も出さなくてはならない。」という。
だが、
「本当に全員の給料を上げなければならないか」
「利益額は今の水準が適切なのか」
「大幅な成長が必要なのか」
については、細かな検証は誰も行っていなかった。
敢えて言えば、「何となくこれくらいは成長が必要」という思い込みによる目標である。
だが目標値を下げることで、現場の負担のみならず品質的な改善も成し遂げることが可能かもしれない。
現場の負荷を下げなければ、新しい試みはできないし、そもそも「永遠の成長」はありえない。
「前提」を疑うことで解決可能な問題は、極めて多いのである。
「前提条件」という言葉がある。
その定義は、PMBOKガイドによれば、
「計画を立てるにあたって、証拠や実証なしに真実、現実、あるいは確実とみなした要因。」
とある。
この「前提条件」を疑うことは、非常に強力なツールであり、例えばディベートで勝つ時にも有効である。
相手が「出発点」としている前提、仮定を攻撃することで、その後の論理を全て無にできるからだ。
これは、自問自答する時にも極めて有効だ。
「私はどんな前提に囚われているのか?」と言う問いを、自分に向けるのである。
冒頭の相談者であれば、おそらく前提としている条件はちょっと見る限りだけでも、3つある。
・事務仕事に就かなければならない
・20代のうちに正社員にならなければならない
・就活は頑張らなくてはならない
これは
「過労に陥っているのに、会社をやめることができない人」や
「ブラック企業で酷使されてしまう人」にも
同じことが言える。
「つらいならやめればいい」という言葉が、本当に辛い人に届かないのは、前提を疑うことにはエネルギーをつかうため、それができない状態になっているからである。
前提とは、すなわち公理である。公理が間違っていれば、間違った結論にしかたどり着かない。
逆に言えば、「物事がうまくいかないときは、前提をうたがうべき」という癖付けがされている人は非常に強い。
そういう人は、問題解決能力が高く、時として偉大な発見に至ることもある。
デカルトは真理を追求するために「間違った前提」から推論を出発することを怖れ、「絶対に疑うことのできないもの」を探した。
そして、彼は「今ここにいる私が疑っている、という事実」から、推論を出発したのである。
それが、「我思う故に我あり」という言葉だ。
アインシュタインは、古典力学で検証なく受け入れられてきた「時間の流れは不変」「光速度は可変」という前提を疑うことで、相対性理論を構築した。
このように、世界の捉え方、人生の見方を変えるには、「公理」、すなわち「自らが検証なく受け入れている真実」を疑わなくてはならないのである。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
・最新刊が出ました。
・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました。
(Photo:d26b73)