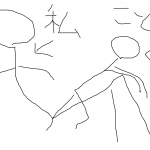またひとつのツイートが炎上しているようだ。
さっきコンビニにて
私「アイブラ8ミリカートン」
大学生ぐらいの店員「????少々お待ちください(煙草キョロキョロ」
私「(イライラ)」
店員「番号で言ってもらってもいいですかね?」
私「見えねぇよ」
店員「….これですか(っ5mアイブラ)」
カートンですらねぇしブチギレそうだった
— 海野seri@パチンコで5万2200円溶かしメス化したマゾ赤ちゃん (@pinball_love) 2019年5月28日
このツイートに関して「番号を言うべき」という反応が多かったようで、こんなツイートが続く。
https://t.co/yXBgIgafwl
なんでこの話、私が悪いみたいになってるの。
いろんな奴に引用RTされて「おかしい」みたいなこと言われてるし
だって考えてみ?商品名言う
↓
店員が分からない
↓
「番号で言ってください」と言われる
↓
煙草に番号なんてねぇだろ。商品名ぐらい覚えとけってなるでしょ
— 海野seri@パチンコで5万2200円溶かしメス化したマゾ赤ちゃん (@pinball_love) 2019年5月28日
個人的には「番号言ったほうが早いし親切なんじゃ」とは思うが、それはおいといて。
「効率的に働くためには相手の協力が不可欠なんだな」と痛感したので、それに関して記事を書きたい。
効率的に買い物すればWin-Winなのに
「アイブラ」と言われて「アイスブラストだ」と認識し、それがどんな見た目でどこに陳列されているかわかるコンビニ店員であれば、番号で注文しようがツイート主のように注文しようが、作業効率は変わらない。
居酒屋で「生ビールをジョッキで一杯ください」と言わずとも、「生」で事足りるのと同じだ。
ただ、居酒屋の「生」とはちがい、タバコにはいろんな種類がある。
コンビニの店員全員がすべてのタバコの銘柄と略称、陳列場所を把握していると想定するのは無理があるし、未成年や外国人の店員からすればなおさらハードルが高い。
店員としても、番号で注文されたほうが早く見つけられるだろう。
だから、ちゃちゃっと買い物を済ませるために、番号で注文するほうが、互いに「効率的」なのだ。
もし、たとえば視力の問題で番号が見えないなら、正式名称を言って空き箱を見せるくらいの協力はあってしかるべきだと思う。
でもツイート主の様子を見る限り、そういう協力をするつもりはまったくなく、「店員ならタバコをすべて把握していて当然」という姿勢のようだ。
それはまぁ個人の自由なのでどうこういうつもりはないが
「いいサービスを求めるのに非効率な作業求める人っているよね〜」と苦笑いしてしまう。
他人の仕事を増やしておきながら「効率」を求める矛盾
わたしは学生時代、全国チェーンの大衆居酒屋で働いていた。
GWや三連休前の金曜日、年末などは目が回るような忙しさで、店はパニック状態になる。
そんなとき、何度も何度も料理を催促してくる人や、「酒が遅い。店長を呼べ」と騒ぐ人、「待たされたんだから割引しろ」とレジでごねる人を何度も見た。
いや、忙しいって、見ればわかるじゃないですか。あんたが呼び止めてるいまこの時間に、こっちはほかのお客様の料理を運べるんですよ。わかります?
だったらせめて、空いた皿をよけて置いといてくれるとか、飲み物をまとめて注文するとか、ちょっとは協力してくれませんかね?
と、ずっと思っていた(早く飲みたい、食べたい気持ちはわかるけども)。
いろんな要求をしてくる人にかぎって、2分おきにバラバラで飲み物を注文したり、テーブルを散らかして後片付けの手間を増やしたりするのである。
いいサービスを要求するくせに、自分自身が相手に非効率な作業を強いている矛盾にまったく気づかない。
協力的なお客様は、飲み物をつくるのに時間がかかることを見越して早めにまとめて注文したり、お皿を重ねてよけておいてくれたりする。
デキる幹事様だと、各テーブルごとに注文を聞き、紙に書いてそれをわたしてくれる(本当にありがたい)。
そういうお客様ばかりであれば、こっちは可能なかぎり効率的に働ける。
お客様が協力的でいてくだされば、仕事というのはずいぶん快適に、効率的にこなせるのだ。
でも上限なく「サービス」を求めることが許されてしまう現状、多くの人は、「自分が相手の仕事の能率を下げている」という自覚がない。
そして同じ口で、「効率的に働くべきだ」なんて言うわけである。
なんだそれ。
ムダな作業を増やす人が多ければ仕事ははかどらない
半年前に公開されたものだが、とても印象に残っている記事がある。
それが、『ごみ収集の現場から眺めた日本社会』だ。
大東文化大学法学部准教授である藤井誠一郎氏が、9ヶ月ものあいだごみ収集作業員として働いた経験をつづっている。
質の高いごみ処理によって、清潔度の高い生活が保証される。それなのに、協力しない人は多い。
自分勝手なごみ出しをされると、道路を清掃するために通行人や車両を待たせざるをえなかったり、清掃車が燃えて廃車になり税金が投入されたり、なんてことが起こるそうだ。
水分が切られていないごみや、ごみ袋がしっかり結ばれていないごみなどは、とくに迷惑らしい。
住民がこうしたいい加減なごみ出しをしても、清掃職員はそれを寛大に受け止め黙々と作業を行っている。
しかしその結果、余計な手間暇や人員、機材が必要となってくる。
結局そのツケは住民が負担することに気づくべきである。
この負担とはおもに税金の話だろうが、コンビニでも居酒屋でも、基本は同じだ。
協力的じゃない人が余計な手間を増やせば、仕事の能率が下がり、いいサービスを受けることができなくなる。
ポジティブに言い換えれば、「顧客や利用者、関係者が協力的になることで、仕事の効率化を実現できる」のだ。
効率的な働き方実現には協力者が不可欠
「効率的に働く」という話になると、だいたいが「労働者目線」で語られる。
ミーティングの時間短縮、ほうれんそうのシステム化、裁量権の明示……などなど。
でも仕事は基本的に顧客ありきだから、効率化を語るのであれば、協力的な顧客もまた必要不可欠だ。
「相手に余計な作業をさせないで済むようにしよう」と、仕事の効率化に手を貸してくれる人がいなければ、どうにもならない。
作業を減らすためにコンビニのタバコに番号をふっても、客が「アイブラ8ミリカートン」と注文すれば水の泡。
最新鋭のごみ焼却場をつくっても、だれも分別しなければ効果は限定的。
いくら社内の働き方を見直したところで、納期の無茶振りをしたり、支払いをごねたりする客ばかりであれば、効率化もなにもない。
労働者視点からの「効率化」だけでなく、顧客視点からの「効率化への協力」もまた、浸透していってほしいと思う。
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
名前:雨宮紫苑
91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&
ハロプロとアニメが好きだけど、
著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)
ブログ:『雨宮の迷走ニュース』
Twitter:amamiya9901
(Photo:Chris Lott)