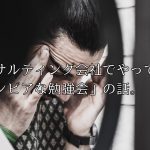仕事においては、「人を助ける」という行為は、美徳に見えますが、意外にもそれなりの思慮を必要とします。
場合によっては、せっかくの行為が、単なる自己満足になることも。
というのも、「助けないこと」と「助けること」を天秤にかけると、あえて助けないほうが良かった、という結果もかなりの頻度で起こるからです。
*
実は昔、私はお世話になった方から「勝手に人を助けるな、「助けてくれ」とはっきり言う人しか、助けないほうがいい」と言われたことがあります。
「どういうことですか?」と聞くと、彼は次のようなことを言いました。
まず、「勝手に人を助ける」とは、はっきりと助けを求められていないのに、何となくその人を助けてしまうこと。
いわゆる「善意」に近い。
しかし「善意」は問題を引き起こしやすい。
なぜか。
一つ目、当人が失敗して反省するという貴重な経験を奪う
命に関わる失敗はまずいですが、オフィスワークでそのようなことはまず、起きません。
むしろ、失敗から学ぶことは非常に多いので、失敗する前に助けてしまうと、いつまでたっても一人前になれません。
二つ目、自分からヘルプを出せない人に未来はない
ヘルプを自分から出すことは、社会人の必須の教養です。
部下には「助けてほしいときは「助けてくれ」とはっきり言うこと」と、徹底して教えましょう。
三つ目、勝手に助けると、感謝されるどころか、嫌な気持ちになるかもしれない
三番目については、不思議な気がしたので「なぜですか?」と私は突っ込んで聞きました。
すると彼は「求めてもいないのに、余計なことをするな」という人もいるし、助けると「助けるのが遅い」「助け方が悪い」「上から目線」とか、理不尽な人も少なくない、と言いました。
あるいは「助けてもらって当然」という態度をとる人もいます。
もちろん、理不尽な人はそれほど多くないでしょう。
しかし、「善意」は必ずしも、意図したとおりにならない、というのは、先輩の言うとおりだと思いました。
ですから私もよほどの事態ではない限り、
「「助けてくれ」とはっきり言う人しか、助けない」
という方針を採用しました。
困っていそうな人をどうする?
では、仕事で困っている人を見かけたらどうするのでしょう。
放っておけばいいのでしょうか?
そんな場合には、いくつか考慮すべきことがあります。
1.まずは目を離さない
一般的には「できない人ほど人に聞けない」という傾向にあります。
ですから、責任者という立場であれば、未熟な人間に対しては、ヘルプが出ていなくても、すぐに介入できるように(助けるとは違う)その人から目を離さないことは必要です。
結論から言うと、「できない人」は人に聞いていないわけではない。
実は、新人同士、できない人同士で聞き合っていて、上司や「できる人」には聞かないのである。
これは、ノーベル経済学賞を受賞したことで知られる経済学者、ジョージ・アカロフの著書の中で
「ややこしい訴訟に巻き込まれた、政府の役人についての観察」で紹介されている。
2.本当に困っていそうなら「助けを欲しているかどうか」を聴く
強調しておきますが、困っていても、助けを求めているかどうかは別の問題です。
助けを欲しているかどうかは必ず確認します。
3.助けを求められたら「何を助けたらよいか」を確認する
相手の求めてもいないことをやってしまうことを防ぐために、「何が助けになるのか」は必ず確認します。
実際には、直接助けるのではなく、相手の話を聴くだけでいいときも多々あります。
4.当人の力量を超えた事態であれば、介入したほうが良い場合も
仕事においては、冷静に見て、当人の力量で収拾がつかない事態になっているときには、「助ける」のではなく、「介入」します。
つまり、本人から責任を移管してしまいます。
ヘタに助けるよりも、「あなたはもう関わらなくていい」と宣言し、主導権をこちらに移すのです。
この場合、本人の意向は全く関係なくなります。
しかし、事態が大きくなってしまった場合は、中途半端に助けるくらいなら、介入してしまったほうが良いケースの方が多いです。
いずれにせよ「人助け」は慎重に
困っている人を見て見ぬふりをするのは、あまり褒められたことではありませんが、「何も考えずに助ける」行為も、よくありません。
小学校では「困っているお友達は助けてあげましょう」と指導されるかもしれませんが、大人の世界ではもう少し複雑で、思慮が必要な行為なのです。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
Photo:J W