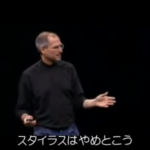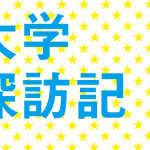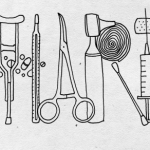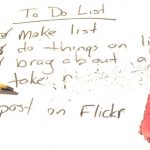仕事が遅いんです…という悩みを聞く。なぜ遅いのかを聞くと、どうも本人は「能力不足」と思っているらしい。
仕事が遅いんです…という悩みを聞く。なぜ遅いのかを聞くと、どうも本人は「能力不足」と思っているらしい。
とんでもない。
能力不足なのではなく、仕事を早く終わらせる行動をとっていないだけだ。能力は仕事の成果の上限を決めるが、仕事のスピードに対する影響は小さい。
仕事のスピードを決めるのは、なんでもない習慣である。きちんと実行すれば、仕事の時間を半分…は言いすぎだが、2/3にはできる。
1.気の散るものを回りにおかない。
家では仕事(勉強)できない、という人も多いが、それは気が散るものが多いからだ。集中したいときは、できればネット環境も切るほうがよい。余計なことをしていると、すぐに時間が経ってしまう。メールを見るな。スマホをさわるな。
カフェでの仕事が捗るのは、余計なものがないからだ。
2.眠い時に無理して仕事しない。仮眠を取れ。
眠い時の仕事のスピードは最低である。仮眠をとっても良い。少し寝た後の仕事のスピードは劇的に違う。もちろん基本として、早く寝ること。
3.タイムリミットを設定せよ。そして聞け。
ある程度悩んでできないものは、いったん捨てる。そして人にヒントをもらうと劇的にスピードが変化する。
自分で調べるのも良いが、聞いたほうがはるかに早い。ただし、メモを取って同じことを2度聞かないように努力すること。
4.仕事の目的を書き出せ
取り掛かる前に目的を書き出せ。「なんとなく」わかっている程度ではダメで、言葉にしろ。仕事は余計な品質を追求しているヒマはなく、目的のために大事なことをする時間である。
5.真似をしろ。ノウハウもらえ。
仕事の早い人の真似をしろ。絶対に素晴らしいノウハウを持っている。仕事ができる人と仲良くすること。
例えば報告書が早い人がいたが、彼は今まで書いた報告書をパターン化、テンプレート化していた。ほとんどの仕事は毎日代わり映えしないのだからこれで十分だ、と彼はいっていた。
6.ツールに習熟しろ
開発者であれば、テキストエディタやエクセルの使い方に習熟しなければいけない。文筆家であればタイピングのスピードは重要だ。営業であれば顧客DBを知り尽くす。ツールの使い方に習熟すればそれだけ仕事早くなる。
7.早くおらわせて遊びに行け
早くやろうと思う動機付けは重要だ。遊べ、家族と過ごせ。友達やパートナーと会う。飲み会に行っても、勉強会に行ってもよい。夜に予定を入れよう。
ほとんどの仕事に才能は必要ない。必要なのは工夫だけだ。
ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の
最新資料を公開しました。
AIが“書く”を担う。
人が“考える”に集中できるライティングサービス
・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします)
・【大学探訪記】を始めました。
「研究が楽しい」「研究成果を知ってほしい」「スタートアップを立ち上げた」
という学部生、大学院生、研究者、スタートアップの方は、ぜひ blogあっとtinect.jp までご連絡下さい。卒論、修論も歓迎です。ご希望があれば、当ブログでも紹介したいと思います。
【大学探訪記 Vol.10】池の水を少し汲めば、その池に住む生物がわかる。そんな魔法のような話、あるんでしょうか?
【大学探訪記 Vol.9】1年に13万件ある日経新聞の記事を、人工知能の一分野「機械学習」によって分類・分析する。
【大学探訪記 Vol.8】雲とチリの相互作用を、スーパーコンピュータで再現する。
・ブログが本になりました。
(Photo:Freaktography)