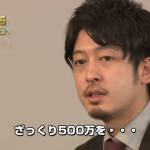年末となり、そろそろ真剣に就職活動について考えている学生の方が増えているようである。
そして、学生たちに話を聴くと、特に見栄えのする学歴を持っている学生ほど「大手に行きたい」という志向が強いと感じる。
たしかに、マイナビの調査によれば、近年では「大手」で、かつ「安定している会社」を志望する学生が増えているという
(2017年卒マイナビ大学生就職意識調査:http://www.mynavi.jp/news/2016/04/post_11203.html)。
何が正解かわからない今、少しでも安定を求める気持ちは分からないでもない。
だが、よくよく学生たちに突っ込んで話を聴くと、本当に「大きな会社」に行ってしまってよいのかどうか彼らも迷っていることがよくわかる。
彼らとて「単に大きい会社にいければ良い」とは思っておらず、彼らなりに真剣に考えている。
それでも「大手」という人が多いのは、結局のところ、小さいけど良い会社というのが、どういう会社なのかわかりづらい上、大きい会社に比べて質のばらつきが大きいからではないだろうか。
「良い会社」と思って入ったら、とんでもないダメ企業だったということも決して少なくないのである。
では「小さいけど良い会社」かどうかは何を見ればよいのだろう。
オススメは、ビジネスの良し悪しよりも、マネジメントの良し悪しを見ることだ。ビジネスの業績は移ろいやすく、良い会社であっても浮き沈みはある。
逆にマネジメントの良し悪しは経営陣の能力に大きく影響されるため、マネジメントの優れた会社は、良い会社である可能性が高い。
そして、マネジメントの良し悪しは以下のような部分に現れる。
1.人を増やすことに慎重である。
一気に人を増やしている会社は、一見調子が良さそうに見えるのだが、じつは微妙だ。理由は2つある。
まず、人をきちんと育てるには非常に時間とお金がかかること。
「小さい会社」ほど人を吟味して採用しなければならないにも関わらず、それに反して大量採用をしている会社は、「とりあえず仕事をやらせてみて、生き残ったやつだけ残れば良い」という考え方になりがちである。
そして、2つめはそもそも、成長性の高い知識集約型産業は、それほど人を多く必要としない。むしろ人が多ければ多いほど、「規模の不経済」が働きやすく、その会社は非効率になるからだ。
したがって、会社を1つの「プロジェクト」と見れば、規模はできるだけ小さく抑えたほうが効率的である。
ソフトウェアにおいて、プロジェクトが大きくなるほど、より大きなグループ間のコーディネーションが必要になる。大きなグループになるほど、より多くのコミュニケーションが必要になる。(Brooks 1995)。その結果、プロジェクトの規模が増えるにつれて、さまざまな人々のコミュニケーションパス(経路)は、プロジェクトの人数の2乗の関数で増えることになる。(中略)
コミュニケーションパスが(他の幾つかの要因とともに)急激に増加する場合、プロジェクトの工数もプロジェクトの規模がふえるにつれて急激に増加する。これは「規模の不経済」として知られている。*1
昔ながらのピラミッド型の上意下達組織であれば、「規模の不経済」は起きづらい。
だがソフトウェアサービスなどの「知識労働」が用いるチーム型組織であれば、規模の不経済は大きな問題となる。
「良い会社」は、常に「いかに最小限の人数で、最大のアウトプットを得るか」を考えている。真に有能な人はそれほど多くない。急に人を増やしている会社はほとんどの場合「水ぶくれ」である。
2.「売上を依存している取引先」を持たない。
多くの企業は「上位2割の取引先が、8割の売上を占める」というパレートの法則が成り立っている。こう言った世界では利益の殆どは上位2割の企業から得られる。
だが、その代償として「売上を依存している取引先」の存在を許してしまう。そして、そういった会社から無理を言われれば「下請けの悲哀」を味わうことになる。
これは残念ながら「良い会社」ではない。
真に「良い会社」は、規模が小さくても、僅かな取引先に売上を依存したりはしない。どの会社にも「別にいつ切ってくれてもいいですよ」と言えることで、結果として付き合いは健全になる。
むしろ良い会社は常に、「ウチと付き合いたいなら、うちの条件を飲んでください」と強い態度に出ている。したがって「お客様は神様」ではなく「お客様はパートナー」である。
入社前に説明会などで聴くことができるなら「売上高」と「取引社数」と「上位10社の売上高」などを聞いておこう。偏りが大きければよくない会社、逆に平均化されていればいるほど、良い会社である。
3.営業を担う人が最小限である
ピーター・ドラッカーはかつて「会社がやらなくてはいけないことはマーケティングとイノベーションのみ」*2と言い、さらに「マーケティングの目的は、販売を最小限にすることである」と述べた。
つまり「販売」を主たる担当とする営業は「最小限」とすべきである。
実際、営業はプロフィットセンターなどではない。究極を言ってしまえば「コスト」であり、省くべきものである。
理想的には、企業活動は「企業に問い合わせが来る」⇒「問い合わせに答えてサービスを提供する」で済んでしまうのだ。そこに「販売」の入る余地はない。
また、営業を減らせばその分、「サービス・プロダクトの質を上げる」ことにリソースを投入でき、ますます競争力が上がる。
そう言う意味では、「マーケティング」がうまく、かつ販売活動を最小限にできる「ストックビジネス」を行っている企業は理想的だ。
企業規模が小さくともPRがうまく名前が知られており、営業をほとんどせずともストックビジネスを行えている会社は、企業規模が大きくても強い営業でなんとか会社を回してる会社よりもはるかに健全である。
説明会では「営業の人数」を必ず聞いておこう。
4.「成果をあげること」と同じくらい「学習すること」に重きをおいている。
多くの人が「成果をあげること」のほうが「学習すること」よりも遥かに難しいと思っている。
だが現実は逆だ。実は会社において「学習すること」のほうが、遥かに難しい。
なぜなら、それは差し迫った要求ではないからだ。
「本を読んで、考えたことをアウトプットすること」
「プロジェクトのレビューをし、体系的にノウハウをまとめること」
「社内で知識の共有を行うこと」
「新しい試みをし、レポートをまとめて発表すること」
「敢えて非効率な方法で実験し、より良い方法を探ること」
こう言った活動は、つねに「会社は学校ではない」「早く成果をあげろ」という脅迫により劣後順位をつけがちである。その圧力に耐えて、「組織的に学習を続けていること」こそ、良い会社の証である。
こう言うと大抵「仕事を経験することが学習だ」という反論をする人がいるが、それは間違っている。
経験はそのままでは学習にならない。経験したことを振り返り、体系的にまとめて再現できるようにしなければ、学習したとは言えないのである。
長期的に見れば、上に述べたような学習活動が無ければ企業の知識は古いままとなり、競争力を保つことはできない。
以前「知的好奇心は会社にとって邪魔である」と述べた経営者がいたが、邪魔どころか、知的好奇心を充足させることすらできない会社においては、新しい試みは行われないし、有能な人物を引きつけることもできないのである。
「会社として、「組織的な学習」をどのように行っていますか。」と聞いてみよう。良い会社であれば、必ず気の利いた返事が返ってくる。
ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の
最新資料を公開しました。
AIが“書く”を担う。
人が“考える”に集中できるライティングサービス
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
*1
*2