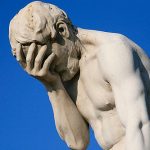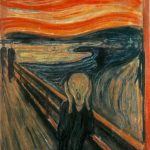間違いを指摘すると、大抵の人は「すみません」と訂正する。
だから「それ、知らなかったです」と言われたとき、珍しいな、と思った。
知らなかったとしても「知らなかった」と相手に伝える人はあまりいない。
なぜなら、まず間違いは訂正するほかないこと。
さらに、「それくらいのことは知っておいてほしい」と思われてしまったり、「教えていないほうが悪いと言いたいのか」と不快にさせてしまったりと、デメリットのほうが大きいように感じられるからだろう。
世渡り上手な人は、そのあたりをうまくやる。
でも思ったことをそのまま表明してしまう人も中にはいる。
たぶん、何も考えずにただ「知らなかった」と言っているだけだと思うのだが、言われる側としては珍しいと思い、つい考えてしまうのである。
正直なところ、「さすがに常識の範疇だろう」と思うようなこともあって、何でもかんでも知らないでは済まされないと思う部分もある。
でも「知らない」ということを、すべてその人の責任にしてしまってよいのだろうか。
*
もう随分前のことになるけれど、小学生になったばかりの頃の記憶が1つ残っている。
それは、「休め、気をつけ、前へならえ」の号令を初めて聞いたときのことだ。入学式だったと思う。
私以外の全員が、サッと動いた。号令通りに。でも私は動けなかった。知らなかったからだ。
たぶん、他のみんなは保育園や幼稚園で教わっていたのだろう。私の通っていた幼稚園では、そのような号令はなかったから、知らなかった。知らないと、動けない。
それでも学校では、全員が知っているという前提で号令がかけられていた。ちゃんと教えてから号令をかけてほしい、と思った。そんなの、知らないよ、って。
「知る」というのは、不可逆的なもので、一度知ったことについて、知らなかった状態に戻すことはできない。
だからこそ、一度知ってしまったことに対して、知らなかったときの状態を思い返すことは難しい。あたかも最初から知っていたかのような錯覚に陥る。
その傾向は知ってから時が経つほどに強くなると思う。でも、考えてみれば誰だって最初は知らなかったはずなのだ。
私は人事と言う立場上、毎月中途入社社員の研修をしているのだが、1つ失敗したと反省していることがある。
それは「お手洗いの場所」を伝えていなかったことだ。
研修中は休憩を挟みながら進んでいくから、休憩のときにお手洗いを案内する。しかし、職場は研修とは別のフロアにあり、当然お手洗いも別の場所にある。その場所を伝えることなく配属先へ案内してしまっていたのだ。
幸いにも、早い段階で「知らなかった」ことを伝えてくれた人がいたことによって気づかされ、その後は気をつけて伝えるようにしているのだが、自分が当たり前のように使っている場所なだけに、盲点になっていたのである。
会社では、新卒であれ中途であれ、新入社員は立場上「知らない」ということを言いづらい。
「知らない側が悪い」という雰囲気を感じ取ってしまうからだろうか。新入社員は一番知らないことが多いはずなのに、一番「知らない」と言いづらいという難しい立場にある。
だからこそ、先輩社員は相手の「知らない可能性」に敏感であるべきだと、最近強く思う。
「別にこちらから気を遣ってあげなくても、学びたい人は自分から積極的に学んでいくし、質問すればいいだけのことではないか」という意見もあるとは思う。
でも、最初のちょっとした気遣いで、お互いが気持ちよく働ける環境になるならば、それは積極的にやっていったほうがいいのではないだろうか。
知らない可能性に敏感になることは、たぶんそんなに難しいことではない。知らない人が知らないと表明することに比べたら、たいした負荷ではないだろう。
それに、知らない相手には、いつか誰かが教えてあげなければならないのだ。それなら先に教えてあげたほうが、そしてそのタイミングは早いほうがいいに決まっている。
もしそうする余裕がないのだとしたら、それはきっと自分に余裕がなさすぎるのだ。相手の「知らない可能性」に敏感になれるだけの余裕は、せめて確保しておきたい。
ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>
第6回 地方創生×事業再生
再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】
ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。
当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。
【今回のトーク概要】
- 0. オープニング(5分)
自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)
保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)
再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)
経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)
「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)
数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)
経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”
【ゲスト】
鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏
ExePro Partner代表 経営コンサルタント
兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。
高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。
卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。
株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。
その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。
現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。
【パーソナリティ】
倉増 京平(くらまし きょうへい)
ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事
顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。
コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。
ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。
(2025/7/14更新)
【著者プロフィール】
名前: きゅうり(矢野 友理)
2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。
【著書】
「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)
[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」
- 矢野 友理,STUDY HACKER(協力)
- マイナビ出版
- 価格¥385(2025/07/19 01:35時点)
- 発売日2015/02/27
- 商品ランキング136,190位
「LGBTのBです」(総合科学出版、2017/7/10発売)
LGBTのBです
- きゅうり
- 総合科学出版
- 価格¥1,150(2025/07/18 16:44時点)
- 発売日2017/07/10
- 商品ランキング428,636位
(Photo:Alex Proimos)



![[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」](https://m.media-amazon.com/images/I/51azOIVRtVL._SL75_.jpg)