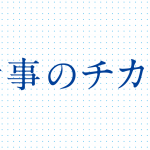「最近なんでこんなに忙しくなったんですかね?」という話題が会社を問わず頻繁に持ち上がる。
理由は2つだ。
・「働いた時間」ではなく、「成果」が問われている
・指示されて動くわけではない人、自分で仕事を組み立てなければならない人が増えている
なぜそう言えるのか。
成果を出そうとすれば、常に時間が足りないからだ。
成果とは作業と違い、本質的に「いつ終わる」かが不確定だ。だからできるだけ行動を増やして、「その中のどれかが当たる」ことを期待して動く。だから、成果をあげるには、試しながらやるしかない。
だから、成果にコミットする、ということは同時並行でたくさん仕事を進めなくてはならない、ということと同義である。
よく「失敗しろ」「失敗した方が良い」と言われる。
ユニクロの柳井氏は「一勝九敗」という本を出しているが、それは「10回のうち1回勝てば良い」という意味ではなく、「とりあえず10戦せよ。話はそれからだ」という意味だ。
失敗した方が良い、というよりは「失敗が必然」なのである。
働いた量ではなく質で判断される、知識労働者の働き方は、「時間あるかぎり働く」という考え方 と深く結びついている。例えば
「あと何時間働けば、バズる記事がかけるのか?」
「あと何時間作業すれば、価値あるwebサービスが作れるのか?」
「あとどのくらい頑張れば、目標達成できるのか?」
といったことは誰もわからない。わからないので「成果が出るまで働く」のだ。知識労働者は、時間に対して報酬を受け取る現在の法制度と、ここが根本的に相容れない。
だから、その人が「仕事ができる人かどうか」を判断する材料の1つに、「時間に対する考え方」がある。なぜならそれは、成果に対する姿勢を色濃く反映するからだ。
・報酬は「作業」に対するものであり、労働時間が早く過ぎて欲しいと思っている人は、「ブルーカラー、ホワイトカラー」である。
・報酬は「成果」に対するものであり、時間がいくらあっても足りないと感じる人は、「知識労働者」である。
これは、多くの人がご存知の通り、どの会社に行っても普遍的な事実だ。そして、「知識労働者」となった人が、大きな報酬を受け取り、知識労働者を集めた会社が勝利するのは、現在の必然的流れになっている。
消費者がレベルの高い商品、サービスを求める限り、それは終わらない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします))
・筆者Twitterアカウントhttps://twitter.com/Books_Apps
・ブログが本になりました。