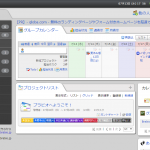技能、またはスキルと呼んでも良いが、あるワザを身につけるためにはそれなりの努力が必要だ。しかも、困ったことに努力したからといって必ず身につくものでもない。
語学やプログラミング、彫刻、演奏など数多のスキルを身につけたいと願う人は多いが、殆どの場合、目指す領域にたどり着ける人は非常に少ないのは、そのためだ。
実際、スキルの習得は、かなり注意深く行わなければ、無駄となってしまう。さらに、数多くのスキルを要求される「仕事」の領域においては、技能の習得のスピードが、仕事の成否を分けることもある。
したがって技能そのものの習得以前に、「どのように技能を習得するか」を学ぶこともまた重要である。
ではその方法とは何か。これについては以前、様々なハイスキルの保持者にインタビューをした時の資料が役に立つかもしれない。
実は、多くのハイスキルの保持者は、かなり共通の体験をしている。
例えばあるプログラマーが技能の習得を実現した時のことと、あるスポーツ選手が技能を習得した時の環境は酷似していた。そして、その環境とは以下のものだった。
1、良き指導者がいる
断っておくが、独学が悪いわけではない。独学でスキルを身につける方法も存在する。なぜなら、練習方法は調べればすぐにわかるからだ。webにはそういったものがいくらでも存在している。
だが問題は「その中で自分に適した練習方法がどれなのか」「今の状況に適した練習方法が何か」がわからないことだ。独学が難しいのは、そのためである。
例えば「腹筋」「トレーニング」で検索してみると良い。すぐに無数の腹筋のやり方が見つかるだろう。だが、自分に合っているトレーニングの方法がどれであるか分かる人は殆どいないはずだ。
従って、良い指導者の真のメリットは「自分にとって適切な練習方法を教えてもらえる」ことにある。逆に画一的な練習の指導であれば教えてもらう価値は半減してしまう。
2、アウトプットの場所がある
習得した技能は、何らかのアウトプットを伴わなければ良いフィードバックを受けることができない。
裏を返せば、自分の技能に対しての何らかの指摘がない状態では、到底上達は見込めない、ということでもある。
語学であれば実際にネイティブスピーカーと話したり、試験を受けたりすること、プログラミングであればソフトウェアを制作し、ソースコードをレビューされたり、販売したりすること、スポーツであれば試合をすることなどだ。
なお、練習を中心に据えてはいけない。練習はあくまでもある特定の課題に対して集中して改善に取り組むためのものだ。技能全般の向上のカギは実践である。
3、明確な目標を設定する
明確で、達成可能だと思える目標を持つことはモチベーションに大きく貢献する。
もちろん試合で勝つなど、アウトプットが評価されることも重要なのだが、日々の鍛錬の中でモチベーションにもっとも重要なのは、上達した実感である。そして、上達した実感は、目標の達成により得られるものだ。
実際、技能の習得に至る道筋がしっかりと決まっていれば、努力はそれほど難しくない。教え子に対して上達のステップを細分化し、達成感を得る頻度をふやすことは、有能なコーチであれば誰しもがやっていることだ。
4、鍛錬の時間を確保する
米国の著名なコラムニスト、マルコム・グラッドウェル氏は著書※1の中で、技術者、スポーツ選手、芸術家などにインタビューを行い、達人になるには「1万時間必要」という説を発表した。
1万時間という単位に根拠があるかどうかは議論の余地があるが「鍛錬の時間が必要」という部分において異論のある方はほとんどいないだろう。単純に言えば、毎日目の前に流れてくるものをこなしているだけでは技能を習得することはできない。
「鍛錬を行うのに必要な時間を確保する」という能動的な行動が必要だ。
余談だが、知人で「社会人になってから、日本にいながら英語を習得した」人物は、ほぼ例外なく毎日1時間程度の鍛錬を数年間、繰り返している。
5、競争する
誰を、何を競争相手とするかによって、技能の方向性は大きく変わってくる。逆に言えば、一定のレベルに達したら、競争する相手により技能の特化の方向が見える。これが「強みを見つける」という行為だ。
したがって趣味程度なら競争は不要だが、「使える技能」となると、競争に晒されなければならない。
技能はアップデートが必要とされる。そして、最新の技能は定式化されていないことがほとんどであり、アップデートをするには他者との競争を通じて行う他はない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。