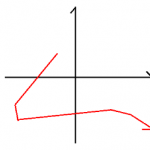どうも、Books&Apps編集部です。
Books&Apps(今更ですがブックス・アンド・アップスって読みます)には、「知識労働者」という言葉が多く登場します。
当たり前のように使っているこの言葉ですが、「知識労働者」って一体何なんでしょうか。何となくドラッカーあたりが提唱していそうな言葉だ、というところまでは見当がつきます。でも、言葉の説明をしろと言われたら、結構難しいですよね。
最近では「21世紀は知識労働の時代となった。知識労働者にならなければ生き残れないでしょう」なんて不安ばかりを煽って、その意味をしっかり説明してくれない記事を見かけたりします。
確かにそうかもしれないけれど、自分の頭で理解しないうちに、”何となくそこにある不安”に踊らされるのも嫌だなー、と。そこで今日は、改めて「知識労働」に関するコラムを振り返りたいと思います。
そもそも「知識労働者」って何?
知識労働を定義するうえで、頻繁に対比される肉体労働。肉体労働はわかりやすい。その字面の通り、体を使った労働です。当たり前ですが、こなせる仕事量は肉体の限界に比例します。
人類の歴史を紐解けば、その大半は肉体を使った役務提供がほとんどです。そう、つい最近までは、肉体労働者中心の世界でした。
知識労働の5つの「常識」
統計局のデータを見ると、1950年当時、労働人口の約半数は農林水産業に従事していた。さらに、工業への従事者は全体の4分の1。
従って、全体の75%の労働者は肉体労働者だった。実際、つい70年前には職業は親から子へ受け継がれ、多くの人は、毎日の仕事をこなすことに対して疑問を持つことは殆どなかった。
ところが2005年になると、この割合は大きく変化する。農林水産業への従事者は全体のわずか5%に過ぎず、工業への従事者も3割程度にとどまる。全体の7割近くの労働者はサービス業、専門技術者などの「知識労働者」だ。
「肉体労働者」と「知識労働者」の割合は逆転している。おそらく2014年現在では更に知識労働者の割合は増えていることだろう。
事実ベースとして、知識労働者が増えているんですね。
しかし、残念ながら「知識労働」は新しい労働形態であり、人類の文明化以来6000年にわたって続けられてきた「肉体労働」のノウハウの集積度合いに比べ、我々が知っていることはあまりにも少ない。
(中略)
では、われわれが「知識労働者」として、幸せに働き続けるには、何が必要なのか。
何が必要なんでしょう!?この続きは是非本稿を読んでみてください。
知識労働社会に求められるリーダー像とは?
我々一人ひとりが知識労働者となれば、当然ながら新たなリーダーシップの形が求められてきます。
知識を扱う現代のリーダーと、労働力を扱う旧来のリーダーの6つのちがい
単純にチカラが強く、権威によって人を従わせることができるだけではもはやリーダーの役割は果たせない。
「知識」を扱う現代のリーダーの役割はもっと複雑で、困難だ。成し遂げなければならないことを定め、それに対するアイデアを持つ人を使い、 全体の方向をまとめてアウトプットし、成果をあげさせる人がリーダーだからだ。
権力者がリーダーというわけではなく、声の大きい人がリーダーというわけでもない。「知識」を扱うことの本質を知っている人が、現代におけるリーダーなのだ。
知識を扱うことのできるリーダーであるかどうかはその人の行動を見れば分かる。
もちろんリーダーのフリは簡単にできるが、その人が現代のリーダーかどうか、旧来のリーダーとの差があまりにも大きいので、だれにでもわかる。
それは主に以下のようなことにおいてである。
こちらも気になる6つの違いは、是非本コラムを読んでみてください。
個人的には、3つ目の「現代のリーダーは、意見が違うことを重視し、旧来のリーダーは意見が揃うことを重視する」が、言うは易し・行うは難しなんじゃないかと感じます。それにしても、現代のリーダーって大変だな…。
知識労働社会に求められる組織像とは?
最後は経営者の方に送るコラムです。
知識労働者にとっては、「組織の価値観」など障害にすぎない
経営者にとってみれば、「価値観の統一された集団」を扱うほうが経営ははるかに楽である。
しかし、「知識労働者」にとってみれば、そういったことは瑣末なことにすぎない。率直に言えば、「どうでもいい話」なのである。
(中略)
「知識労働者」は、本質的に自分の属する組織の業績に興味はない。また、そういった業績に興味を持つよりも、専門分野に真剣に取り組んだほうが、優れた仕事ができる。
高度な仕事を労働者に求めれば求めるほど、「企業の都合」にその仕事内容を合わせるわけには行かなくなる。「知識」というものは、その応用分野が広ければ広いほど価値があるからだ。そこにジレンマが存在する。
「知識労働」を目指す企業であれば、そのバランスをどのように取っていくのか、創意工夫が求められる。
これまで推奨されていた”価値観の統一”をバッサリ切っていますね。『ビジョナリー・カンパニー』を信奉していた私にとっては、頭をその本でガツンと殴られるくらい衝撃的なバッサリ感です。
ではどうやって組織を構築すればいいのかー。
残念ながら、本コラムからその答えを得ることはできません。というより、その答えを持っている組織って、まだ無いんじゃないでしょうか。
Books&Appsはこれからもその問いを世間に投げ続け、一緒に考えていければと思います。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。