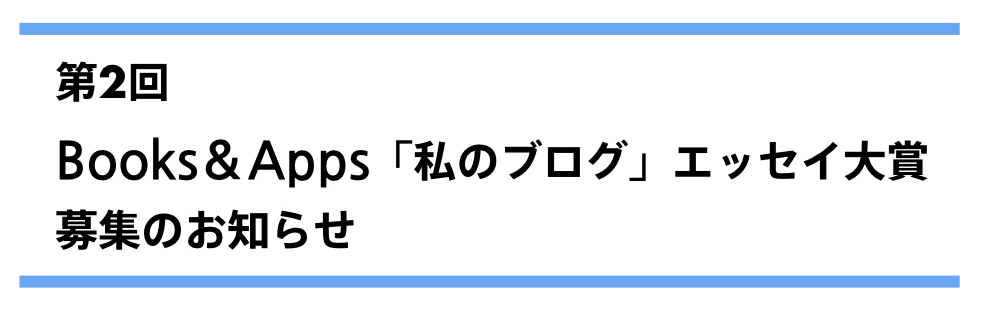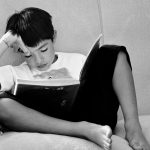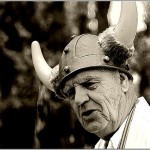会議をうまく運営するのは難しい。
会議にはその会社の「時間に関する考え方」が色濃く現れるので、だめな会社は会議を見ればひと目で分かる。会議が下手くそな会社は決まって、生産性が低いのだ。
例えば、以前書いた記事の中でも触れたが、会議鉄則の1つとして、会議には「発言する人」だけを参加させたほうが良い、と言うものがある。
「集団を賢くするのは何か」を明らかにするため、MITのアレックス・ペントランドは、数百の小グループを対象に、IQテストを行うなどして、「集団的知性」を検証した。*1
賢い集団と、愚かな集団にどのような違いがあるのか?組織の中で働くことの多い我々にとって、興味が尽きない分野だろう。そして、この実験結果は意外なものだった。
実験によれば、会社で経営者が気にしているような要素、
- 団結力
- モチベーション
- 満足度
などについては、統計学的に有意な効果はなかった。集団の知性を予測するのに最も役立つ要素は、「会話の参加者が平等に発言しているか」だった。
少数の人物が会話を支配しているグループは、皆が発言しているグループよりも集団的知性が低かった。
発言しない人を会議に参加させると、その人の時間を食いつぶすだけではなく、会議そのものの生産性も下がる。役立たずを出席させるくらいなら、出席させないほうが断然マシなのだ。
だが、一方で「意味のない会議に、上司が部下を付き合わせる」という逆のパターンもある。
部下はこう思っている。
「この会議、いつも無駄なんだよな……」
「何でわたしが参加しているんだろう?」
「この時間、苦痛なんだよな。早く終わらないかな。」
こう言った会議の特徴は「惰性で開催されている」という点にある。
以前に品質マネジメントのコンサルティングを行った時のことだ。プロジェクトを開始するにあたって、我々はいつも、公式、非公式の「会議一覧」を顧客に提出してもらっていた。
すると、せいぜい100名程度の所帯の会社であっても、大抵は10から20、場合によってはそれ以上の会議があることがわかる。
全体定例、部署の定例、チームの定例、リーダー会議、品質改善会議、在庫削減プロジェクトの会議……
あまりにも会議が多いので、「この会議、必須なんですか?」と聞くと、誰からも返事が返ってこない。議事を予め定めているわけでもなく、参加者を吟味しているわけでもなく、アウトプットも明確ではない、そんな会議が驚くほど多数見つかるのだった。
多くの「必須ではない会議」の中身はこうだ。
まず議長である組織長、もしくはリーダークラスが、各人から報告を求める。そこには一応数字もあるので、コメントを付けて報告される。
たまに議長がおかしな数字に対してツッコミを入れる。
「この数字、おかしくないかね。」
「何で今月の数字は未達なんだ。」
報告者は理由を述べる。
「は、カクカクシカジカの理由がございまして……現在対策取っている最中です。」
上司は「そうか」と言い、次の人が発表をする。
そして一通り、各部署からの報告が終わったあと、議長から議題が投げかけられる。
例えばこんな具合だ。
「今回のディスカッションテーマは、今期の人事評価項目についてだ。」
「最近発生した大きなクレームの件だが」
「新規開拓のペースが落ちている。なんとかしたい。」
ようやくここで活発なディスカッション……と思いきや、誰も意見を述べない。アイデアがないのか、お互いを牽制しているのかわからないが、とにかく意見は出ない。
時間が5分ほど経つと、ようやくその中で「できる人」と目されている人が発言する。
「◯◯だと思います。」
一人が発言すると、数名がポツリ、ポツリと発言するが、大した意見は出ない。
そしてまた沈黙が訪れる。
最終的に組織長が「では、その案で異論はないか?」と聞くと、皆がなんとなく同意して、会議は終わる。
*****
Googleの元CEOだった、エリック・シュミットはこんなことを述べている。*2
会議の出席者全員に「イエス」と言わせても、全員が同意したとは限らない。あなたの部下がボブルヘッド(イエスマンの意)だらけであることを意味するだけだ。
コンセンサス・ベース”の意思決定を目指すリーダーは多いが、コンセンサスの意味を根本的に誤解している。
(中略)
コンセンサスとは、全員にイエスと言わせることではなく、会社にとって最適解を共に考え、その下に結集することなのだ。
最適解に到達するためには、意見の対立が不可欠だ。オープンな雰囲気の下、出席者が自分の意見や反対意見を述べなければならない。なぜならすべての選択肢を率直に議論しなければ、全員が納得し、結論を支持することはありえないからだ。
納得していない者はボブルヘッド人形のように頷いておきながら、部屋を出たとたんに自分の好きなように行動する。だから真のコンセンサスに到達するには、反対意見が必要だ。
本質的に、会議というものはアイデアに対して賛成、反対がぶつかるディスカッションをすることに意味がある。
逆に言えば、アイデアも出ない、ディスカッションもない会議は廃止して良いということだ。
だからもちろん、参加者が「私たちは参加する必要が無いのでは?」と思うような会議は開催する必要がない。
反対意見を考えるのは骨が折れるし、下手な意見を言えば、上司や組織長に「無能である」とみなされてしまうリスクもあるから、結局「黙っていたほうが得策だ」となるからだ。
会議は「本気の人同士」でやるからこそ、意味がある。
ピーター・ドラッカーは会議について、あるエピソードを紹介している。*3
スローンは、GM(ゼネラル・モーターズ)の最高レベルの会議では、
「それではこの決定に関しては、意見が完全に一致していると了解してよろしいか」
と聞き、出席者全員が頷くときには、
「それでは、この問題について、異なる見解を引き出し、この決定がいかなる意味をもつかについて、もっと理解するための時間が必要と思われるので、いつものように更に検討することを提案したい」
といったそうである。
ディスカッションのためには参加者全員の協力と、なによりも会議を開催する人間の強い目的意識が不可欠だ。
ある経営者が言っていた。
「ディスカッションというものは、勝ち負けではない。全員で知恵を出し合うことで、今とは別の場所に行くためのものだ。そうでなければ、ディスカッションをする意味はない。」
まったく、そのとおりである。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
*1
*2
*3