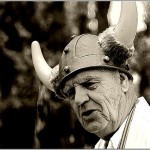今「営業」といえば「売り込まないこと」が主流になりつつある。
聴いて、相談に乗って、オススメするスタイルの営業だ。
それらは「コンサルティング営業」と名付けられ、確かに昔のど根性営業に比べてスマートに商売をやっているように見える。
しかし、世の中には実は「ゴリゴリ売り込まれたい人」もたくさんいるのだ。
過去に生命保険の営業、いわゆる生保レディをやっていて、今は独立して会社をやっている女性から話を聴いた。
初対面の方であったので「今は、どういった仕事をなさっているのですか」とお聞きしたところ、
「営業部隊の強化をするサービスをしています」
とのこと。
私の経験に照らしても「営業強化をしたい」という経営者はたしかに多かった。マーケットがあるのだろう。
そこで「具体的には、どのような感じのご依頼が多いのですか?」と伺った。
するとその方は苦笑しながら、
「生保レディたちのような営業部隊を作りたい、という経営者が多いです」
と言った。
「なるほど、確かに強い営業のイメージがありますが。」
「そうですね。」とその女性は言った。
「でも、ほとんどの経営者は生命保険の営業を迷惑だ、って思っているのにですよ。」
言われてみればそうかもしれない。たしかに、売り込みをかけてくる営業をそっけなく扱う経営者は多い。
「ということは、皆さん「自分は迷惑に思っているタイプの営業が自社に欲しい」ってことですよね、可笑しいですよね。」とその方は言った。
生保レディ時代は「目標の数字まであとわずか」という時には、待ち伏せしたり、経営者の携帯電話の番号を社員から聞き出し、直接「なんとか買ってください」と1日に何度も懇願したり、苦労したという。
「生命保険という商品は、ニーズもウオンツもないんです。おまけにどこの会社の商品も同じようなもので、しかも複雑でわかりにくい。それをなんとか売り込むわけですから、もうメチャクチャやらないと売れないんです。」
と、その方は言った。
その方の話を聞き、私は思った。
経営者たちは、売り込みを迷惑に思いつつも、実は「売り込まれている状況」を密かに楽しんでいる可能性もあるのではないだろうか、と。
そこで、過去に不動産営業をやっていた方にも話を伺った。彼は個人用の投資物件を扱う会社に7年間在籍し、ひたすらテレアポでお客さんを開拓してきた方だ。
「1日に、同じ人に3回電話をかけるんですよ。」
「いい加減にしろ、って言われません?」
「めちゃめちゃ言われます。でも電話をかけ続けるんです。すると、中には「アンタもしつこいねぇ」と、根負けして話を聞いてくれる人もいる。」
「ほう」
「口では「要らない」って言っている人でも、中には実は興味ある人がたくさんいるんです。お金の話ですからね。で、一度話を聴いてくれるようになったら、そんなひどい扱いはされない。営業って、ホントに熱意なんですよ。」
「厳しい仕事ですね」
「でも、そういう営業って、実はとても面白いんですよ。言い方悪いですけど「人間として見られていない状態」から「信頼してお金を預けてもらう」までのプロセスが、すごいやりがいがあるんです。実際、売り込まれたい人もたくさんいるんですよ。」
またホテルなどで行う「宴会」の営業をやっている方の話を聴いたときのこと。
宴会の営業もかなり属人的である部分が大きく、中小企業のオーナー経営者や政財界の大物と直接つながって、とにかくリピートしてもらうことが大事なのだと言う。
「休日でももちろん、携帯電話はいつでもつながるようにしておきます。」と彼はいう。
「なぜですか?」
「何しろ接点をたくさん持たないといけないからです。もちろん完全に公私混同で「知り合いに◯◯やっている人いない?」といった個人的な要望にも答えます。私は取引先の引っ越しにもしょっちゅう顔を出しました。引っ越しは宴会がセットであったりしますから。」
「なるほど」
「もちろん、そういうのが好きじゃないと続けられません。ですが、個人的な付き合いを続けると、大きな仕事を回してもらえたり、コチラが仕事で困っているときに人を紹介してもらえたりもする。」
「たしかにそうですね。」
「まあ、自分をアピールして、売り込むのは基本ですよ。で、向こうもそれを喜んでいるんです。」
いま、Amazonに押されて劣勢だった「家電量販店」で業績を戻しつつある会社が複数ある。
ヤマダ電機が黒字3倍、劣勢の家電量販店でなぜ勝ち組になれたのか?
家電量販店最大手、ヤマダ電機が発表した、16年3月期の連結決算に驚いた。売上高は1兆6,127億円で、前期比3.1%減だったものの、営業利益は同2.9倍増の581億円、最終利益にいたっては、なんと、同約3.3倍の303億円と、「大幅な増益」になったとのこと。
驚いた理由の一つは、よくこのメルマガでも書いているが、私の頭の中で、「家電量販店は安売り中心。利益も出なくなっているのでは?」という固定観念があったからだ。(mag2news)
そして、その理由の1つは「接客」にある。
つまり「知っている人から買いたい」という欲求、「接客してほしい」「売り込まれたい」という欲求を叶えてあげることで、業績を改善させることが可能だということだ。
「売り込み」を嫌う人が数多くいる一方で、それとは逆に「もっと自分に売り込んでほしい」という密かな欲求を持つ人も数多くいる。
それは「自分が偉くなったような感覚」を味わったり、「人情」に触れることを大事にしたり、「知り合いから買いたい」と思ったりする、極めて人間的な欲求だ。
AmazonやGoogle、webがどんどん「人を介在しない取引」を増幅させる一方で、密かにそれに対して不満を持つ人は数多くいる。
そして、そこにはまた別のビジネスチャンスが数多くあるに違いない。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。