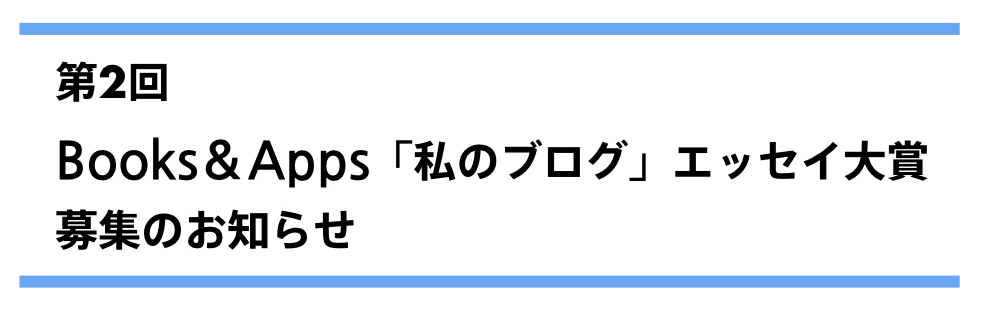ちょっと前にファクトフルネスという本を読んだ。
本書では教育、貧困、環境、エネルギー、人口など幅広い分野を最新の統計データを用いて取り上げて、世界の正しい見方を紹介している。
詳しい内容は本書を読んで欲しいのだけど、簡単にいうと、世の中は私達が思っている以上によくなっているという事実を、これでもかと事実(ファクト)を元に証明していく本だ。
結構、思った以上に事実と認知の間にズレがある事がわかり、人によっては衝撃を受けるかも知れない。
本書をどう読むかは人それぞれだろうが、僕はこれを読みながら、なぜ人間はここまで事実を事実として受け取れないのか、また、人々が事実を事実として淡々と伝える事ができないのかをずっと考えていた。
一ヶ月ほど考えて出た結論は、人間がロジックとエモーションを混同させて生きる生き物だからこそ、世界をありのままに見ることができないのかもな、というものだった。
というわけで今日はロジックとエモーションの話をしていこうかと思う。
情を持つと、世の中を正しくみれなくなる
かつてGEにジャック・ウェルチという経営者がいた。
彼は1年ごとに社員の下位10%を解雇するか配置換えするという非常に厳しい人事評価システムを採用していた事で知られている。
このシステム自体は、賛否両論いろいろあったようだけど、なぜこのシステムをジャック・ウェルチが考えついたのかについての話が非常に面白い。
ジャック・ウェルチが働いていた頃の外資系企業では、必要に応じてキチンと他人のクビを切るのもマネージャー(管理職)の1つの大切な仕事だった。
しかしやはり人にクビを言うのは非常につらい。その為、多くのマネージャーはこれが原因で数年で疲れてしまい、他の職を移ってしまっていたのだという。
そうすると、当然次にまた新しいマネージャーがやってくるわけだけど、ここで非常に興味深い現象が生じている事にジャック・ウェルチは気がついたのだという。
なんと、職場環境をよく知っているはずの前任マネージャーよりも、新しくやってきた新任マネージャーの方が、誰をクビにすべきかを客観的かつ正確に判断できる事が多かったのだという。
普通に考えれば、情報量が多い前任マネージャーの方がよりよい選択ができそうなものだけど、なぜそんな事が起きてしまうのだろうか?
それは、前任マネージャーが”知りすぎている”が故に、社員に情が移ってしまうのが原因ろうとジャック・ウェルチは推測する。
そして、ロジカルな10%ルールを導入すれば、情に惑わされる事なく常に”正しく”、おまけにマネージャーの心を悩ませる事もなく、誰をクビにするべきかをきめる事ができる、と考えるに至るわけだ。
ジャック・ウェルチのこの考えは、クビを言い渡す心労に頭を悩ませていたマネージャーには実に甘美な囁きとなった。
今まで、いろいろと頭を悩ませて誰をどういった理由でクビにするか、なんて言葉でクビを伝えればいいかを考えなければいけなかったマネージャーからすれば、「ルール」でクビを言い渡す相手を自動的に決めてもらえるのだから、これ以上楽な事はない。
というわけで労働者からすれば冷徹だが、マネージャーからすればこの上なく優しい10%ルールは、一時期経営者から称賛をもって向かい受けられていた。
これぞエモーションがあるがこそ故に、ファクトをありのままにみれない事例として、最適な例といえよう。ロジックという合理性の前に立ちはばかるのは、いつだって非合理的なエモーションなのである。
ファクトに基づいてロジカル考え、合理的に正しかったはずの結論が……
そして面白いのはここからである。
ファクトに基づき、ロジカルに出したエレガントな解法であった10%ルールだけど、結果的にはなんと大失敗だったのだ。
今ではGEを含め採用している企業はほとんどない。
果たして10%ルールの何がいけなかったのだろうか?
原因は様々だろうけど、一般的には働きアリの法則というもので失敗の原因が説明される事が多い。
働きアリの法則とは以下のようなものだ。
1.働きアリのうち、本当に働いているのは全体の8割で、残りの2割のアリはサボっている。
2.よく働いているアリと、普通に働いている(時々サボっている)アリと、ずっとサボっているアリの割合は、2:6:2になる。
3.よく働いているアリ2割を間引くと、残りの8割の中の2割がよく働くアリになり、全体としてはまた2:6:2の分担になる。
4.よく働いているアリだけを集めても、一部がサボりはじめ、やはり2:6:2に分かれる。
5.サボっているアリだけを集めると、一部が働きだし、やはり2:6:2に分かれる。
GEの10%ルールの問題点は、4の「よく働いているアリだけを集めても、一部がサボりはじめ、やはり2:6:2に分かれる」に集約されている。
つまり、パフォーマンスが悪い働かないアリをのけ者にして、働きアリだけを集めたところで、結局働きアリが働かなくなるだけなのだ。
なぜアリには、こんな奇妙な生態系が導入されているのだろうか?北海道大学の長谷川英祐は進化生物学の見地からこれをこう解説している。
働くアリと働かないアリの差は「腰の重さ」、専門的に言うと「反応閾値」の差によるのだという。
アリの前に仕事が現れた時、まず最も閾値の低い(腰の軽い)アリが働き始め、次の仕事が現れた時には次に閾値の低いアリが働く。
なぜこんなシステムを導入しているかというと、仮に全てアリが同じ反応閾値だと、すべてのアリが同時に働き始め、短期的には仕事の能率が上がるが、結果として全てのアリが同時に疲れて休むため、長期的には仕事が滞ってコロニーが存続できなくなるからだ。
この結果が正しい事はコンピュータシミュレーションの結果からも確認されており、閾値によっては一生ほとんど働かない結果となるアリもいるが、そのようなアリがいる一見非効率なシステムがコロニーの存続には必要なのだという。
エモこそが私達の本能なのではないだろうか?
10%ルールの失敗はロジカルに、合理的に頭のよい人が正しく判断したはずの回答が、巡り巡って結果的に不正解となった事例として、人間の思考力の限界を痛感させられる一例だと言えよう。
こう考えると、マネージャーが部下をクビにする事に罪悪感を覚えるという情こそが、働きアリの法則の法則を集団で守らせようとする為の本能のようなものに思えてくるのだから面白い。
人間は、働きアリのようにプログラム化された存在ではない。私達には、それぞれ固有の自由意志というものがある。
しかし、この自由なはずの私達だけど、面白いぐらいに類似した文化を各地で形成して社会を営んでいる。
自由な意志を持っているのなら、多様な社会が形成されてもいいだろうに、なぜ人間は世界中のアリが似たような生態系を呈するがごとく、類似したシステムを組み上げてしまうのだろうか?
僕が思うに、それこそがエモーションの役割なのだ。感情という無意識に仕込まれたプログラムこそが、人間を最もキレイにコントロールする補佐役となっているからこそ、人間というのはここまで上手に社会を形成できているのである。
実は民主主義こそがこれを最も体現していると言ってもいい。
太古の昔から、王政や貴族制といった、”頭のいい人”が市政の人々をロジカルに束ねる試みは常に実験されてきた。
しかし多くの場合において、それは失敗している。全てを政府の計画下に置いて、効率化を推し量った共産主義の歴史的な失敗が、それを最もよく表しているだろう。
結局、キリストが産まれてから2019年もたった今、大国の政治はほぼ選挙によって選ばれた政治家と、それを補佐する官僚により成立している。
国民のエモーション担当が政治家であり、国民のロジカル担当が官僚と考えると、この組み合わせが驚くほどシックリくるのは、僕だけだろうか?
もちろん、常にエモーションが正しいとは限らないし、むしろエモーションはよく間違える。
ファクトが正しくみれない私達は、まさにその体現といってもいい。
しかし、それは言うまでもなく、ロジックについても同じことがいえる。
例えば透析患者は自己責任で全員医療費自己負担にしろという考えは、国が借金まみれの今だと、”合理的に考えれば”、ある人にとっては”正解”なのかもしれない。
しかし、これを冷徹に”良し”と判断できない、私達のエモーションの部分に宿った無意識の部分にこそ、私達人間の大切な本能が隠されているのではないだろうか。
もし、近々合理性が社会に導入されたら、エモーションで無意識にコントロールしていた部分はどうなるのだろうか?
ディープラーニングを導入されたAIでビッグデータを解析し、ファクトに基づいた正しい分析が行われようとしつつある。
僕の本職である医療においてもAIの力は及ぼうとしているが、ハッキリ言ってファクト抽出に関して言えば、AIに敵う医者は1人もいないだろう。それぐらいに、AIのファクトを見る目は優れている。
この事を、大手を振って迎え入れている知識人も結構多いけど、一般人の感覚としては、なんか薄ら寒いものを感じないだろうか?
たぶんなんだけど、その感覚は間違ってないのではないかな、と僕はファクトフルネスを読んでなんとなくだけど思った。
こんなにも事実を”正しく”みれてないにも関わらずこの世がどんどん良くなっているのは、逆にいえば多くの人が”正しく”事実をみず、エモーショナルに基づいて行動しているからこそ、結果的に正しくなっているのではないだろうか?
AIが導き出した圧倒的ファクトでロジカルに導き出された答えは確かに正しいのかもしれない。
ただ、それを水面下でコントロールするエモーショナルな部分は、AIが導入された社会において、果たしてキチンと機能できるのだろうか?
ファクトに基づいたロジカルな意識と、エモーションに基づいたスピリチュアルな無意識。
もし、社会にAIが導入され、ファクトがエモーションより多い比率で採択されたとき、私達は真の意味で無意識から手が離れた社会を生きることになる。
それが楽園なのか、地獄なのかはそう遠くないうちにわかるだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【プロフィール】
都内で勤務医としてまったり生活中。
趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。
twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように
noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki
(Photo:nelio filipe)