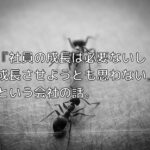昔、「仕事の心得」について、ワークショップをしてくれた先輩がいた。
その最初の問いはこうだった。
『仕事とは何か。』
難しい問いだと思ったが、しばらくして、一人の同僚が言った。
『顧客にサービスを提供することです。』
すると先輩は言った。
『それは現代の「商売」の定義かな。石器時代の共同体には顧客もサービスもなかったが、仕事はあった。』
なるほど、と思った。
確かに仕事とはもうすこし範囲の広いものかもしれない。
もう一人の同僚が、それを受けて口を開いた。
『辞書的に言えば、生きるための作業、というイメージでしょうか。』
先輩は言った。
『悪くないけど、抽象的すぎる。その定義だと、食事なども含まれてしまうのでは?』
誰も正解にたどり着けず、先輩は口を開いた。
『仕事とは、課題を解決する行為だよ。これはピーター・ドラッカーの定義だ。なお彼は「労働と仕事は根本的に違う」と言っている。どういうことか知りたければ「マネジメント」を読みなさい。』
言われてみれば、特に意外でもない回答だったが、ゼロからそれを思いつくかどうか、と言われたら自信はなかった。
先輩は続けた。
『ではもう一歩進めよう。課題とは何か。』
そこで同僚が手を挙げた。
『やらなければならないこと、あるいは問題のことでしょうか?』
先輩は言った
『近いけれども、不十分だ。ほかには?』
もう一人の同僚が言った。
『解決しないといけない問題、でしょうか?』
『そう、課題とは課された、つまり解決されるべき問題のこと。では最後の問い。その問題が解決されるべきかどうか、どう決まるか?』
問題が解決されるべきかどうか……どう決まる?
はっきりと問われると、意外に難しい。
世の中には問題はゴロゴロ転がっているが、解決に向けてきちんとリソースが割かれ、「課題」として扱われることは少ない。
そして、『これが問題だ!あれが問題だ!』と騒ぐ人も多いが、実際に手を動かして、解決に向けて自発的に動く人も少ない。
実際には『課題』かどうかはどのように決まるのか。
例えば、国のレベルでは、課題には予算がつく。
企業においては経営管理者に人とお金を割り当てる決定権がある。
身の回りでは、自分が決めることもある。
私は先輩に回答した。
『多くの場合は、その場の責任者が決めますが、皆の合意による時もあります。』
先輩は言った。
『そう、つまりその作業や労働が「仕事」かどうかは、結局「人」が決める。したがって仕事の心得で一番重要なのは、『他人』に興味を持つこと。』
同僚が質問をした。
『当たり前と言えば、当たり前のことですが、なぜそこまで強調するのですか?』
先輩はすぐに答えた。
『ほとんどの人は、結局「自分」にしか興味がないからだよ。でも、多くの仕事は、他人がどう思うかをベースとしなければならない。』
『なるほど……』
『つまり、お客さんに興味を持て、同僚に興味を持て、社長に興味を持て、世の中の出来事に興味を持て、ということ。興味が大きくて深いほど、仕事はうまくいく。逆に、自分ばかりを見て『人』に興味がない人は、仕事ができなくなりがちだ。』
当時の私は、理系の大学院を出たばかりで、人への興味という点では薄かった。
しかし、先輩はそれを見透かしたように、仕事はそれではいけない、とガッチリくぎを刺してきた。
「仕事の心得」とはまさに、人に興味を持って、それを深く探求することを指す。
技術職でも、芸術家や職人ですら、「仕事」が一人で完結しない以上、他者に興味を持たないわけにはいかないのだ。
他者への興味がない人は仕事が苦痛になる。
他者との関係性を考え抜いた先に、仕事がある。
だから、人が難しいのと同じで、仕事は難しく、かつ奥深い。
ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>
第6回 地方創生×事業再生
再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】
ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。
当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。
【今回のトーク概要】
- 0. オープニング(5分)
自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)
保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)
再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)
経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)
「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)
数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)
経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”
【ゲスト】
鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏
ExePro Partner代表 経営コンサルタント
兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。
高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。
卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。
株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。
その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。
現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。
【パーソナリティ】
倉増 京平(くらまし きょうへい)
ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事
顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。
コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。
ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。
(2025/7/14更新)
【著者プロフィール】
安達裕哉
元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。
◯Twitter:安達裕哉
◯Facebook:安達裕哉
◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)
頭のいい人が話す前に考えていること
- 安達 裕哉
- ダイヤモンド社
- 価格¥1,650(2025/07/18 10:08時点)
- 発売日2023/04/19
- 商品ランキング199位
Photo:Helena Lopes