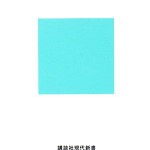「失敗は成功のもと」ということばがある。スタートアップにおいて成功の条件の一つは、「失敗すること」という人も多い。失敗することは大事なのだ。
しかし、会社において、これは大失敗、という話を聞くことは実は少ない。また、書籍やwebにおいても、「失敗談」が公開されているケースは少ない。
経験的にも、私がコンサルタントをしていた時かなりの数の会社に訪問したが、「失敗」についての話はあまり耳にしなかった。
会社によっては社長の失敗した新規事業や、人事異動など、「その話はタブー」と、腫れ物に触るように扱うケースも多く、「失敗」についてはその事実が隠蔽されていることも多い。
だから、キレイ事として「失敗は成功のもと」とはいうが、現実は乖離している。皆、失敗を認めたくはないのだ。
だから、あるwebサービスの会社に訪問し、経営者から「うちは失敗を奨励しています」と聞かされた時、私は大変不遜だとは思うが、その言葉をさほど信じてはいなかった。
だが、それはすぐに間違いだとわかった。この会社は実際に新しいサービスを次々と生み出し、そして潰していた。webサービスが収益を生み出すまで大きくなる可能性はそれほど高くない。だが、数多くの失敗の中で、ほんの僅かなものは収益を生み出した。
そしてなによりも皆、その失敗とチャレンジを楽しんでいた。
私は経営者に「なぜ皆、積極的に失敗することができるのですか?殆どの人は失敗を認めないのに」と聞いた。
「なぜだと思います?」
経営者は質問に答えず、私に意見を求めた。
「失敗しても、その責任を取らされないからでしょうか。」
「そんなことはありません。責任は取らせます。」
「そうですか、だとすると……」
私の頭には仮説らしきものすら思い浮かばなかった。
「では、質問を変えましょう。人が失敗を認めるのは、どんな時だと思いますか?」
私は過去の会社の仲間、顧客のメンバーなどの顔を思い浮かべならがら、「自分の限界を知った時でしょうか」と回答した。
「そうです。それに近いかもしれません。我が社では「失敗と認める基準」を、チャレンジをする前にプロジェクトの責任者に提出してもらいます。もちろん、安易に失敗を認められては困りますから、「失敗の基準」はかなりきちんと練ります。」
「成功の基準ではなく?」
「そうです。そこが最大のポイントです。どの程度の大きさの成功をするかは、こういったwebサービスには向いていません。逆に言えば、自分たちの想像よりも成長しなければ、成功とはいえない。」
なるほど、そうかもしれない。新規事業の事業計画など、あらゆる会社で当たった試しがないのである。
「失敗の基準は、「成果」もありますが、「◯◯のような施策を行う」といった、行動に関するものもあります。網羅的に行動したが、うまく行かなかった。今の自分には実現不可能だった。これは失敗を認める基準になります。
失敗は失敗と認める。そういう社風はこの取り決めから生み出されていた。
「しかし、頑張る人ばかりではないのでは?」と、私は疑問をぶつけてみた。
「そのような方は、失敗した、ではなく、怠けている、として扱います、きちんとやり切るまで失敗を認めさせません。」
「認めさせない、というのも変わってますね。」
「諦めが悪くなければ、成功などおぼつきませんよ」
失敗を認めるのは、誰にとっても難しいものだ。だが、仕組みによってはそれを補うことができる。制度やシステムとは、人の弱さを補完するものなのだろう。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (最新記事をフォローできます)
(Photo:Behrooz Nobakht)