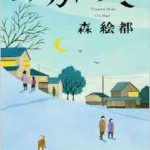人事部で仕事をしている関係上、“ルール”と向き合う機会が非常に多い。
労働基準法という法律レベルのルールから内規という社内限定ルールまで、様々なルールのもとで組織が成り立っている。
普段ルールを意識することはあまりないかもしれないけれど、何かトラブルがあった時に頼りになるのはルールであり、無意識のうちに行動の基準になっているのもルールである。
社会人になり、人事部で仕事をするようになり、私の中でルールの捉え方は大きく変わった。
子どもの頃は、「ルールを守りましょう」「ルールを破ってはいけません」と教わる。
ルールを破る人は“問題児”であり、ルールを守ることは“優等生”であるための条件の1つだった。大学に入るまで、私にとってルールは絶対的なものだった。破るなんてありえない。
宿題は必ずやるし、校歌は必ず歌うし、遅刻は絶対にしない。髪を染めたりスカートの長さを変えたりするなんて言語道断。それこそ車も通らなければ周囲に人もいない横断歩道であっても、赤信号では絶対に渡らないような生き方だった。ルールに縛られた生き方とはまさにこのことだ。
優等生でありたかったというより、ルール通りに生きることが自分の中での正義だったため、ルールを破ることが選択肢として存在していなかった。
大学生になり、ルールを破るという選択肢があることを知った。
形式的で無意味なルールが存在すること、現状のルールが必ずしもベストなわけではない、疑義を呈する余地があるものだということを知ったのだ。
自分の中の正義感が揺らいでいき、だんだんルールとの付き合い方を覚えていった。
そして社会人になり、人事の仕事をするようになり、仕事としてルールに向き合うようになった。
人事部に配属されて最初に言われたのは「就業規則を熟読してください」であり、問い合わせへの対応がわからないときに上司に言われたのは「就業規則に書いてあるから探してみて」であった。
給与の計算でわからないことがあったら「就業規則ではどうなっている?」とにもかくにも「就業規則」が基準である。大学生の頃、「ルールは意外と守られない」「ルールが正しいとは限らない」と、自分の中でルールのパワーが弱くなっていたが、ここにきて再びルールが強い力を発揮してきた。
就業規則は労働基準監督署にも届け出ているちゃんとしたルールらしい、ということも少し経ってから知った。
ルールの力を再認識したところでもう1つ、大事なことに気づいたのだが、ルールは結構な頻度で変わっていく。
ベンチャー寄りの企業に勤めているから余計そう感じるのだろうか。
本当に、頻繁に変わる。法改正という大きな変更でさえ、毎年何かしらある。まして社内ルール……現状に合わないと思ったら、あっさりと変わる。
今日ダメだったことが、明日には認められるなんてことも結構ある。
「言ってみるもんだなー」と思う。今のルールには当てはまらないから、という理由で主張を伝えないのはもったいない。そのルールは絶対的なものではないのだ。
現状から合理的に考えて変えた方が良いのであれば話し合う余地は充分にある。
実は少し前から「就業規則をつくる」という仕事をしていて、「ああ、こうやってルールができていくんだな」ということを実感している最中でもある。
つくると言っても0からつくるわけではなく、「会社を合併したから規則も統合しないとね」という流れで、2つの就業規則をもとに新しい規則をつくっていこうとしているのだが、これがなかなか興味深い。
2つの就業規則を比べてどちらか良い方を選択するケースもあれば、「これはどちらもイマイチだね」と全く新しいルールをつくるケースもある。決して簡単ではないものの、ある意味“簡単に”ルールがつくられていく。
強い力があると感じていた就業規則である。その就業規則を、話し合いをもとにつくっていく。
就業規則に限らず、法律も校則もどんなルールも、少人数の話し合いの結果が、多数の人々の基準となる。これってかなりすごいことじゃないだろうか。頭では「そんなのあたり前」なんだけど、感覚的に、すごい。
ちなみに、中には「こんなルール、必要?」と思ってしまうような細かいルールがあったりもする。
そんな時に思い出すのが、「性善説を信じているなら、そもそもルールなんて必要ないんだよ」という誰かの言葉である(誰に言われたのか忘れてしまった)。
この言葉を脳内に浮かべながら不要だと思ったルールをもう一度見ると、大抵の場合、必要に思えてくる。
結局のところ、
・ルールは強いパワーがある
・けれど、絶対的なものではなく、変わっていく
ことがわかったというそれだけのことなのだが、「ルールは守るか破るかのどちらか」だと思っていた私にとって、「変えたりつくったりするものでもある」というのはちょっとした発見だった。
ルール至上主義という言葉がある一方で、「ルールは破るためにある」なんて言う人もいる。
私は、ルールは守るものでも破るものでもなく、使うものなんじゃないかな、と最近考えている。
☆★☆★☆
ではまた!
次も読んでね!
(Photo credit: funkandjazz via Visualhunt / CC BY-NC-ND)
(2025/12/24更新)
生成AIを導入しても成果につながらない――そんな課題に向き合うためのウェビナーを開催します。
生成AI活用が当たり前になりつつある一方で、「思ったように成果が出ない」「手応えが感じられない」と感じている企業も少なくありません。
本ウェビナーでは、ティネクトが実際に経験した“失敗事例”を起点に、生成AI活用でつまずく本当の理由と、成果につなげるための考え方を整理します。
経営層、マーケティング責任者、オウンドメディア運営担当者の方に特におすすめの内容です。
ぜひご参加いただき、2026年に向けた判断軸をお持ち帰りください。
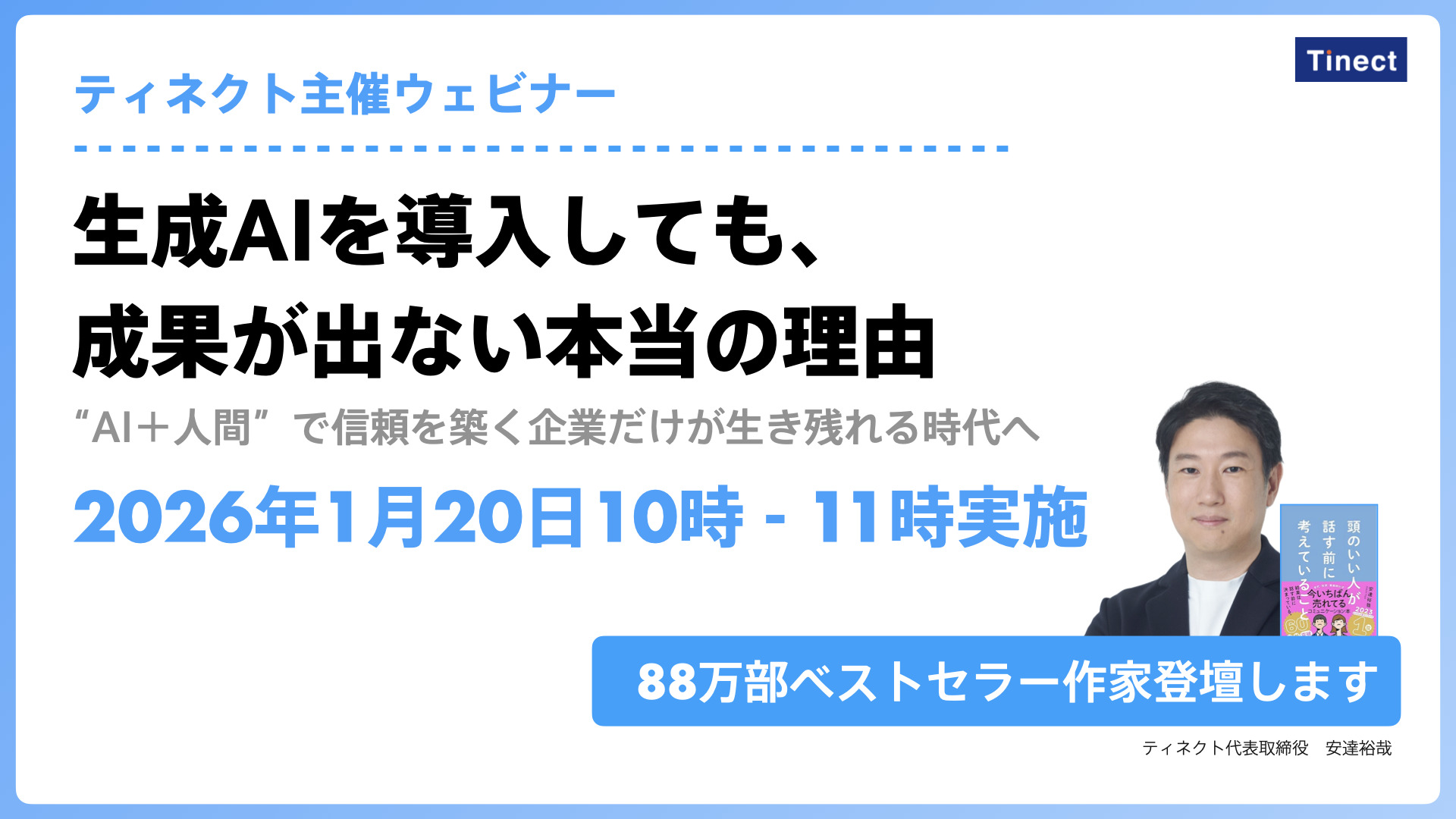
このウェビナーでお伝えする5つのポイント
・生成AI活用が「うまくいかなくなる構造的な理由」がわかる
・実際の失敗事例から、避けるべき落とし穴を学べる
・問題はAIではなく「設計」にあることが整理できる
・AIと人間の役割分担をどう考えるべきかが明確になる
・2026年に向けたコンテンツ投資・運営の判断軸が持てる
<2026年1月20日 実施予定>
生成AIを導入しても、成果が出ない本当の理由
“AI+人間”で信頼を築く企業だけが生き残れる時代へ。
失敗から学ぶ、これからのコンテンツ設計と生成AI活用の考え方をお届けします。
【内容】
第1部:しくじり先生の告白 ― 生成AI活用で何が起きたのか(楢原一雅)
第2部:客観解説 ― なぜ成果が出なかったのか、どうすべきだったのか(安達裕哉)
第3部:解決編 ― AI+人間で信頼を生むコンテンツ制作の考え方(倉増京平)
日時:
2026/1/20(火) 10:00-11:00
参加費:無料
Zoomウェビナーによるオンライン配信となります。
お申込み・詳細
こちらのウェビナー詳細ページ
をご覧ください。
[著者プロフィール]
名前: きゅうり(矢野 友理)
2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。
著書「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)
(Photo:Carlo Scherer)