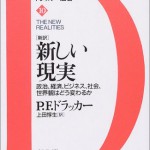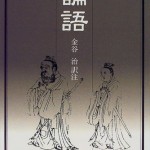学生同士のグループディスカッションを見ていた。テーマは「終身雇用の是非について」だ。
今の学生は保守的であるとの見解もあるようだが、殆どの学生は「自分が最初に就職した会社に定年まで在籍する」とは思っていないようだ。いずれ何処かで転職したり、起業したり、そういったことが話題となっていた。
そこで、「何歳くらいまでに最初の会社をやめていると思う?」と聞くと、「30歳前後です」という声が多かった。
そこで私は一つ質問をしてみた。
「今話してもらったとおり、60歳まで一つの会社に勤めることは殆どない、と皆は考えているようだけど、もし法律で「定年を35歳とします。その後は各人が企業と自由契約です」ということが決まったらどう思う?」
これに対して学生のほとんどは「困ります」「反対」という回答だった。
なるほど、殆どの学生は自分が30前後で会社を辞めると言っているにもかかわらず、35歳になったら強制的に辞めざるをえない、ということには抵抗する。
理由を聞いてみると、
「ずっと働きたいと思っていても、辞めなければいけないのは不合理」
「35歳で職が見つかるかどうかはわからない。安心できない」
「できる人は再雇用されるが、できない人はクビになる。失業者がたくさん出て、格差が広がりそう」
などの意見が出た。
総合して見えることはやはり、「正社員はセーフティーネット」という意識だ。つまり「とりあえず会社員でありさえすれば、食べていくには困らない。」という発想である。
これはドラッカーの予言した、「知識労働者」とはずいぶん発想が異なる。著書「新しい現実」の中で、彼はこう述べる。
知識労働者であるということは、いかなる特定の雇用主にも組織にも縛られないことを意味する。
コンピュータの専門家にとって、就職口はデパート、大学、病院、政府機関、証券会社のいずれでも良い。彼らの関心は、給料を別とすれば設備が最新のものか仕事が面白いかである。
同じことは金融アナリスト、理学療法士、人事管理者、治金の専門家、セールスマン、グラフィックデザイナー、地方の美術館の企画担当者に当てはまる。
つまり学生たちは自分たちを専門家とみなしていない、ないし、専門家として自立していくと考えていないということだ。
しかし、現実には専門家として働く人、フリーランスは増えているようだ。
これは大きな変化である。また、フリーランサーのマッチングサイトは海外でも日本でも盛況であり、業績も延びている。例えば日本は「クラウドワークス」や「ランサーズ」などのフリーランサーのマッチングサイトが業績を伸ばしている。
ドラッカーは「知識」が社会の中心となると言った。
もしこれが本当であれば、35歳くらいまでには「自分が何の専門家となるのか」を見極める必要があるだろう。
ダニエル・ピンクは、「フリーエージェント社会の到来」の中で、アメリカではすでに4人に1人がフリーエージェントであると述べる。近未来の日本で同じようなことが起きる蓋然性は高い。学校で「専門家を目指せ」ともう少し強くメッセージを出しても良いと思うのだが、どうだろうか。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。