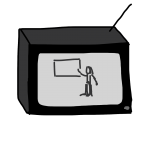このメディアの書き手の一人である高須賀さんから、メッセージを頂いた。
高須賀さんは、月200時間以上の超長時間労働を経験されたということだったが「結構がんばれていた」という。
ただしそれは「指示を出す側」という条件付きの場合だった。
それでも指示出し側だったのもあって、結構みんながんばれてましたね。逆に指示出される側のコメディカルは、勤務時間が僕らよりも少なくてもバンバン消えてってましたし。やっぱり裁量の有無は大きいなぁと
私も同様の記憶が数多くある。
例えば、私が新人の時に一番キツイと感じた仕事が、実は「上司・先輩のコンサルタントへの同行」だった。
「上司や先輩のコンサルタントへの同行なんて、任せてればいいからラクじゃない」
という方もいるが、とんでもない。あれは一番負荷が大きい仕事の1つだ。
仕事に慣れておらず、自分だけでは何一つできない状態で、先輩からの指示だけ飛んで来る。
・議事録つくってお客さんに投げといて
・お客さんに様式をわたしておいて
・日程調整しておいて
・説明会の案内を作っておいて
……
仕事がよくわからないながらも、飛んでくる指示をこなすことで一杯一杯となるあの状態。
さらに、お客さんに訪問したときは自分はひたすら「聴いているだけ」である。
ずっと黙っているのは非常に苦痛であるし、お客さんは全くコチラを向いてくれない。当たり前だ。金魚のフンのようにくっついてきている若造に、だれが話をしたい思うだろうか。
客先でも、先輩からも「下っ端」として扱われ、自分の裁量のないところで夜11時、12時まで拘束され、働くことを想像してほしい。
これが「精神を病んでいく」働き方の本質である。
それでもわたしはかなりマシだった。
会社には「独り立ち迄のルール」が定められており、何回か先輩と上司の同行を受ければ、あとは「一人でやりなさい」という明確なルールがあったからだ。
そのルールに定められた規定回数をすぎれば、責任は重くなるが、自分の好きなようにやれる、自分のペースでやれる、お客さんとまともに話すことができる。
そう思えばこそ、あの時期に超長時間労働に耐えることができたのだと思う。
逆に「お前なんか、まだまだ若造だ」
とか、「本当にだめなやつだ、一人前になるのはかなり先だな」
と言われながら同じような働き方を続けなければならなかったとしたら、そして会社を辞めることができない状態なら、かなりの割合で抑うつになったのだろうと推測する。
————————-
人間は本能として「コントロールする能力」を失うと、生きる力を失う。
ハーバード大の社会心理学教授、ダニエル・ギルバートは次のように述べた。*1
人間はコントロールへの情熱を持ってこの世に生まれ、持ったままこの世から去っていく。
生まれてから去るまでの間にコントロールする能力を失うと、惨めな気分になり、途方に暮れ、絶望し、陰鬱になることがわかっている。死んでしまうことさえある。
そして、彼はそれを実証したこんな研究に触れている。
地域の老人ホームの入所者に観葉植物を配った。
・半数の入所者には自分で植物の手入れと水やりを管理するように伝える(コントロールする能力を与えられた側、高コントロール群)
・後の入所者には職員が植物を世話すると伝える(コントロール能力を奪われた側、低コントロール群)
6ヶ月後、後者では30%の入所者が死亡していたのに対して、前者では死亡はわずか15%だった。
さらに、追試研究によって、コントロール能力が老人ホーム入所者の福利にいかに重要であるかが確かめられたが、同時に予期せぬ不幸な結果も招いた。
学生を雇って、入所者を定期的に訪問させた。
・高コントロール群の入所者には、訪問してほしい日時を自分で決めさせた。
・低コントロール群の入所者には、日時を決める自由はなかった。
2ヶ月後、高コントロール群の入所者は低コントロール群の入所者より幸せで、健康で、活動的で、薬の服用量が少なかった。
ところがこの研究が終了し、学生の訪問が終わった数ヶ月後、高コントロール群の入居者の死亡が極端に増えた。
研究者たちは愕然とした。
原因はあきらかだった。高コントロール群の入居者は、研究が終わった瞬間、コントロール能力を取り上げられてしまったからだった。
コントロールを得ることは、健康や幸福にプラスに働くが、コントロールを無くすのは、はじめから持っていないよりも深刻な事態を招きうる。
電通で自殺した女性は、ある意味「何もかも自分でコントロールできる人生」を歩んできたはずだ。
容姿に恵まれ、学歴に恵まれ、そして就職も電通、人生は「ある程度コントロールできる状態」だっただろう。
だが、その「人生のコントロール能力」は一瞬にして奪われた。会社の中では、何もかもが予測不能で、自分の裁量はほとんどない。
彼女は深い絶望に襲われたのだろうと思う。
マネジャーは「指示を出される側の苦痛」を知らなければならない。
裁量のない仕事、それは時として、マネジャーが想像するよりも、遥かに大きな精神的苦痛なのだ。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
*1
・筆者Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。