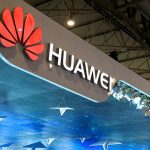わずか一代で1兆円を超える売上を上げる企業を作った、日本電産の創業者である永守重信氏は厳しい人物であることで有名だ。
特に、役員を始めとした「幹部社員」には、些細なミスであっても猛烈な叱責をすることで知られている。
だが永守氏は、誰にでも厳しく当たるわけではないらしい。
著作においては「組織の上の人物には厳しく当たるが、新人には優しくする」「上に上がれば上がるほど、厳しく叱られる」と書かれている。*1
かの会社においては「管理職への評価は厳しく、かつ労働時間も長い」ことが、当然のこととされている。
確かに、私が企業の現場で感じたこととして、管理職がラクをしている会社の業績はあまり良くなく、現場の士気も低い。
それは本質的に、管理職の役割が「平凡な社員が、労せずして成果をあげる仕組みを作ること」だからだ。
そして、仕組みを作ることは、自分が手を動かして働くことの、数十倍、大変な試みであり、大きなプレッシャーを伴う仕事だ。
必然的に、労働時間は長くなる。
だが「仕組み」を担うべき管理職が仕事をしていなければ、その損害の額は機会損失も含めれば膨大である。
部下たちの離職、モチベーションの低下、生産性の低下、長時間労働による人件費の増大や法律違反リスク……
管理職が「仕組みづくり」に失敗し、そのミスによる負荷を現場に背負わせた結果が、多くの「ブラック企業」なのだ。
永守氏が地位が上がれば上がるほど些細なミスに対しても猛烈な叱責をするのは、おそらくその責任の重さを理解してほしいからだろう。
しかし、現実にはこれと逆の会社も多い。
経営者が管理職には甘く、ラクをさせる一方で、現場の社員は悲鳴を上げている、というケースは実は非常に多く見受けられる。
・「上司より早く帰宅すると評価が下がる」という会社
・社長は幹部の意見を信用するが、現場の末端社員の話は取り合わないという会社
・「創業時から会社に尽くしてくれたから」という理由だけで、社長が特定の管理職をかわいがっている会社
・部門の成果が出ない原因を「管理職」ではなく「現場の社員のやる気」の責任にする会社
そのような状況においては、無能な管理職、ひいては経営者に対する怒りが社員に蓄積していく。
しかし、経営者がその状況に気づくことは稀である。
当然だ。管理職はその権限で「マネジメントの失敗です」という事実は伏せ、部門の成果が出ないのは、ダメな部下の能力やモチベーションのせいにすることができるからだ。
*******
実際、上に挙げたような「成果を出せていない管理職」は、
「ルールを守らない社員が多い」「うちの社員は能力不足だ」「社員のモチベーションが低い」と言うことが多く、必死に社内のルールをいじる。
だが、結局は大した改善もなく終わる。
なぜなら、人事をやるものであれば当然のこととして知っているが、
「管理職の人選ミスは、他の施策でカバーできない」からである。
実際、部門の成果が出ない原因は、ほとんどの場合ルールではなく、社員のモチベーションでもなく、能力不足でもなく、管理職の人選が間違っているだけである。
実際、管理職を取り替えるだけで、劇的に部門の成果が改善することはそう珍しくない。
逆に、成果をあげることのできない管理職をそのまま居座らせることは、周りにとっても、本人にとっても不幸なことである。
ピーター・ドラッカーは「人事は究極の権限」と述べ、次のように言った。*2(太線は筆者)
人事がうまくいかなかったときには、動かされた者を無能と決めつけてはならない。人事を行った者が間違ったにすぎない。
マネジメントに優れた組織では、人事の失敗は異動させられた者の責任ではないことが理解されている。
重要な仕事をこなせない者をそのままにしておいてはならない。動かしてやることが組織と本人に対する責任である。仕事ができないことは本人のせいではない。だが動かしてやらなければならない。
「管理職」から異動/降格させたことで、一時的にふさぎ込む人もいる。だが、結果的に異動後のほうが、成果をあげることも多い。
ある降格させられた管理職は、
「現場に戻れて、かえって良かったです。人にやらせるより、自分でやるほうが性に合ってます」と言った。
当然である、彼はかつて、「営業成績No1」だった社員なのだ。だから管理職になれた。
しかし、彼は「管理職」には向いていなかった。
*******
多くの企業が苦しんでいるのは、実は不適切な管理職を異動/降格できないからである。
「成果を出せない管理職」は、誠意を持って、すぐに動かしてあげよう。会社と部下、そして本人のために。
*2
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【著者プロフィール】
・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)
・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント
・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ
・ブログが本になりました。
・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました!
(Photo:Maurizio)