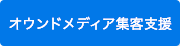先日安達さんが寄稿した『「心理的安全性」という概念は、まだ、日本人には早すぎる。』という記事がよく読まれていた。
みなさんの反応を見てみると、どうやらこの一文が多くの人の心を捉えたようだ。
日本人は、反対意見と、人格攻撃を区別できない人が多い。
だから、知識労働者に必要とされる「率直な物言い」が、そのまま対人トラブルにつながる。
わたしもずいぶん前に『「ちがう意見=敵」と思ってしまう日本人には、議論をする技術が必要だ。』という記事を書き、大きな反響をいただいて新聞にまで転載された。
どうやら、「日本人はちがう意見の人とうまく付き合えない」というのは、多くの人が抱いている思いらしい。
でも日本でそうなるのはある意味当然で、理にかなっているのだ。
だって日本は、「全会一致」を目指すから。
「異なる意見を出しても拒絶されない」という心理的安全性
「心理的安全性」という言葉は安達さんの記事を読んではじめて知ったのだが、どうやらこういう意味らしい。
心理的安全性とは、対人関係においてリスクある行動を取ったときの結果に対する個人の認知の仕方、つまり、「無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」と信じられるかどうかを意味します。
つまり、「人間関係が悪くなるかもしれないけど、モノゴトをよくするためにこういう行動をしたい。
このチームのメンバーならそれをわかって受け入れてくれるはず」という信頼感、安心感のことを指すようだ。
チームの心理的安全性を調べるのには、以下の7つの要素が評価軸になるとのこと。
わたしは英語が不得手なので、心理的安全性を提唱したエドモンソン氏の説を紹介している、前述のGoogleのページから引用したい。
1.チームの中でミスをすると、たいてい非難される。
2.チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える。
3.チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある。
4.チームに対してリスクのある行動をしても安全である。
5.チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい。
6.チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない。
7.チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる。
今回注目したいのは、3つ目の「チームのメンバーは、自分と異なることを理由に他者を拒絶することがある」という部分だ。
「異なる意見を出しても受け入れてもらえるという信頼」が心理的安全性のひとつの要素なら、反対意見=人格攻撃として否定されがちな日本は、「心理的安全性が低い」と言えるだろう。
「んじゃいろんな意見を出しやすい環境にすればいーじゃん!」と思うのだが、そうもいかない。そうはならない。
なぜなら日本では、心理的安全性が低いほうがうまくいくから。
全会一致を目指すなら異分子排除が効率的
日本では主に、「全会一致」を目指す。
みんな同じ意見をもち、みんなが賛成し、みんなが「自分だけで決めたんじゃない」と安心できる状況が「良い」のだ。
率直な意見は、波風立てるだけのジャマなもの。
そんなのないほうがいいのに、なんであの人は余計な反論をするの?
ほーら、空気が悪くなった。あの人っていつもそう。
わかるわかる、前からデリカシーないと思ってたんだよね。空気読めって感じ。
この前だってわたしの化粧に文句つけてきたんだよ。
なにそれサイテー……。
こんな感じで意見と人格がごちゃまぜになり、反対意見=こっちを否定した悪い人として、「協調性なし」の烙印を押される。
それがイヤだから、たいていの人は余計なことは言わず、多数派に流れていく。
異なる意見を出す反乱分子は「オカシイ人」としてちゃちゃっと排除、平和に、滞りなく、「全員賛成」に着地して大団円。
みんな一緒で安心安全、最高の結果である。
もし「異なる意見を出しても大丈夫」なんていう心理的安全性を保証してしまったら、せっかくの「和」が乱れてしまう。
全会一致から遠のいてしまう。それはイカン。
全会一致に対する手段として考えれば、心理的安全性は低いほうがいいのだ。
自分の意見がいかに優れているかをプレゼンするドイツ
では、「いろんな意見をバンバン出そうぜ!」という環境ではどうなるのか。
例として、わたしが住んでいるドイツを挙げたい。
ドイツの大学でゼミに行ったとき、みんなが口げんかしているように思えた。
みんな自分の言いたいことばっかり言って、他人の意見を否定ばっかりするからだ。
ほかの人が話してるのにかぶせて話すし、一度話し始めたら止まらないで気が済むまでずーっとしゃべってるし。
「その統計は信用できるのか」「君はなにもわかっていない」「基本的なことを見落としてるじゃないか」「それはまちがっている」なんて、かなり挑発的な表現もよく耳にした。
その勢いに最初はビビっていたけど、だんだんわかってきた。
この人たちの目標は「一番いい意見を採用する」ことだから、自分の意見をプレゼンしているだけなんだ、と。
「俺を納得させろ、納得させられないなら俺が正しい」と自分の意見をプレゼンし、自分が反論できなくなれば「相手のほうが上手だった」と白旗を上げるだけ。
押し勝ったほうの意見が正しくなるのだから、そりゃ強気でいくわ。
「どの意見が一番いいのかを決めるプレゼン大会」だと思えば、心理的安全性確保が大切になるのもうなずける。
だってみんなが同じ意見になったら、そもそもプレゼンする意味がなくなっちゃうもの。
意見を言わない人間は、話し合いで存在する価値がないのだ。
もちろん、比較検討した結果全会一致になることもあるし、多くの人が賛成する=一番いい意見、という側面もある。
しかし、「結果的にみんなが納得する」のと、「みんなが同じ意見になることを目標にする」のはちがう。
日本で「異なる意見を言ってもいい」という心理的安全性が低いのは、日本が遅れてるというわけではなく、単純に「全会一致という目的に対する手段として心理的安全性が不要。むしろないほうがいい」から。
ドイツで意見が言いやすいのは、「さまざまな意見を聞いたうえで最善を選びたいから」。
要は、話し合いに期待するものがちがうのだ。
目的を変えなければ手段は変わらない
とはいえ、「だから日本で異なる意見を言えないのはしょうがない」と納得していいものか……。
さまざまな意見が尊重されない社会はきっと、とても息苦しい。
少しでも異端になれば、すぐにつまはじきにされるから。
「じゃあ『日本でも異なる意見を言えるように心理的安全性を確保しましょう』と言えばなにか変わるのか」といえば、まぁ変わらないだろう。
全会一致を目指すなかでは、「異なる意見が飛び交う環境」なんて必要じゃないもの。
戦争が科学を発展させたように、必要になれば技術は発展するし、需要がなければいつまで経っても進化しない。
つまり、「心理的安全性が必要な状況」がなければ、それは発展しないのである。
だから一番最初にするべきは、「異なる意見を言ってもいいですよ」と言うことではなく、「全会一致ではなく、たくさんの意見を比較検討し一番いい意見を採用する」のを話し合いの目的に据えることだ。
全会一致方式から抜け出せば、おのずと、気兼ねなく意見をいう心理的安全性が必要になるのだから。
心理的安全性を高める2つのカギ
全会一致方式から抜け出すポイントは、ふたつあると思う。
一つ目は、決定権を明確にすること。
「みんなで決める」の一番のメリットは、責任の分散だ。
多数派に合わせておけばたいした責任をとらなくて済むから、適当なイエスマンが増える。反論すると責任が発生するからだんまりになる。
それを回避するために、決定権を明確にするのだ。
その場にいた全員の意見がどうであれ、決定の責任を負うのはたったひとり。
判断を一任される責任者の心理的プレッシャーは、かなり大きいだろう。
だからこそ、毒にも薬にもならない適当なイエスマンより、ちゃんと考えて意見を率直に言ってくれる人をとなりに置きたくなるはずだ。そのために意見を言いやすい環境を整えるだろう。
(なかには「俺が決めるからお前ら黙ってろ!」というパワハラワンマン社長的な人もいるだろうが、その人はそもそも話し合いを求めていないので棚上げしておく)
二つ目は、話し合いをコンペのように捉えることだ。
ドイツで経験した議論は、話し合いというより、自分の意見をみんなにプレゼンして、まわりがそれらを比較検討するコンペみたいだった。
「自分はこう思うからこれがいい」に始まり、「あなたの意見はここがダメ」「いいや、そっちだってデータが足りない」「でも実践ではこうなんだ」「再現性はあるのか」と、どっちのほうが説得力があるかの勝負をしている感じ。
決定権をもつ人に「なるほど」と思わせれば、勝ちだ。
このやり方が優れている、というわけではないが、少なくとも「いろんな意見を出す心理的安全性の確保」という点では、相性がいいと思う。
全会一致を目指すのであれば、心理的安全性は必要ない。
でもいろんな意見を聞きたい、異なる意見も受け入れたい、それができる環境の方が健全だ、と思うのであれば、「全会一致」から「一番いい意見の採用」を目指していくべきだと思う。
そのために、「決定権を明確にした」「コンペ形式」というのは、ひとつの例になるんじゃないだろうか。
大好評ティネクト主催ウェビナー5月実施のご案内です。
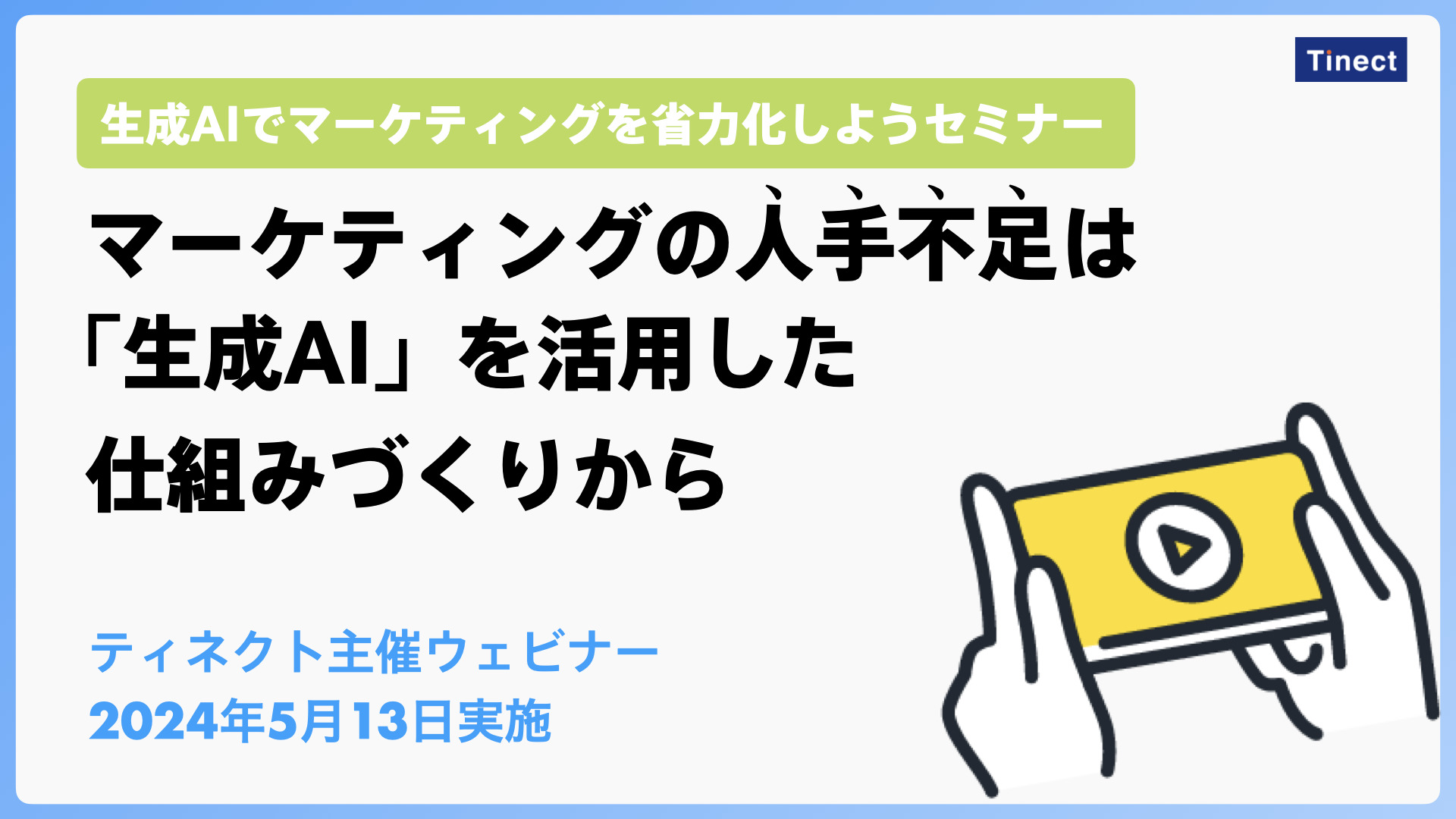
良いアイデアはあるけれど、実行に移せない…
このような課題をお持ちの企業の経営者様、事業責任者様へ向けたセミナーを開催します。
<2024年5月13日実施予定 ティネクト90分ウェビナー>
マーケティングの人手不足は「生成AI」を活用した仕組みづくりから
-生成AIで人手不足を解消しようセミナー<セミナー内容>
1.あらゆる業界で起こっている人手不足
2.「動ける人材がいない状態」から脱却しつつある事例紹介
3.マーケティングの省力化事例
4.生成AI用いた業務省力化、その他の取り組み
【講師紹介】
倉増京平(ティネクト取締役)
楢原一雅(同取締役
安達裕哉(同代表取締役)
日時:
2024年5月13日 (月曜日)⋅18:00~19:30
参加費:無料
Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。
お申込み・詳細 こちらティネクウェビナーお申込みページをご覧ください
(2024/4/21更新)
【著者プロフィール】
名前:雨宮紫苑
91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&
ハロプロとアニメが好きだけど、
著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)
ブログ:『雨宮の迷走ニュース』
Twitter:amamiya9901
Photo by Michal Matlon on Unsplash