ちょっと前のこと。
妻が、ホームベーカリーを前にして、ウンウン言っていた。
「どうしたの?」と聞くと、「今までとは違う小麦粉を買った。」という。
「なんで焼かないの?」と尋ねると、どうやら今までの小麦粉と膨らみ方が違うと本で読んだので、躊躇しているという。
悩んでても結果がわかるものではないので、
「とりあえず、今までと同じやり方で焼いてみりゃいいじゃん。それ見て調節したら?」というと、
「うーん、でも……。」
と腰が重い。
たとえパン焼きであっても、新しい試みは、考えなければならないことが飛躍的に増える。
「まあ、面倒だよな……。」と思ったが、急かすことはないと思い、「がんばれ」と言ってその場を立ち去った。
*
別の日。
子供が、あさがおの観察日記を書いていた。
ところが、書き始めてしばらくして、固まってしまっている。
「どうしたの?」
と聞くと、「うまくかけない。失敗した」という。
色鉛筆で書いてしまったので、消すことができない。
また、学校指定の様式に書くのだが、その様式が1枚しかない状況だった。
そこで、手伝うことにした。
スキャナで取り込んで、写真加工ソフトで絵を消し、様式のみをプリンターで出力する。
これで様式のデータが出来上がったので、何回失敗しても大丈夫だ。
ところが、「何枚くらいいる?」と聞くと「1枚でいい」という。
「うまく書きたいのなら、何枚か書いてみて、できが良いのを提出すればいいじゃん。」
というと、しばらく考えている。
「じゃ、紙5枚くらいとりあえず出しておこうか?」
というと、彼女はしばらく考えていたが、「うーん。」と言った。
なにか渋っているので、後で話を聞くと、
「書き直しは嫌だな、と思った」という。
私は「何度でも書き直せるので、気が楽になった」というかと思ったが、どうやら大きなお世話だったようだ。
単純に「書くのが面倒」だったのだ。
*
知人から「企画書を書きたいのだけど、書き方を教えてほしい」と言われた。
私は、参考になりそうな資料をいくつか渡し、アドバイスをした。
「けど、実際に書いてみないと、ちゃんとしたアドバイスはできないよ」
というと、彼は「書くので、見てほしい」という。
しばらくして。
私が「書いた?」というと、
なんと知人は「まだ書いていない」という。
「そっか。」というと、
「なんか、うまく書けないんだよね……。」とゴニョゴニョいう。
残念ながら「書かない人」には、これ以上なんともできない。
ただ、「書いたら見せろ」というのは不躾だったかも知れない。
反省である。
そこで、
「最初はみんな下手だから、恥ずかしがる必要はないと思うよ」
とやんわりいうと、
「恥ずかしいわけじゃないけど……」という。
そこで、「ははーん……初めてだから、腰が重いんだな。」と思い、率直に聞いた。
「書くのは大変だよね。ここで見てるから、今ここでやったら?」
「……助かる。」
*
私も、若い時はよく勘違いしていた。
多くの人が「やらない」理由はほとんどが「失敗が怖いから」とか「やり方がわからないから」なのだと。
だが、それは嘘だった。
別に怖くもないし、やり方も聞いたり調べたりすれば、たいていわかる。
単に「初めてのことは、面倒くさい」のだ。
そう考えると、いろいろなことに説明がつく。
会社で新しい試みを推進するのも。
「怖い」だけならば、「大丈夫、思い切りやればいい。」と上司がバックアップすればよい。
だが、「面倒くさい」は、突破できない。
SNSをやっていない人に「やったほうがいいよ」とおすすめするのも。
「よくわからないので怖い、でもやりたい」ならば、情報を与えて、やり方を伝えれば始めるかもしれない。
だが、「面倒くさい」に対しては無力だ。
転職したことのない人に、「自分の市場価値を知っておいたほうがいいのでは?」と転職活動を推奨するのも。
「やったことないので怖い」ならば、いくらでも手法はある。
だが「面倒くさい」と言われたら、それでおしまいだ。
実は、「面倒くさい」というのは様々な感情に隠れて、最も強固に人間の活動を抑制している。
例えば、今の仕事のやり方に対して「効率わるい」と文句を言う人に、「じゃ、もっといいやり方を提案しなよ。」と言っても、何も提案しない人が圧倒的多数だ。
また、今の仕事が「つまらない」と文句を言う人たちに、「じゃ、転職するか、異動願いを出せばいいじゃない」と言っても、全く響かないだろう。
それは「面倒くさい」を言い換えているだけなので、あれこれ解決策を出してもダメなのだ。
*
だが「面倒くさい」は人に言いたくない。
職場で何か頼まれたときに、「面倒くさい」などと言おうものなら、「ダメなやつ」と思われるし、自分が面倒くさがりだと認識するのはプライドに関わる。
だから表側は皆、「効率が悪い」とか「費用対効果が合わない」とか、きれいな言葉で繕う。
実際そうかも知れない。
でも、私が知る限り、動かない理由の本音は殆どが「面倒くさい」だ。
だから私は、コンサルタントをやっているとき、
「費用対効果」とか
「効率」とか
「手順が定まっていない」とか
「リスクが見えない」とか
言う人たちは、ひとまず「面倒くさいんだな。」とみなして、できるだけこっちで面倒な部分を引き受けるようにしていた。
もちろん、彼らの体裁に配慮して、
「面倒くさいんですよね?」とか無粋なことは言わない。
「皆様には、大事な仕事に集中していただきたいので、こっちでやりましょうか?」
という。
「今ここでやりましょうか?」
も効果的だ。
そうすれば、少なくとも物事は進む。
逆に言えば「面倒な部分を引き受けてくれる人」はあまりいないので、非常に重宝される。
こうして、私は多数のクライアントを獲得した。
「知恵」ではなく「戦略」でもなく、「面倒を引き受けてくれる人」のが、実は最も好まれる。
*
「企業」においては、上のように面倒なことを、泥臭くやってくれる誰かに全部投げてもいい。
それが賢い選択であるときもある。
だが「自分の人生」はどうか。
残念ながら、面倒で、泥臭いことが、必ず発生する。
例えば宿題。
例えば語学、プレゼンなどのスキルの習得。
例えば転職。
例えば新しい機会の獲得。
例えば体調管理。
例えばパートナーとの関係構築。
例えば親孝行。
例えば休暇を取ること。
こういったものに対して「面倒くさい」と逃げていては、あまり良い結果は期待できない。
前の記事で、「豊かさとは、経験のバリエーションのこと」と述べた。
しかし、バリエーションを獲得するためには、最大の障害である「面倒」を克服しなければならない。
「いつも同じこと」
「知っていること」
「やったことのあること」
「簡単にできること」
は、安心、安全ではあるが、経験のバリエーションを増やさないからだ。
「面倒だ」は、あらゆる意味で、人生を貧しくする。
だから結局のところ、「面倒」の克服こそ、豊かさを得る手段なのだ。
とすれば、我々はどうすべきだろうか。
これは、私のマネジメントの大きなテーマでもある。
一朝一夕に解決するものではない。
例えば、下のように様々な記事も書いた。
人は、記録をつけると、行動が変わる。継続できる。人生が変わる。
「なんでこんなに仕事が手につかないんだろう?」と悩む人に読んで欲しい話。
なぜ35歳を超えると頑張らなくなるのか。それはロールプレイングゲームの終盤と同じだから。
人に「意識改革」を求めてもあまり効果はない。仕組みからアプローチする。
行動したいなら、自分がそう遠くない将来に死ぬという事実について深く考えてみるといい
上を見るとわかるが、基本的に私は「仕組み志向」なので、機械的に努力を継続できる仕組みを作ってしまうのが楽だと思っている。
が、ストレートなメッセージも、時に役に立つ。
ともに頑張って生きよう。

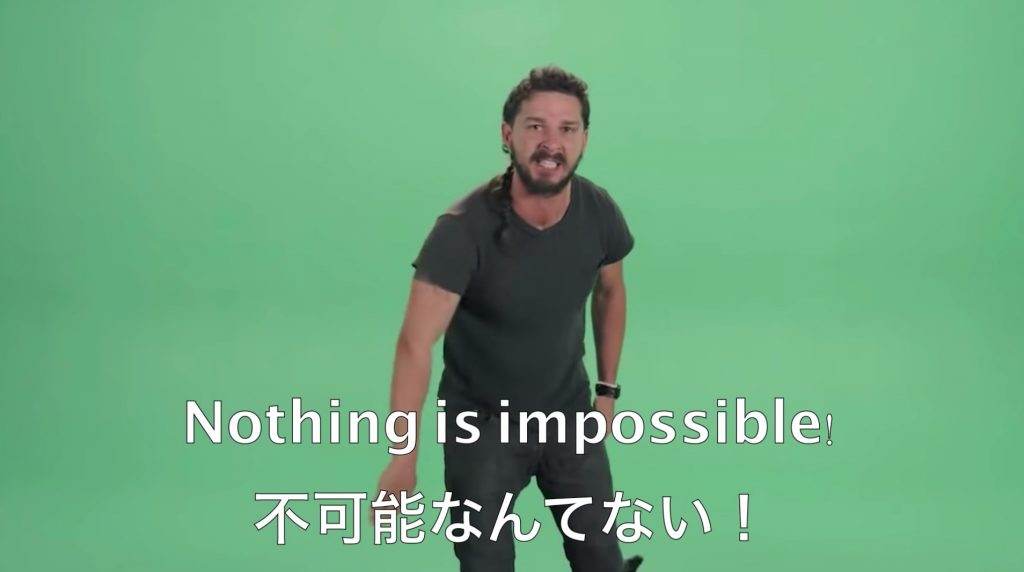


◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
(2026/01/19更新)
【著者プロフィール】
◯Twitterアカウント▶安達裕哉
◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)
◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)
◯ブログが本になりました。
(Photo by John Moeses Bauan on Unsplash)














