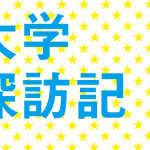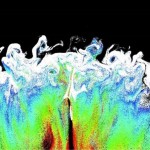慶応大学で最も特徴のあるゼミの一つ、「牛島ゼミ」。毎年多数の応募者があり、入ゼミ選考を経て現在ゼミに所属する人数は3・4年生合わせて40名近くです。
慶応大学で最も特徴のあるゼミの一つ、「牛島ゼミ」。毎年多数の応募者があり、入ゼミ選考を経て現在ゼミに所属する人数は3・4年生合わせて40名近くです。
そのゼミの責任者、牛島教授はどのような方なのか、何を研究対象としているのか、お聞きしました。

牛島利明 慶応義塾大学 商学部教授
近代日本経済史,産業史,経営史,地域経済論を専門とする。近現代における日本産業史・経営史の研究。日本産業の発展と衰退の過程を分析すること,および産業と地域経済とのかかわりについて検討することを主眼とし,また,近年では商業・サービス業や非営利分野にも関心を持っている。
ゼミwebページ http://gyuzemi.jp
―どのような分野を専門としていらっしゃるのでしょう?
そうですね、私は産業史、経営史を専門としていますが、もう少し深く言えば「衰退のマネジメント」に非常に興味があり、研究対象としています。
―「衰退のマネジメント」とは?あまり聞いたことがありませんが…
一般的には成長を対象とするのが一般的ですが、あえて成長を扱うのではなく、「衰退」を扱います。例えば日本における石炭産業の衰退や限界集落の発生、あるいは小さな商店街などがそれに当たります。
―面白いですね、なぜそのようなことにご興味を持たれたのですか?
自然に、なんとなくそうなっていた、というのが正直なところです。もともと、地域経済に関心があり、地域系のテーマを扱っているうちに衰退する地域を数多く目にしたからだと思います。
―具体的には、どのようなことが起きていたのでしょう?
衰退時には政府、自治体などが政策として手を差し伸べていることが数多く有りますが、政策が介入することで、衰退が歪むケースが見受けられます。
当然のことながら、長期的視点では永遠に成長しつづけるものはありません。時代とともに古いものが衰退し、新しいものに移り変わることで、全体の活力が保たれます。
ところが、政策が介入することで速やかに衰退させるべきものが延命され、かえって状況が悪くなることがあるのです。また、逆に衰退しているものの中から新しい考え方、価値観が生まれ、イノベーションをおこすこともあります。それを考えれば衰退することは、必ずしも悪いことだけは言えないでしょう。
―ゼミ紹介を拝見しましたが、「全ての人が楽しめるまちづくり」など衰退というテーマ以外にもかなり多くの研究対象があるようですが?
はい。実は「今の社会できづらさを感じている人々」や、いわゆる「社会的マイノリティ」の方々にも着目しています。具体的には障害者、外国人、LGBTの方々などです。
―なぜ、マイノリティの方々に着目しているのでしょう?
「停滞」と言うのは、メインストリームが行き詰まっているから停滞なのです。そこで色々と停滞を打開しようと皆動きますが、そこで必要なのは、「多様性」、つまり新しい、従来とは異なったものの見方です。
メインストリームが行き詰まったら、メインストリームの範囲で考えていたら、突破できないのです。 ではその見方を提供するのは誰か、何かといえば、たとえば「社会的マイノリティ」と呼ばれるような人々ではないか、と思いました。
彼らの視点を学ぶことで,我々の固定化されたものの見方を相対化することができると考えています。 これは「衰退」にも同じことが言えます。「成長」だけを見ていては、成長が止まった時に新しい発想が出てこない。そこで衰退の中でもがきながら新しい何かを生み出そうとする動きに着目するわけです。
―ゼミの学生たちに、変わった指導をしている、とお聞きしましたが?
そうですか?基本的には、さきほどご紹介した考え方に基づいて、指導をしています。ただ、このゼミは「指針は示すが、あとは自分たちで考え、自由に何をやってもよい」と言っています。

―なぜそのような考え方で指導なさっているのですか?
まず学生が、受験などの「わかりやすい評価指標」や「正解のかならずある作られたプログラム」の中でしか生きてきていない、という問題意識がありました。働けば皆わかりますが、世間にはわかりやすい指標や、絶対の正解などというものはほとんどない。
そしてまた、学生は、同世代の限られたコミュニティの中で生活しており、それ以外の価値観にほとんど触れたことがありません。すごく、同質的で、閉ざされています。それも問題です。
そういった背景もあり慶大生は特に、大企業に入りたいという価値観や志向が強いと思います。彼らの選択肢として、有名な大企業に入る、がとりあえずの正解であって、彼らなりの成功なのです。
でも、彼らはそれ以外の選択肢を持ちあわせていない。もちろん、疑問を持っていないわけではないでしょう。が、それ以外に世界がないのです。
でも、少し考えてみれば人生もっと色いろ選択肢があります。立ち止まって考えた時に、どれだけ広い世界観を持っているか、大企業に居るとしても、違う価値観を知っているか、そういったことが、豊かな人生を作る。もしかしたら新しいビジネスチャンスを生み出すきっかけになるかもしれない。
ゼミに入ってきた学生に、やりたいことを出してもらうと、
「有名テーマパークの戦略について」
「有名ゲーム会社の動向について」
など、だいたい画一的なテーマが上がってきます。でもこれは、世界を消費者目線でしか捉えることができていない証拠です。私は、その立場ではないところからものを見る感覚を身につけてほしいと思っています。
だから、彼らの住んでいた世界と全く異なる世界、たとえば限界集落やマイノリティの方々をテーマに、フィールドに出て行ってもらうのです。
―自由すぎてついてこれない学生もいるのでは?(笑)
そうですね、起こり得ます。誰かに何かを期待して、受け身になってしまうケースも多いと思います。ですが、逆に意外に頑張る学生も中には出てきます。
ビジネスではありませんので、儲けなくていい、と言うのはできる事が結構多いのです。言ってしまえば採算を考えなくていいのが、大学のメリットです。失敗してもダメージを受けることもない。
とは言え、表層的な部分だけを見て「楽しいことができそう」という感覚で入ってくる人も多いですが、お金がかけられない分、やってみたら泥臭くて大変だった、という人が多いと思います。
まあ、10年たったとき「あの時の経験は良かった」と思ってもらえればいいのですが。
―具体的には、どのような学生たちの取り組みがあったのでしょうか?
例えば、宮城県の養豚農家との取り組みが有ります。
その養豚家は30代の女性なのですが、震災で豚舎が壊滅的な被害を受けて、飼育している豚も2000頭から100頭になってしまった。大ダメージです。まだ完全に復旧しておらず、未だに仮の場所で養豚を続けているのです。
ただ、その養豚家の方は、元の経営に戻したい、とも思っていないのです。養豚のあり方を考えなおすいい機会だ、と捉えています。
具体的には、「アニマルウェルフェア」という考え方があります。豚を豚らしく、遊び回らせて育てるといった、飼育に対する考え方です。まだわずかな頭数ですが、このようなことに共感する方々に、高付加価値商品として販売しています。
これは、震災で大きな被害を受けながらも、あたらしい価値を見出し、いままでできなかったことを追求するきっかけとなったよい事例です。
学生はそういった養豚家の方のところへ、夏休みに会いに行き、スペースを作る手伝いなどをしました。また、大きくなって出荷できるようになったら、1頭丸ごと買って、調理して食べることもします。
私たちは豚肉を毎日のように食べていますが、生産者の方と知り合って、その思いを感じ、一頭の豚と携わり、最後に料理になるプロセスを体験するのは生産・流通の全貌を理解し、問題意識を持つためにいい経験ではないでしょうか。
もう少し活動が進めば、単に買って食べるというだけではなく、サプライチェーン全体を見直し、豚を売ることで利益を出すこともチャレンジして欲しい。買っていただくためには、豚の価値や生産者のアピールが必要だが、そういったことも活動の一環です。
生産者の方々に感銘を受け、価値観が変わる学生もいます。
―学生の指導に非常に熱心なので、驚きました。
正直に言いますと、もう15年間ゼミをやっていますが、当初は今ほど熱心ではありませんでした。ほどほどで良いか、と最初は思っていたのです。
ただ、学生に関わると中には食いついてくる学生もいる。学生が頑張ると、こっちも引きずられて頑張ってしまう。そうするとと、ではさらにもう一つやろうじゃないか、と。こうして年々、発展していき、手応えがある方向に進んでいったのです。
私自身も、学生から新しい世界を教えてもらってきました。その相互作用がある限りは楽しくできるのではと感じています。
―牛島先生、良いお話を、ありがとうございました。
製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)
単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。
本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】
・開催日:2026年2月12日(木)
・時間:12:00〜13:00
・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)
・参加費:無料(定員150名)
本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者
・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者
・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方
・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者
【セミナーの内容】
・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)
・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)
・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換
・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有
【登壇者】
奥田 真輔 氏
システム開発やITコンサルティングを経て、
外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、
メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。
現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、
日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。
岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)
野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。
その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。
BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。
WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。
2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。
【お申込み・詳細】
こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。
【バックナンバー】
【大学探訪記 Vol.15】起業イベントで出会う大学生ってどんな人か?
【大学探訪記 Vol.14】建築材料ならお任せ!俺たちコンクリート研究チーム。
【大学探訪記 Vol.13】ビルやダムなどの巨大なコンクリート構造物を長持ちさせるにはどうしたら良いのか?
【大学探訪記 Vol.12】R社に就職が決まってしまう大学生とは
【大学探訪記 Vol.11】監視カメラの画像から、街における「人の挙動」を人工知能で明らかにする
【大学探訪記 Vol.10】池の水を少し汲めば、その池に住む生物がわかる。そんな魔法のような話、あるんでしょうか?
【大学探訪記 Vol.9】1年に13万件ある日経新聞の記事を、人工知能の一分野「機械学習」によって分類・分析する。
【大学探訪記 Vol.8】雲とチリの相互作用を、スーパーコンピュータで再現する。
【大学探訪記 Vol.6】スーパーコンピュータ「京」で社会のしくみを解き明かす
【大学探訪記 Vol.5】銀幕スターを通じて「戦後の日本人」を解き明かす
【大学探訪記 Vol.4】ベトナムの人材育成を支援したい!と、ベトナムに単身渡る女子大生
【大学探訪記 Vol.3】プロ野球に統計学を適用するとどうなるか?
【大学探訪記 Vol.2】1本の木を植えるとどんだけ気温が下がるのか?
【大学探訪記 Vol.1】東大のNicogoryというスタートアップを訪ねました